飲食店を閉店するときの賠償責任とは?失敗事例と回避するための対策を解説

飲食店を閉店する際、思わぬ賠償責任に直面するオーナーも少なくありません。賃貸契約に基づく原状回復工事や契約違反による違約金、さらに従業員や取引先との関係トラブルなど、「知らなかった」では済まされない事態から多額の費用を請求されるケースもあります。本記事では、飲食店を閉店するときの賠償責任とは何かをわかりやすく解説し、実際に起きた失敗事例を紹介しながら、トラブルを避けるための対策をお伝えします。これから閉店を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
飲食店オーナーが閉店時に直面しやすい主なリスク
飲食店を閉店する際、オーナーは契約や人材、資金面など幅広いリスクに直面します。たとえば、賃貸契約に基づく原状回復義務や違約金、従業員の解雇手続きや給与精算、リース契約の残債や取引先への未払い債務、さらに顧客への安全管理上の責任まで、多岐にわたります。これらを十分に確認せずに閉店を進めると、高額な費用請求や訴訟に発展する恐れもあり、オーナーに大きな負担となりかねません。
飲食店の閉店でよくある賠償責任トラブル事例
飲食店を閉店する際には、賠償責任に関わる思わぬトラブルに直面することがあります。なかには高額な費用や法的責任を負わされるケースもあり、その後の生活や再出発に影響を与えることも。ここでは、飲食店の閉店時によくある賠償責任トラブルの事例を紹介します。
事例1. 原状回復工事で高額請求を受けた
飲食店がテナントを退去する際、賃貸契約に基づいて「原状回復工事」が必要なのが一般的です。しかし、契約内容を十分に把握していないと、工事見積もりが想定を大きく超えるケースも少なくありません。
千葉県の居酒屋チェーン店では、閉店時に原状回復を求められ、厨房設備やダクトの撤去まで指定されました。最終的に820万円もの高額請求を受け、追加費用の捻出に苦慮したといいます。また東京都のファーストフード店では、契約書にはない工事を指定され、数百万円の追加請求を受けました。裁判になった結果、本来必要な工事のみ負担で済んだという事例も確認されています。
敷金や保証金が工事費に充てられて返還されないというトラブルも多く、閉店後の資金繰りに影響を与える一因になっています。契約時に原状回復の範囲を明確にし、工事見積もりには貸主にも同席してもらうことが重要です。
事例2. 従業員の解雇トラブルに発展した
飲食店を閉店する際、従業員の解雇手続きが不十分だと賠償責任に発展することがあります。特に、突然の解雇通知や賃金未払いによるトラブルは少なくありません。
大阪市内のイタリアンレストランでは、閉店のわずか1週間前にスタッフへ解雇を告げました。解雇予告手当も支払わなかったため、従業員から未払い賃金と手当を求めて労基署へ申告され、最終的に80万円超の支払いを命じられました。別の居酒屋チェーンでは、残業代未払いが閉店時に一斉に請求され、数百万円規模の清算に追われています。
労働基準法では、解雇日の30日以上前に予告することが義務付けられています。予告期間が30日に満たない場合、解雇予告手当の支払いが必要です。突然の解雇通知はこの規定に違反し、賠償問題へと発展しかねません。
閉店を決めた段階で早めに従業員へ告知し、就業規則や契約書に基づいて給与精算や手続きを進めましょう。必要に応じて社会保険労務士に相談すれば、実務的なアドバイスを受けられて安心です。
事例3. 取引先や金融機関への未払いが大きな負担となった
閉店時に取引先や金融機関への未払いが残っていると、深刻なトラブルに発展することがあります。仕入れ先への買掛金やリース契約の残債は閉店後も消えず、支払いを求められるのが一般的です。
東京都のラーメン店では、閉店時に厨房機器リースの残債200万円を一括清算するよう求められました。さらに酒販業者への未払いも重なり、オーナーは資金繰りに行き詰まって自己破産を選ばざるをえませんでした。大阪市内のカフェでは銀行からの借入金が残っていたため、廃業後も返済が続いた結果、経営者個人が連帯保証人として追及されました。
閉店を決めた時点で取引先や金融機関へ早めに相談し、分割払いや債務整理を検討することが重要です。場合によっては弁護士へ相談することで、最適な解決策を得られるでしょう。
事例4. 顧客の事故や食中毒で賠償責任を負った
飲食店を閉店する直前でも、顧客に対する安全管理の責任はなくなりません。店舗内での転倒事故や、提供した料理が原因の食中毒などが発生すると、閉店後であっても賠償責任を問われる可能性があります。
名古屋市のある和食店では閉店準備中に来店客が床で転倒し、治療費や慰謝料として約150万円を請求されました。福岡市の居酒屋では、閉店直前に提供した料理が原因で集団食中毒が発生し、保健所からの指導とともに損害賠償を求められたケースがあります。
閉店が決まっていても、顧客への責任は最後まで継続するという認識が大切です。日々の清掃や設備の点検を怠らず、安全管理を徹底しましょう。あわせて、施設賠償責任保険やPL保険(生産物賠償責任保険)の補償範囲を事前に確認しておけば、万が一の際にもリスクを軽減できます。
飲食店を閉店する際にオーナーが負う責任範囲
飲食店の閉店にあたって、オーナーが負う責任は多方面に及びます。従業員、家主(不動産所有者)、取引先や金融機関、顧客といった関係者に対してそれぞれ異なる対応が求められます。主な責任範囲を説明します。
家主(不動産所有者)に対する責任
テナントを借りて飲食店経営を行っている場合、賃貸借契約に基づく責任が発生します。多くの賃貸契約には原状回復義務が定められており、入居時の状態に戻す工事が必要です。飲食店の場合、内装や設備をすべて撤去するスケルトン工事を求められることが多く、数百万円単位の費用が発生するケースもあります。
また、解約には一般的に3〜6か月前の解約予告が必要です。告知が遅れると、その期間分の家賃を余分に支払うことになります。敷金や保証金も未払い家賃や工事費用に充てられ、戻らない場合があります。
居抜き譲渡を行うことで原状回復工事などの費用を抑えられますが、その際、事前に家主の承諾が必要です。契約内容を早めに確認し、計画的に進めることが賠償責任トラブルを防ぐポイントです。
従業員に対する責任
飲食店を閉店する際の解雇(整理解雇)では、労働基準法に基づき、解雇日の30日前までに予告する義務があります。30日に満たない場合は不足日数分の平均賃金を「解雇予告手当」として支払います。解雇通知はトラブル防止のために書面で行い、記録を残しておきましょう。
未払いの給与・残業代、退職金(規定がある場合)は速やかに精算します。アルバイトやパートを含む全従業員が対象で、対応を怠ると労働基準監督署からの指導や訴訟に発展する恐れがあります。
解雇後は、健康保険・厚生年金・雇用保険の資格喪失届と離職証明書(離職票)の速やかな交付が必要です。怠ると従業員が失業給付をスムーズに受給できずに不利益が生じかねません。万が一、経営破綻で賃金支払いが困難な場合は、国の未払賃金立替払制度の利用を従業員へ案内すると良いでしょう。
従業員には閉店の理由や今後の対応を丁寧に説明し、誠意を持って接します。そして適切な手続きを進めることで不要なトラブルを防ぎ、円満な閉店につながります。
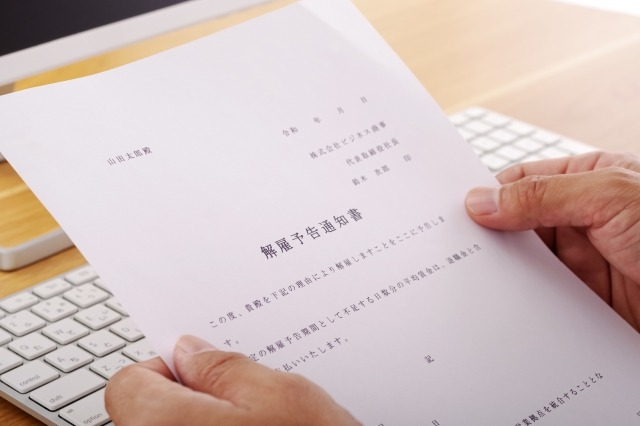
取引先に対する責任
仕入れ業者やリース会社への対応も大切です。買掛金を放置すると信用を失うだけではなく、法的措置に発展する恐れもあります。閉店を決めたら、早めに取引先へ連絡し、これまでの取引への感謝とともに支払い予定を明確に伝えます。
売掛金と買掛金がある場合は、相殺できるかどうかを相談してみると現金支出を減らせることも。酒類や食材などの在庫は取引先に引き取ってもらうか、計画的に消化するなどして処分を進めましょう。厨房機器などリース契約中の設備があれば、残債や違約金を確認します。一括清算が難しければ分割払いを交渉してみるのも有効です。
金融機関に対する責任
金融機関からの借入金は、閉店しても返済義務は消えません。個人事業主の場合、事業の借金は個人の借金と同一とみなされ、閉店後も返済を続ける義務があります。法人の場合でも、多くはオーナーが連帯保証人となっており、会社が返済できなければ個人が責任を負います。
閉店が決まったら速やかに金融機関へ連絡し、返済計画の見直し(リスケジュール)を相談しましょう。無断で返済を滞らせると信用情報に傷がつき、将来の融資にも影響します。金融機関との交渉や返済が難しい場合は、弁護士や税理士に相談して債務整理や事業譲渡を検討するのもひとつの選択肢です。専門家のサポートを得ることで、最適な解決策を見つけやすくなります。
顧客に対する責任
飲食店を閉店する直前であっても、顧客への安全管理責任は最後まで続きます。店舗内で転倒事故が起きたり、提供した料理が原因で食中毒が発生したりした場合は閉店後であっても損害賠償を求められる可能性があります。特に飲食店は食品を扱う業態のためリスクを軽視できません。
トラブルを避けるには閉店直前まで清掃や設備点検を怠らず、食品管理を徹底します。さらに施設賠償責任保険やPL保険(生産物賠償責任保険)の補償範囲を確認しておくことも大切です。保険の有効期間を見直し、閉店後も事故リスクに備えた補償が継続されるのかどうかを再確認しましょう。顧客への責任を最後まで果たし、万が一の際にも備えておくことが、信頼を守り円満な閉店につながります。
行政機関に対する責任
飲食店を閉店する際には、税務署や自治体、保健所、警察署といった複数の行政機関への手続きが必要です。手続きを怠ると、罰則や追徴課税といったペナルティが科される可能性があります。
個人事業主は税務署に廃業届を提出します。同時に、青色申告の承認取り消しや消費税に関する手続きも行いましょう。都道府県税事務所にも廃業届の提出を求められる場合があります。法人の場合は、法務局での解散・清算登記に加え、法人税の最終申告が必要です。個人事業主、法人いずれの場合も、閉店に伴う確定申告や最終的な税務申告を忘れずに行いましょう。
飲食店の場合、管轄の保健所への廃業届の提出と営業許可証の返納が必要です。提出期限は地域によって異なるため、早めに確認してください。深夜に酒類を提供していた店舗は警察署に廃止届を、風俗営業の許可を得ていた店舗は許可証を返納しなければなりません。これらの手続きを怠ると罰則が科される恐れがあります。
行政手続きや税務処理は後回しにせず、必要に応じて税理士や社会保険労務士などの専門家に依頼するのもおすすめです。適切な手続きを行うことで、余計なリスクを避け、スムーズに事業を終えられます。

飲食店閉店時の賠償責任を回避するための対策
飲食店の閉店に伴う賠償責任は、適切な準備と対応によって大きく軽減できます。ここでは、オーナーが実践すべき対策を5つ紹介します。
契約内容と貸主承諾を早めに確認する
賃貸借契約に記載された解約予告期間や原状回復義務の内容を早めに確認しましょう。認識不足のまま退去を進めると、違約金や高額な工事費を請求される恐れがあります。特に居抜き譲渡を検討する場合は、家主の承諾が必須です。承諾を得ずに進めると契約違反となり、賠償責任を問われる可能性があります。
リース契約を整理する
厨房機器や什器などをリース契約している場合、原則として途中解約はできません。残債の一括清算や違約金が発生するのが一般的です。閉店前に契約内容を確認し、リース会社に精算方法を相談しましょう。居抜き譲渡で次のテナントが契約を引き継げれば、残債を回避できる可能性があります。
内装・設備を点検・メンテナンスする
内装や設備を良い状態に保つことで、退去時の原状回復費用を抑えることが可能です。特に居抜き譲渡を検討している場合、メンテナンスが行き届いていれば、査定額のアップにつながるでしょう。厨房機器や水回りなどを日頃から点検・整備しておくことは、事故や食中毒を防ぐうえでも重要です。
居抜き譲渡を活用して費用負担を抑える
居抜きでの譲渡を選択すると、原状回復工事をせずに内装や設備をそのまま次の借り主に引き渡せるため、大幅に工事費用を削減でき、閉店コストの軽減につながります。さらに、設備や什器を譲渡することで譲渡金を得られる可能性も。リース契約の引き継ぎが認められれば、残りの支払いをせずに済むというメリットもあります。
専門業者に相談し無料査定を受ける
内装や設備の市場価値は、専門業者の査定により客観的に把握できます。査定結果は家主や次の借り主候補との交渉材料になり、有利に話を進められる可能性があります。居抜き物件に強い専門業者に相談すれば、費用負担の軽減やスムーズな譲渡が期待できます。
「買取の神様」では、飲食店の閉店や移転をお考えのオーナー様に向けて居抜き売却のご相談を承ります。弊社では、一般的な不動産会社で発生する仲介手数料や企画料は不要です。また、グループ会社で10業態100店舗以上の開業および経営経験があり、どのような物件でも柔軟に対応可能です。管理会社や家主との交渉も代行し、オーナー様が閉店業務に専念できるようサポートいたします。査定・相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
飲食店の閉店なら「買取の神様」にお任せください
飲食店を閉店する際には、多岐にわたるリスクが伴います。準備不足のまま進めると、高額な賠償責任や思わぬトラブルに発展しかねません。契約内容の早期確認やリース契約の整理、設備メンテナンスなどを適切に行えば、費用や負担を大幅に抑えることが可能です。さらに居抜き物件として次のテナントに引き継げれば、原状回復費用の削減だけでなく、譲渡金の獲得にもつながります。
飲食店の閉店を検討している方は、まずは「買取の神様」にご相談ください。 無料査定を通じて、あなたの店舗の価値を最大限に活かし、安心して次のステップへ進むサポートをいたします。


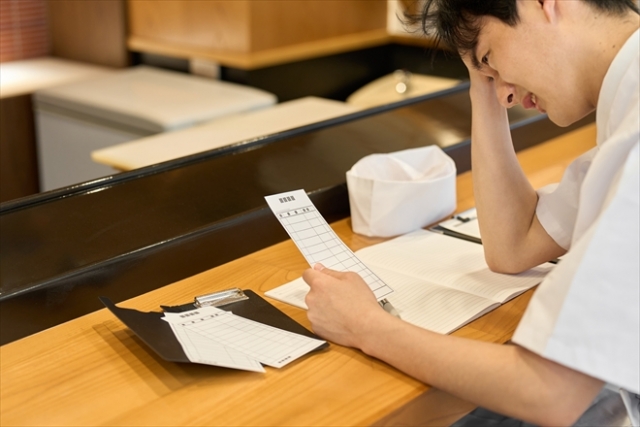





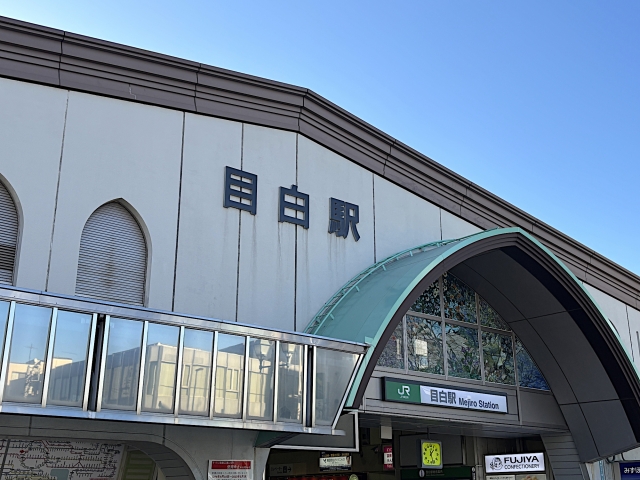




コメント