弁当屋の開業は儲かる?必要な許認可や具体的な流れ、失敗しないコツも解説

近年、ライフスタイルの多様化に伴い、手軽でおいしい弁当の需要が急増しています。弁当屋は比較的少ない資金で開業できる飲食業態ですが、「本当に儲かるのか?」と気になる方も多いでしょう。本記事では、弁当屋の開業に必要な許認可や具体的な流れを解説するとともに、失敗しないためのコツも紹介します。
弁当屋の開業は儲かる?弁当屋を取り巻く現状
近年、日本の食市場では弁当を含む「中食」の需要が大きく伸びています。一般社団法人日本惣菜協会「2024年版惣菜白書」によれば、2023年の惣菜市場規模は 10兆9,827億円(前年比+4.9%) に達し、今後は11兆円を超える見込みです。また、2013年から2022年までの成長率で見ると、中食は 117.6% と内食(113.8%)を上回っています。
共働き世帯の増加や生活スタイルの多様化を背景に、「家庭外で調理されたものを家庭や職場で食べる」という形態がすっかり定着しました。外食需要が伸び悩む中でも、中食は食生活を支える存在として欠かせない位置を占めています。業態別に見ると、過去10年でスーパーは約1.4倍、コンビニは約1.2倍に拡大。特にコンビニ弁当や総菜コーナーは、日常的に利用される「生活インフラ」として認知されています。弁当は中食市場の中心的存在として、今後も安定した需要が見込めるでしょう。
弁当屋を開業するメリット
弁当屋の開業は、飲食業態の中でも比較的始めやすく、安定した需要が見込める分野です。ここでは、弁当屋を開業する具体的なメリットとして4つ紹介します。
消費者の購入機会が多い
消費者の食生活の中で、お弁当は手軽で栄養バランスの良い食事として受け入れられています。一般社団法人日本惣菜協会「2024年版惣菜白書」によれば、持ち帰り惣菜の中でも弁当の購入頻度はどの年代でも男女ともに高い傾向です。その背景には、「手軽で健康的で経済的」 という消費者の基本的なニーズに応えている点にあります。さらに、毎日の献立を考える手間を省き、和・洋・中華といった幅広いメニューから好みに合わせて選べることも弁当の魅力です。
外食制限時でも営業が可能
コロナ禍では、多くの飲食店が営業時間短縮や休業を余儀なくされましたが、弁当屋は「持ち帰り販売」という強みを活かし、営業を継続できました。外出自粛が求められる中でも安全な手段にて商品を提供できたため、経営への影響を最小限に抑えられました。弁当屋は社会情勢や規制の変化に柔軟に対応しやすく、景気の波に左右されにくい業態だといえます。
軽減税率の対象になる
持ち帰り弁当は、消費税8%の軽減税率が適用されるため、より低い価格での提供が可能です。10%の消費税が適用される外食に比べ、価格競争力を持てます。消費者にとって価格面での魅力があり、競合との差別化や継続的な集客につながります。
小規模・低資本で始められる
弁当屋は店舗を構えることなく、キッチンカーや宅配専門といった形態で開業することが可能です。比較的低い初期投資で開業できるので、スモールスタートを実現しやすい業態といえます。また固定費も最小限に抑えやすいのが特徴です。キッチンカーや宅配専門なら場所に固定されないため、消費者の動向やイベントに応じて柔軟に対応できることも大きなメリットです。
弁当屋の営業スタイルと資金の目安
お弁当屋には、実店舗を構える「店舗型」、キッチンカーで各地を回る「移動販売型」、自宅やレンタルキッチンを活用した「無店舗販売型(宅配・デリバリー型)」といったいくつかのスタイルがあります。
店舗型
店舗型は、弁当屋の中で最も一般的な営業スタイルです。実店舗を構え、調理から販売までを行い、顧客は来店して商品を直接購入します。対面販売は、接客を通じて信頼関係を築きやすく、リピーター獲得にもつながります。
売上は立地条件に大きく左右されます。オフィス街なら平日ランチタイムの会社員に、住宅地なら夕方以降の帰宅客の需要が取り込めるでしょう。特に人通りの多い場所に出店できれば、安定した売上が期待できます。一方、店舗の取得費や内装工事費、厨房設備費といった初期投資は、他の営業形態に比べて大きく、さらに家賃や光熱費といった固定費も毎月かかります。
一般的には600万円〜1,200万円程度の初期費用が必要とされますが、地域や店舗規模、内装の内容によって大きく変動します。事前に入念な市場調査と資金計画を立てることが成功の鍵です。
移動販売型(キッチンカー型)
移動型は、キッチンカーなどを使って弁当を販売する営業スタイルです。店舗を持たないので家賃などの固定費がかからず、車両の維持費や出店料のみで運営できます。イベント会場、公園、オフィス街など、需要の高い場所を選んで出店できる自由度の高さも魅力です。
初期費用は中古車で約200万円から、新車で約300万円からが目安。さらに車両のカスタマイズ費用がかかります。その他、原材料費やガソリン代、イベントの出店料といったランニングコストも必要です。
ただし、移動販売の場合、営業許可の取得や駐車場の確保、キッチンカーの設備基準などの規制をクリアする必要があります。また、長期的な成功を目指すには、安定した出店場所の確保が求められます。出店先との信頼関係を築きながら、柔軟に販売エリアを開拓していくことが大切です。
無店舗販売型(宅配・デリバリー型)
無店舗販売型は、実店舗を持たずに調理と配達を組み合わせて運営する営業スタイルです。自宅のキッチンやレンタルキッチンを活用して調理し、電話やウェブサイトなどを通じて注文を受け付け、自社や委託スタッフが配達します。店舗を持たないため家賃の安い場所で運営でき、立地の制約が少ない点もメリットです。
初期投資は小さく、厨房設備や在庫、人件費のみなら約100万円から開業可能といわれています。ただし配達用の車両がない場合は、購入やレンタル費用が追加されます。
オフィスや高齢者施設など特定の顧客と定期契約を結ぶことで安定収入を得やすく、地域密着型のサービスを展開しやすい特徴があります。自社配達であれば配達時間や温度管理を直接コントロールでき、品質面でも差別化が可能です。
弁当屋の開業に必要な資格や許認可
弁当屋を開業する際には、食の安全や衛生管理を徹底するためにいくつかの資格や許認可が必要です。ここでは、代表的な資格や許可について解説します。
【必須】食品衛生責任者
食品を取り扱う施設に、必ず1名以上設置する義務があります。食品衛生責任者は食品衛生法に基づいて指定され、施設の衛生管理や従業員への衛生教育を担当します。各都道府県の食品衛生協会などが実施する食品衛生責任者養成講習会を受講して取得するのが原則です。栄養士、調理師、製菓衛生師といった資格を保持している場合は、講習会が免除されます。
【必須】飲食店営業許可
飲食店営業許可とは、弁当を調理・販売するために必要な都道府県知事(保健所)の許可のこと。店舗の所在地を管轄する保健所に申請してください。申請には、施設の構造や設備が基準を満たしているかの確認検査が必要です。事前に保健所へ相談し、施設の設計段階から基準に適合するように準備しましょう。
キッチンカーで移動販売を行う場合も、別途、保健所の移動販売に関する営業許可が必要です。
そうざい製造業許可または食品の冷凍又は冷蔵業許可
取り扱う商品の内容や調理・販売の形態によっては、追加の許可が必要となる場合があります。
そうざい製造業許可
調理済みの総菜を大量に製造し、パック詰めして販売する場合に必要です。店頭販売だけでなく、スーパーなどへ卸す際などに求められる許可です。
食品の冷凍又は冷蔵業許可
調理済みの弁当や総菜を長期保存し、冷凍・冷蔵で販売する場合に必要です。インターネット販売やデリバリーで冷凍弁当を配送する営業スタイルを検討している場合は、事前に確認が必要です。これらの許可が必要かどうかは、営業スタイルや商品の提供方法によって異なるため、開業前に必ず管轄の保健所へ相談しておきましょう。
参考:一般社団法人日本惣菜協会「そうざい製造業における複数営業許可一覧」
道路使用許可
キッチンカーなどを利用して公道上で営業を行う場合には、「道路使用許可」が必要です。道路使用許可は公道を占有して販売活動を行う際に求められるもので、営業予定エリアを管轄する警察署に申請します。イベント出店や路上での営業を検討している場合は、開業準備の段階で忘れずに確認しましょう。
弁当屋の開業までの流れ【7ステップ】
弁当屋の開業で失敗しないためには、事前の準備と計画が大切です。弁当屋を開業するための流れをステップごとに説明します。
ステップ1. コンセプトを明確にする
コンセプトは、弁当屋の象徴といえる重要な要素です。オフィス街向け、学生向け、健康志向など、どんな弁当を誰に売るのかを明確にします。ターゲット層や商品の魅力を整理した軸を明確にし、差別化できるコンセプトを作りましょう。
ステップ2. 開業スタイルに応じて物件を決める
店舗型、移動販売型(キッチンカー型)、無店舗販売型(宅配・デリバリー型)など、営業スタイルに応じた物件を選びます。店舗型は人通りが多く、ターゲット顧客が頻繁に訪れる場所を選びます。移動販売型では、車両の購入や駐車場、厨房の確保が必要です。無店舗販売型では、自宅で作る、または厨房を借りるなど条件に応じて物件は変わります。交通の便や競合店の存在、地域の需要などを考慮しながら、最適な場所を見つけましょう。
ステップ3. 資金を調達する
資金計画を立て、必要な開業資金を調達します。自己資金、銀行ローン、家族や友人からの融資、補助金や助成金など調達方法を検討しましょう。正確な予算計画を立て、余裕を持った資金計画が安定経営につながります。
ステップ4. 外装・内装・設備工事を行う
店のコンセプトを意識し、イメージに沿って店舗の外装・内装のデザインを行い、厨房設備など必要な設備配置を計画します。店舗のレイアウトは、作業フローが効率的で顧客も快適に利用できるように考慮しましょう。
ステップ5. メニューを作成し、仕入れ先を決定する
弁当屋の成功は、どのようなメニューを提供するかに大きく左右されます。顧客のニーズに合わせて魅力的なメニューを考案し、同時に競争力のある価格設定を行います。さらに安定した仕入れ先を確保し、開業後のスムーズな運営を目指しましょう。
ステップ6. 集客方法を検討・実施する
弁当屋をどのように宣伝し、顧客を呼び込むかを具体的に検討します。ウェブサイトやSNSの活用、チラシの配布などターゲット層に合った宣伝戦略を立て、お店を認知してもらうことが大切です。開業後、安定して売上をあげるために、事前に集客方法を計画しておきましょう。チラシやポスティング、近隣オフィスや学校への営業、看板や店頭販促などのオフライン施策に加え、SNSやデリバリーアプリを利用したオンライン集客も検討します。
立地やターゲット層に応じて複数の集客方法を組み合わせれば、開業直後から顧客を呼び込む体制を整えられます。
ステップ7. 各種届出の提出
弁当屋の開業前に必要な届け出を行います。管轄の保健所からの飲食店営業許可、開業届、必要に応じたキッチンカー許可など、前述の「弁当屋の開業に必要な資格や許認可」を参考に申請してください。申請に必要な書類を早めに準備しておけば、スムーズに申請できます。
弁当屋の開業を失敗しないコツ
看板メニューを作る
弁当屋を成功させるには、店舗を象徴する「看板メニュー」が不可欠です。看板メニューは店の存在を強く印象づけ、口コミやSNSで広まりやすく、新規顧客の獲得にもつながります。競合店との差別化を図るため、オリジナルで記憶に残る料理や、地元の食材を活かした商品を開発しましょう。
立地の特性に合わせることも大切です。高齢者が多いエリアでは栄養バランスを配慮した健康志向のお弁当、学生街ではボリュームのあるスタミナ弁当など、ターゲット層に寄り添ったメニューが効果的です。
開店する立地を慎重に選ぶ
弁当屋の成功は、立地に大きく左右されます。開業する弁当屋のコンセプトやターゲット層に合わせて、立地を選びましょう。特に店舗型で営業する場合、どの場所に店を構えるかで売上が大きく変わります。通勤・通学の経路やオフィス街、商業施設の近くなど、ターゲットとする顧客が多く集まる場所を選ぶことが基本です。
衛生管理を徹底して信頼を築く
弁当は安全性が最も重視される食品の一つです。調理場の清掃、食材の温度管理、手洗い・消毒などを徹底することで、食中毒リスクを防ぎ、お客様からの信頼を得られます。清潔感のある店舗やスタッフの身だしなみもリピーターを増やす要因です。
レジ業務を効率化する
レジ業務のスムーズさにより、顧客満足度は左右されます。特にオフィス街での昼休み時間帯は、短時間で購入を済ませたい顧客が多いため、迅速な対応が欠かせません。
キャッシュレス決済やPOSシステムを導入することで、会計をスピーディーに進められます。キャッシュレスはお客様の利便性が高まるだけではなく、販売者にとっても現金管理の手間や盗難リスクを減らせるメリットがあります。また売上をデータで一元管理できるのも魅力です。
さらに、事前注文や事前決済の仕組みを活用すれば、ピーク時の待ち時間を大幅に短縮でき、顧客のストレス軽減につながります。レジ業務の効率化は顧客満足度を高め、リピーター獲得に直結するでしょう。
SNSを活用し、集客に力を入れる
集客には、積極的な情報発信が欠かせません。なかでもSNSは効果的で、InstagramやX(旧Twitter)を活用して弁当の写真や調理中の動画、新メニューやキャンペーン情報を発信することで、新規顧客の獲得やリピーターの定着につながります。ハッシュタグを使えば地域ユーザーにも届きやすく、口コミやシェアによる自然な拡散も期待できます。SNSはコストを抑えて始められる点もメリットです。加えて地域密着型の店舗であれば、チラシ配布やオフィスへのあいさつといった地道な営業活動を組み合わせることで、より確実に集客効果を得られるでしょう。
万全の準備で弁当屋の開業を成功させよう
弁当屋は他の飲食業態と比べ、小資本で開業できるのが魅力です。特に移動販売型や無店舗販売型であれば、物件費用を抑えられ、小規模からスタートして徐々に拡大していく戦略も可能です。開業にあたっては、食品衛生責任者の資格取得や営業許可の申請など、必要な資格や手続きを確実に行いましょう。そのうえで、独自のコンセプトや看板メニューを開発し、ターゲットに合わせた商品展開と価格設定を行うことが成功のポイントです。
現在、弁当屋の経営に悩んでいるなら、居抜き物件として売却し、新たなスタートを切る方法もあります。「買取の神様」は飲食店専門の買取業者です。500件以上の実績を持ち、大家や管理会社との交渉もしっかりサポートします。査定や相談は無料なので、まずは気軽に問い合わせてみてください。






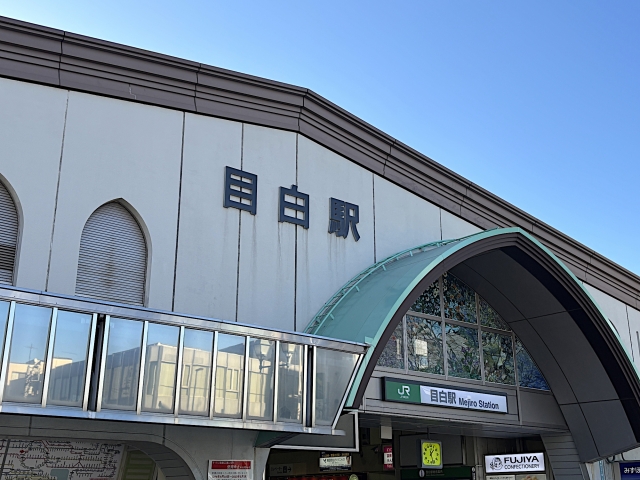






コメント