「バーテンダーの資格を取りたいけれど、どんな種類があるのだろう」「どの資格が自分に合っているのか分からない」このような思いを抱えている方も多いのではないでしょうか。
バーテンダーの資格は、飲食業界でのキャリアアップや独立開業に役立ちます。体系的な知識を習得して専門性を高めることも可能です。
この記事では、バーテンダーにまつわる資格や検定の種類、取得費用や期間からワインや日本酒、ビールなど、ほかの酒類の資格についても詳しく解説します。資格選びの参考として、ぜひ最後までお読みください。
バーテンダーにまつわる資格

バーテンダーにまつわる資格にはさまざまなものがありますが、ここでは、とくに有名な3つの団体が提供している資格を紹介します。
日本バーテンダー協会(NBA)
一般社団法人日本バーテンダー協会(NBA)はバーテンダーの資質向上を目指して発足した民間団体であり、多くのバーテンダーが入会しています。NBAが主催する資格には「バーテンダー呼称技能認定試験」と、その上位資格である「インターナショナル・バーテンダー呼称技能認定試験」があります。
バーテンダー呼称技能認定試験は、バーテンダーとして持っておくべき基礎的な知識やスキルを証明するもので、初めての資格取得を目指す方にもおすすめです。受験資格は、アルコールを提供している飲食業やサービス業に従事している、またはバーテンダーとして働いている20歳以上の方です。
試験は学科試験のみで「NBA新オフィシャルカクテルブック」に掲載されている酒類に関する知識が問われます。20問中18問以上正答(90点以上)で合格となります。
インターナショナル・バーテンダー呼称技能認定試験は、バーテンダー呼称技能認定試験の上位資格にあたります。協会に3年以上在籍し、実務経験が7年以上、かつバーテンダー呼称技能認定を取得して2年が経過した25歳以上のNBA会員のみが受験できます。
この試験は学科試験と実技試験の両方で構成されており、学科試験では酒類に関する知識と食品衛生に関する問題が出題されます。実技試験ではフルーツ・カッティングやシェイク、ステアといった基本的な技術が確認されます。両方の試験で合格点をクリアする必要があります。
出典:一般社団法人日本バーテンダー協会(https://www.bartender.or.jp/qualification/)
日本ホテルバーメンズ協会(HBA)
一般社団法人日本ホテルバーメンズ協会(HBA)では、5種類の認定資格試験を主催しています。主な資格として「HBAカクテルアドバイザー」と「HBAビバレッジアドバイザー」があります。
HBAカクテルアドバイザーは、一般の方も対象とした通信講座型の資格で、自宅で受講・受験が可能です。カクテルの知識を深めたい方におすすめで、20歳以上であれば経験を問わずに受験できます。
HBAビバレッジアドバイザーは、HBAバーテンダー資格を目指す方が最初に受ける試験で、バーテンダーの経験がない方や非会員の方でも受験できます。試験は筆記形式です。
HBAビバレッジアドバイザーの取得後は、会員限定の上位資格である「HBAバーテンダー」、「HBAシニアバーテンダー」、そして最上位資格の「HBAマスターバーテンダー」へと段階的に目指すことができます。上位資格に進むには実務経験や年齢、推薦などの要件が加わります。
出典:一般社団法人日本ホテルバーメンズ協会(https://www.hotel-barmen-hba.or.jp/license-list)
プロフェッショナル・バーテンダーズ機構(PBO)
NPO法人プロフェッショナル・バーテンダーズ機構(PBO)は、バーテンダーの育成と資質向上を目的として「プロフェッショナル・バーテンダー資格認定試験」を実施しています。
プロフェッショナル・バーテンダーズ機構は、バーテンダーとバーテンダーを目指す人々に向け、プロフェッショナルバーテンダーの養成や資質向上、カクテル創作・技術等の教育・研鑽を通じて、カクテルを中心とする酒文化の発展と、より豊かな生活の向上、文化の振興に寄与することを目指しています。
この試験は「バランスのとれたバーテンダーの育成」と「バーテンダーの資質の向上」を目的としています。試験内容は、筆記による知識試験とカクテル調合による技術試験の2種類で構成されています。両方の試験で合格点をクリアすることが合格の条件です。
出典:特定非営利活動法人 プロフェッショナル・バーテンダーズ機構(http://www.pbo.gr.jp/accredit/)
バーテンダー資格取得のための勉強方法

バーテンダー資格を取得するための勉強方法は、大きく分けて独学と、通信講座や専門学校といった教育機関を利用する方法の2つのパターンに分類されます。それぞれの方法のメリット・デメリットを紹介しましょう。
独学で学ぶ
独学の主なメリットは、自分のペースで学習を進められることです。時間的な制約がなく、仕事をしながらでも空いた時間を活用して学習できます。また、参考書代と受験料のみで費用を最小限に抑えられる点も大きな利点です。
一方、デメリットとしては、効率的な学習計画を立て、モチベーションを維持するための工夫が求められる点が挙げられます。特に、カクテル作りのような実技スキルを独学で習得することは非常に困難であるという点に注意が必要です。
通信・専門学校で学ぶ
バーテンダー資格の取得に向けて、より体系的に知識とスキルを身につけたい場合には、通信講座や専門学校の利用がおすすめです。
主なメリットは、講師のサポートを受けながら体系的に学習できることです。とくに専門学校や民間のスクールでは、プロのバーテンダーからカクテル作りの技術を直接学ぶことができるため、実技試験対策に非常に有効です。
デメリットとしては、独学に比べて費用が高くなることが挙げられます。また、専門学校では2年程度の期間を要する場合があります。通信講座の場合でも、自宅学習のため、強い意志がなければ学習が途中で滞ってしまう可能性も考えられます。
バーテンダー以外の酒類に関連した資格

より幅広い専門知識を身に付けたいのであれば、バーテンダーにまつわるもの以外の酒類資格も同時に取得するとよいでしょう。多くの方がワインや日本酒の資格取得を目指しているのは、総合的な酒類知識が飲食業界でのキャリア形成に重要な要素となるためです。
とくにワインソムリエ資格と日本酒関連資格は人気が高く、それぞれ異なる特徴と取得メリットがあります。
ワインソムリエ資格
ワインソムリエ資格は、ワインの専門知識とサービス技術を証明する代表的な資格です。日本では主に2つの団体が認定を行っており、それぞれ異なる受験条件や試験内容を設定しています。
飲食業界での就職や転職に有利になることから人気が高く、どちらの団体を選ぶかによって学習方法や費用も変わってきます。
日本ソムリエ協会認定資格「ソムリエ」
日本ソムリエ協会(JSA)認定のソムリエ資格は、実務経験を重視した資格です。受験には飲食サービスなどの3年以上の実務経験と、試験時点でその職に従事していることが条件となります。
試験は第1次(筆記試験)、第2次(テイスティング・論述)、第3次(サービス実技)の3段階で構成されており、全体合格率は約30%と高い難易度を誇ります。受験費用はJSA会員であれば17,210円、一般の場合は25,440円です。スクール利用の場合、受験料や教材費を含めた総費用は約10万円〜15万円かかります。
出典:一般社団法人日本ソムリエ協会 呼称資格認定試験 (https://www.sommelier.jp/exam/index.html)
全日本ソムリエ連盟認定資格「ソムリエ」
全日本ソムリエ連盟(ANSA)認定のソムリエ資格は、実務経験を必要としない教育重視の資格です。NPO法人FBOの団体のひとつであるANSAが認定しており、受験資格は申込み時に満20歳以上であることのみとなっています。
こちらのソムリエ資格は、ワイン業界での経験がない愛好家やキャリアチェンジを考える方にも門戸を開いているのが特徴です。資格取得は講習カリキュラムの受講後に筆記・記述試験を第5次試験まで受験する仕組みとなっています。
学習内容は酒類・飲料の基礎知識、世界の食文化、テイスティング、サービスの基本など幅広く設定されています。通信コースも用意されており、課題提出による資格取得も可能と、柔軟性を備えています。
合格者にはワインコーディネーターまたはソムリエの呼称から選択でき、認定証書とバッジが授与されます。取得期間は最短2日〜1年で、費用はコースによって異なります。
出典:日本酒サービス研究会(SSI) 認定資格 (https://ansa-w.com/qualification/)
日本酒の資格
日本酒に関する資格は、近年の日本酒ブームにより注目度が高まっています。基礎的な検定から専門的な資格まで数多くの選択肢が存在し、日本酒の奥深い世界を体系的に学ぶことが可能です。
これらの資格を取得することで、飲食店での提案力向上や日本酒業界での活動に役立ちます。ここでは、数ある日本酒の資格の中からとくにおすすめの3つをご紹介します。
日本酒検定
日本酒検定は、5級から1級まで6段階に分かれた段階的な資格です。初級レベルの5級・4級では日本酒の基礎知識を身に付けて個人で楽しむことを目指し、中級の3級では知識を他者に伝える能力が求められます。
上級の2級では新たな楽しみ方を考案するレベルに到達し、最上級の準1級・1級では日本酒のすべてに精通して後世への継承発展を担える人材を育成しています。1級合格者は日本酒名人として認定される仕組みです。
受験料は5級・4級が各1,100円(税込)、3級・2級がCBT試験7,100円(税込)または会場受験6,000円(税込)、準1級・1級が会場受験6,000円(税込)となっています。日本酒の魅力を深く理解し、その知識を広く伝える能力を段階的に身につけられる資格といえるでしょう。
出典:日本酒サービス研究会(https://ssi-sake.jp/nihonsyu-kentei/)
唎酒師(ききさけし)
唎酒師(ききさけし)は日本酒サービス研究会(SSI)が認定する日本酒の専門資格です。この資格は単なる知識習得ではなく、飲み手に日本酒を美味しく飲んでもらうための実践的なスキルを身に付けることを目的としています。
1991年の制度開始から約34年にわたり継続的に運営しており、酒類業界で高い信頼を得ています。学習コースは6つの選択肢があり、2日間集中コースから通信コースまで受講者のライフスタイルに応じて選択可能です。
受講料は59,000円(税込)から99,000円(税込)で、合格率は84%と比較的高い水準を維持しています。日本酒の基礎知識やもてなしの技術を総合的に学べるため、飲食業界で日本酒の提供に関わる方に適した資格といえるでしょう。
出典:唎酒師(https://kikisake-shi.jp/#whats)
SAKE DIPLOMA(酒ディプロマ)
SAKE DIPLOMAは、日本ソムリエ協会が認定する日本酒と焼酎に特化した専門資格です。2017年に新設されたこの資格は、和食の無形文化遺産登録を背景として日本の伝統的食文化の普及を目的としています。
受験資格は満20歳以上のみで、国籍や職種、実務経験は不問です。一次試験は60分の選択式で行われます。二次試験ではテイスティング試験30分と、論述試験20分が実施されます。
受験料は一般1回受験で32,900円(税込)、2回受験で37,800円(税込)となります。合格後の認定登録料20,950円(税込)が別途必要ですが、年会費などの維持費用はかかりません。
出典:一般社団法人日本ソムリエ協会 2025年度 J.S.A. SAKE DIPLOMA認定試験(https://www.sommelier.jp/exam/exam_guidance_detail4.html)
ビールの資格
宴会やお祝いの席で長い間親しまれてきた、日本人と馴染みの深いビール。近年ではビアバーやクラフトビール専門店も増え、一昔前とはまた違ったビールの楽しみ方がメジャーなものとなってきています。話題性のひとつとして、ビールにまつわる資格を狙ってみるのもよいでしょう。
ジャパンビアソムリエ
ジャパンビアソムリエは、日本食文化とビールのペアリングに特化した国内認定資格です。全3回のオンライン講座で約3週間の学習期間を要し、受験を含めた費用は68,000円(税込)となります。
レポート課題、筆記試験、テイスティング試験による総合評価で認定され、資格取得後の維持費は不要です。日本のビール文化と食文化の組み合わせを学びたい方に適した資格といえます。
ディプロム ビアソムリエ
ディプロム ビアソムリエは、ドイツの醸造学校「Doemens」が主催している上級資格です。原材料から醸造工程、グラスまでビールの全体的な知識を身に付けられます。
講座は約6ヵ月でオンラインとリアルにて行われます。費用は講座受講料500,000円(税別)と受験・認定料50,000円(税別)で総額550,000円(税別)です。
こちらの記事では、バーの開業に必要な資格や届出についてくわしく解説しています。
資金の目安や開業の流れも取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
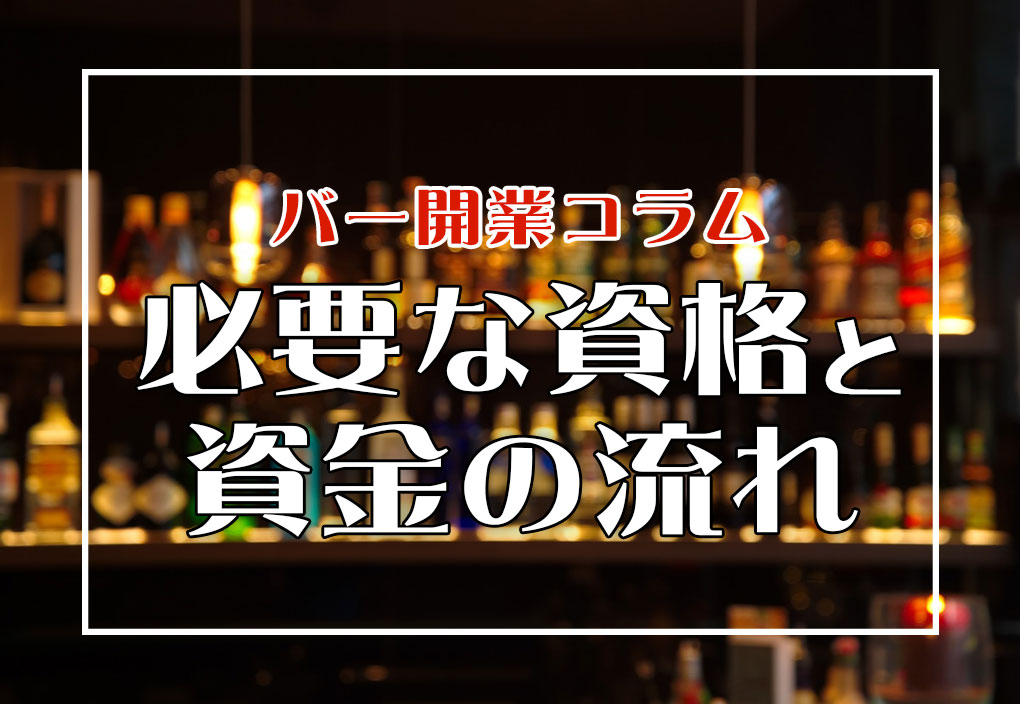
まとめ

バーテンダーに関する検定受講や資格取得は、飲食業界でのキャリアアップや独立開業を目指す方にとって価値の高い投資となります。これらは、飲食店やバーでの就職に有利になるだけでなく、将来的に自分の店舗を開業する際にも大きな武器となるでしょう。
とくに、オーセンティックバーやカクテルバーの開業を考えている方にとって、資格で得た知識は顧客への的確なアドバイスやメニュー開発に活かせます。さらに開業を具体的に検討する際には、初期費用を抑えられる居抜き物件の活用がおすすめです。
居抜きの神様では、初期費用や工期を大幅に抑えられる居抜き物件を豊富に取り扱っており、理想の店舗づくりをサポートしています。内装や設備が残されたままの物件を活用することで、初期投資を削減できるため、スピーディーな開業が可能です。開業をお考えの方は、ぜひご利用ください。













コメント