憧れのカフェ経営を実現するためには、夢や情熱だけでなく必要な資格や免許、申請などがあります。怠ると罰則や罰金が発生する場合もあり、適切な知識が必要です。
また、カフェ経営を成功させるためには、いくつか取得しておくとよい資格やポイントがあります。活用することで、店舗の信頼性向上や資金の確保などに役立ちます。
この記事では、カフェ経営に必要な資格や免許だけでなく、取得しておくと役立つ資格やカフェ経営を成功させる具体的なポイントについても詳しく解説します。
カフェ経営に必須の資格・申請は?

カフェの経営には、食品衛生責任者や防火管理者、営業許可申請などの必要な資格や申請があります。
無資格や無許可で営業すると罰則や罰金が発生する可能性があるため、十分に注意が必要です。そこでまずは、カフェ経営に必須の資格や申請について詳しく解説します。
食品衛生責任者
食品衛生法にもとづき、食品の製造や販売を行う場合は、食品衛生責任者の資格が必要になります。そのため、カフェの経営でも必須となる資格です。
食品衛生責任者の役割としては、食品の管理だけでなく、設備の衛生管理や従業員の健康管理における知識の提供などが挙げられます。食品を取り扱うため、正しい知識が求められ、適切な管理が必要になります。
食品衛生管理者の資格取得方法は、各自治体で開催される講習を受講後、保健所に申請することで取得できます。具体的な開催日などは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
また、栄養士や調理師、製菓衛生士など所定の資格を持つ人は、講習が免除になり窓口に申請するだけで取得できます。
※出典:一般社団法人東京都食品衛生協会「食品衛生責任者について」(https://www.toshoku.or.jp/training/seki-gaiyou.html)
防火管理者
防火管理者資格は消防法にもとづき、一定規模以上の事業所や施設で必須となる資格です。とくに、火災が発生した場合の初期対応や避難誘導、消火設備の管理などが求められます。
防火管理者資格には「甲種」と「乙種」の2種類があり、それぞれ求められる知識や担当する施設の規模が異なります。
資格の取得は、甲種が2日間で10時間程度、乙種は1日5時間程度の講習で取得可能です。そのため、乙種の方が比較的簡単に取得できるでしょう。しかし、乙種は甲種に比べ使用に制限がかかる点は注意が必要です。
※出典:東京消防庁「防火管理者が必要な防火対象物と資格」(https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/jissen/p04.html)
※出典:一般財団法人|日本防火・防災協会「防火管理者とは」(https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/guide_bouka.html)
飲食店営業許可申請
飲食店を開業する場合、飲食店営業許可申請が必要です。無許可で飲食店を経営すると、食品衛生法違反となり、懲役や罰金などの可能性があります。
飲食店営業許可申請は、管轄の保健所に申請し検査に合格すれば取得できます。許可申請にはいくつか必要な書類があり、食品衛生責任者の資格を証明する書類や飲食店営業許可申請書・見取り図・設備の配置図・内装配置の平面図などが必要です。
※出典:e-GOV「食品衛生法第55条・第82条」(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233/#Mp-Ch_11)
※出典:新宿区「営業許可等の手続きについて」(https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/file03_04_00001.html)
開業届
開業届を提出することで、控除の面で大きなメリットがあります。そのため、カフェを開業する場合は開業届を提出しましょう。
そもそも開業届とは、個人としてなんらかの事業を始める場合や廃業する場合に、その旨を届け出る際に提出が義務付けられている書類を指します。とはいえ、開業した年の事業収支をまとめて確定申告すれば開業届の代わりになり、開業届を出さなくてもとくに罰則等はありません。
ですが、開業届を提出する際に青色申告承認書も提出することで、条件が整えば最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。
また、個人事業主の場合、最長3年間赤字を繰り越せたり、家族へ支払った給与を経費計上できたりするなどさまざまなメリットがあり、気持ちの区切りだけでなく金銭的な面からもきちんと出しておいた方がよいでしょう。
※出典:国税庁「個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき」(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/07_3.htm)
※出典:国税庁「青色申告制度」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm)
社会保険の加入
法人の事業所は、従業員の人数に関わらず加入の義務があります。しかし、飲食店を含むサービス業の一部に区分される個人事業の場合は、従業員の人数に関わらず加入の義務はありません。そのため、オーナーの裁量で決められます。
社会保険に加入することで、傷病手当や出産手当金の支給対象となります。また、厚生年金保険に加入すれば将来もらえる年金額も増加するため将来的な不安解消にも役立ちます。
とはいえ、保険料は給与から差し引かれるため手取り額が減ってしまうため、事業主は従業員の希望を踏まえたうえで検討することが重要です。
※出典:日本年金機構「事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき」(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20130502.html)
労働保険の加入
労働保険は、労災保険と雇用保険の2種類あります。雇用形態に関わらず1人でも従業員を雇っている場合は、労働保険への加入が必要です。
労災保険は、労働者を対象とした労災事故などに必要な給付をする社会保険制度で、業務中の怪我や事故などが対象となります。一方、雇用保険は労働者が働けなくなった場合や失業した場合などに備えた保険です。
出典:厚生労働省「労働保険制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/980916_1.html)
カフェ経営に役立つ免許・資格は?

上記では、カフェの開業に必要な資格や申請について解説しましたが、必須ではないものの、持っていると役立つ免許や資格がほかにも存在します。そこで次は、カフェ経営に役立つ免許や資格について詳しく解説します。
調理師免許
調理師免許は、調理師法にもとづく国家資格で、調理法や栄養などの食に関する豊富な知識を証明できます。そのため、カフェではフードメニューの品質や味わいに対し高い信頼性をアピールできます。
また、調理師免許は食品衛生責任者の講習が免除されるため、より迅速な対応が可能です。調理師免許の資格取得は、専門学校や養成所で学び取得する方法か実務経験を積み試験に合格する方法のどちらかで取得できます。
実務経験を積んでから受験する場合、あくまで調理に関する実務となるので注意が必要です。また、実務経験の証明には、調理業務従事証明書が必要になるのでその点も覚えておきましょう。
※出典:公益社団法人|調理技術技能センター「調理師試験について」(https://chouri-ggc.or.jp/chourishishiken/all_delegation/)
栄養士免許
栄養士免許は、栄養学に関する豊富な知識を有していることが証明される国家資格です。そのため、栄養に関する専門家がいるという安心感を与えられます。食品を取り扱う事業所において信頼性や安心感は大きな魅力と言えます。
栄養士免許を取得することで得た知識は、栄養管理のできたメニューの作成や開発などに活用可能です。また、従業員に対して食に関する幅広い知識を持つ栄養士からの指導やアドバイスは、刺激にもなりモチベーション向上なども期待できるでしょう。
栄養士免許取得には、厚生労働省大臣が指定する養成施設で必要な課程を履修し卒業する必要があります。養成施設は、専門学校や短期大学、4年生大学などさまざまで、独学での取得はできません。
※出典:東京都保険医療局「栄養士・管理栄養士免許」(https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/kenko_zukuri/ei_syo/menkyo)
JBAバリスタライセンス
JBAバリスタライセンスは、日本バリスタ協会が主催している民間資格です。バリスタとして必要な専門的な知識が習得でき、コーヒーに関するスペシャリストとして活躍できます。
JBAバリスタライセンスはレベル1からレベル3まであり、JBA認定校でスクールを受講後、ライセンス試験に合格すれば取得できます。
バリスタとして従事している方やコーヒー関連の企業に勤めエスプレット抽出経験のある方、JBA認定校が別途開講するカリキュラムの必修課程修了後1年未満の方が受講可能な資格です。
※出典:日本バリスタ協会「JBAバリスタレベル」(https://jba-barista.org/license)
簿記
簿記は、お金の動きや取引内容を記録するスキルで、経理や会計、財務などで活かせる資格です。そのため、店舗の売り上げや仕入れ、税金などの管理に役立ちます。
利益計算や原価管理が上手くいかない場合、経営状況の悪化を招く可能性があります。そのため、売り上げの管理や仕入れ、税金、人件費など適切な管理が大切です。簿記の資格は、お金の動きや取引内容を適切に記録するスキルが身につくため、カフェの経営を円滑に進めやすくなります。
商工会議所が設けた高校や大学、専門学校などの教育施設で試験が受けられ、学歴や年齢の制限はありません。そのため、勉強すればだれでも取得できる可能性がある資格です。
社労士
社労士とは、労働や雇用、社会保険、公的年金などの分野で唯一の国家資格です。人事や労務管理に関する豊富な知識が身につくため、カフェの開業でも大いに役立ちます。
カフェの開業にあたって従業員を雇う場合、労働保険の加入が必要になり、任意で社会保険へ加入する場合もあります。人事に関する部分は、慎重かつ丁寧に進める必要があり、専門的な知識があれば適切な対応が取りやすくなります。
資格取得について、受験資格は学歴や実務経験、厚生労働大臣が認めた国家資格合格のいずれかを満たすことが必要です。
※出典:社会労務士試験オフィシャルサイト(https://www.sharosi-siken.or.jp/exam/)
カフェ経営を成功させるポイントは?

カフェの経営を成功させるためにはいくつかポイントがあり、実際に働くことやメニューの数を少なくすること、設備を整えることなどが挙げられます。
具体的なポイントを抑えておくことで、効率よく事業を進められるでしょう。そこで次は、カフェ経営を成功させる具体的なポイントについて詳しく解説します。
実際に働く
カフェ経営を成功させるためには、実際に働いてみることもひとつの方法です。実際に働くことで経験を積めるだけでなく、具体的なイメージが湧きやすくなります。
また、必要な設備やメニュー、忙しい時間帯など店舗の地域やコンセプトによっても変わります。ネット上に流れている情報以外にも、実際に働いてみることで得られる知識には実用性が期待できます。
メニューの数を少なくする
メニューの数を少なくすることもカフェの経営を成功させるポイントのひとつです。一見、メニューの数は多い方が消費者の要望に添った商品ラインナップが揃えられ、利用が増えると考えられます。
しかし、メニューの数が多いと食材費の増加や従業員の負担も多くなるだけでなく、人件費も増加する可能性があります。
メニューの数を絞りシンプルにすることで、消費者も注文が決めやすくなるため、1日のなかで多くの方に来店してもらえる環境が作れます。店舗における回転率は、売り上げを左右するため重要なポイントです。メニューの数を少なくすることで店舗の回転が良くなり、回転率向上が期待できます。
設備を整える
カフェ経営を成功させるためには、設備を整えることもポイントのひとつです。居心地の良さや快適性は、新規顧客の獲得だけでなくリピーターを増やすことにも影響します。
働き方改革や少子高齢化の影響で、通信環境が整っていれば仕事ができるモバイルワークなどの働き方が増えています。このようなモバイルワークをする人にとって、通信環境が整っている店舗は、商品以外でも魅力を感じやすくなるでしょう。
また、キャッシュレス化が進んでおり、現金を持たずに外出する方も少なくありません。そのような方にも対応可能な、キャッシュレス決済を導入することも有効な方法のひとつです。
同業者の経営者に人脈を広げておく
同じ業界の経営者に人脈を広げることで、メニュー選びのコツやノウハウなどを学べる可能性があります。そのため、同業の経営者に人脈を広げることもカフェ経営を成功させるポイントのひとつです。
カフェを開業する場合、さまざまな資格や申請、届け出などが必要になります。また、従業員を雇う場合、大きな責任を背負うこととなり、これまでとは違う環境になることから多くの不安を抱えることも考えられます。
そんなとき、同業の経営者に人脈を広げておくことで、状況に応じた具体的なコツやノウハウを学べるうえ、悩みの共有や相談相手として不安の解消にも役立ちます。
現実的な収支計画を立てる
カフェ経営を成功させるためには、現実的な収支計画を立てることが大切です。事業を継続していくにあたって、物価の高騰や設備の不調など予期せぬ出費が発生する場合があります。
このような事態に陥ったとき、現実的な計画が立てられていないと、冷静かつ適切な対応は難しくなるでしょう。
現実的な収支計画を立てる場合は、具体的な利益率や材料費、消耗品補充費、設備のメンテナンス費だけでなく、必要資金の具体的な調達方法なども事前に決めておくこと安心です。あらかじめ現実的な収支計画を立てることで、長期的に安定したカフェ経営がしやすくなります。
居抜き物件を利用する
居抜き物件を利用することもカフェ経営を成功させるポイントのひとつです。居抜き物件とは、前のテナントが使用していた内装や設備が残っている状態の物件で、改装費や設備費が節約できます。
そのため、初期費用を抑えて開業が可能です。また、初期費用を抑えて開業できることから、開業コストを早めに回収できる点も魅力のひとつです。
新規でカフェを開業する場合、物件の敷金や礼金だけでなく設備購入費用や内装工事費用なども発生します。そのため、多くの資金が必要となることが想定されます。
削減できた初期費用は運転資金としても活用できることから、余裕をもってカフェ経営を進めやすくなります。
こちらの記事では、カフェ経営が難しいとされる理由について解説しています。成功させるポイントも取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

まとめ

カフェ経営に必要な資格や申請は、食品衛生責任者や防火管理者、飲食店営業許可申請、開業届などがあります。従業員を雇う場合は、労働保険への加入が必要になるので注意しましょう。また、個人事業主の場合は任意ですが、法人の事業所であれば社会保険への加入も必要になります。
カフェ経営に役立つ資格は、調理師免許や栄養士免許、JBAバリスタライセンス、簿記、社労士などがあります。カフェの信頼性を高められるだけでなく円滑な経営にも役立つでしょう。
カフェ経営を成功させるポイントは、実際に働くことやメニューの数を少なくする、設備を整えるだけでなく、人脈を広げておくことや現実的な収支計画、居抜き物件の利用などが挙げられます。
なかでも、居抜き物件を利用することで、初期費用を大幅に削減でき、余裕をもって経営が進められます。
居抜きの神様では、飲食店開業を目指している方向けの小型物件を中心に、数多くの居抜き物件を紹介しています。居抜きの神様だけが取り扱っている未公開物件もあり、理想の物件をご提案いたします。気になる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
<併せて読みたい>
・取ってよかったおすすめ資格



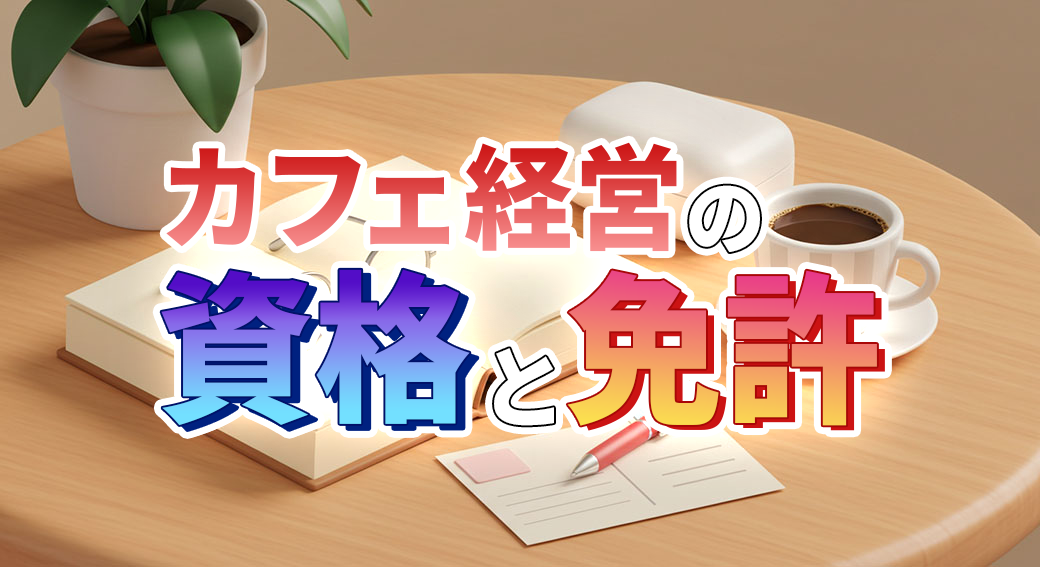









コメント