飲食と空間演出を融合させたダイニングバーは、独自性を活かした店舗経営を実現できる業態のひとつです。とくに、こだわりの料理や酒類を提供しながら、顧客にとって居心地のよい場を創出できる点が大きな魅力となります。
一方で、飲食業の経験がない場合には、開業に必要な資金規模、取得すべき資格や許可、開業までの具体的なプロセスなど、多くの疑問や不安が生じるのも事実です。
本記事では、開業に必要な資金の内訳、取得すべき資格や届出の流れ、開店までの手順を順を追って解説します。さらに、経営を軌道に乗せるための実践的なポイントも紹介します。
ダイニングバーの開業に必要な資金

ダイニングバーを開業するには、初期費用としておよそ1,000万円から4,000万円が必要です。金額に幅があるのは、物件の立地や広さ、さらに内装工事の規模によって大きく変わるためです。
ただし、漠然と「1,000万円ほどかかる」と考えるだけでは現実的な資金計画は立てられません。物件取得費や内装工事費、諸経費、運転資金といった主要な項目を分けて把握することが大切です。
物件取得費
物件取得費には、保証金・敷金・礼金・仲介手数料・前家賃などが含まれます。一般的には賃料の6ヵ月~12ヵ月分が相場とされ、たとえば月額30万円の物件であれば、180万~360万円程度を想定しておく必要があります。
ただし、金額の目安だけで判断することは危険です。開業後のキャッシュフローに支障をきたさないよう、売上計画との整合性を踏まえて支払可能な範囲を見極めることが重要です。
とくに月商に占める賃料の割合は10%以下に抑えることを目安とすると、安定した店舗運営につながります。
店舗デザイン・工事費
工事費用は、居抜き物件を選ぶかスケルトン物件を選ぶかで大きく変わります。居抜き物件の場合、既存の設備や内装を再利用できるため、100万~300万円程度で開業可能となるケースもあります。
一方、スケルトン物件はゼロから設備を整備する必要があり、30坪の物件であれば坪単価30万~50万円を要し、総額は900万~1,500万円に達することも珍しくありません。
居抜き物件の大きなメリットは、初期投資を大幅に抑えられる点と、開業までの工期を短縮できる点です。とくに前のテナントがダイニングバーや飲食店だった場合、厨房や給排水設備をそのまま使えるため、開業までの準備期間を2ヵ月程度にまで縮められる可能性があります。
諸経費
開業前の準備には、初期費用全体の10%ほど、目安として100万円から200万円程度を見込んでおきましょう。この費用には、資格取得や届出・許可の申請、スタッフの採用・研修、そして開業前の集客活動が含まれます。
具体的には、食品衛生責任者の講習会が約1万円、防火管理者講習は7,000円から8,000円程度です。さらに、集客活動としてチラシ制作や配布、ウェブサイト制作、SNS広告などを行う場合、50万円から100万円ほどの予算を確保しておくと安心です。
小さな出費に見えても積み重なると大きな金額になります。開業準備の段階で余裕を持って計画することが、後の経営安定につながります。
出典:一般社団法人東京都食品衛生協会「食品衛生責任者養成講習会」
出典:一般財団法人日本防火・防災協会「防火・防災管理講習」
運転資金
運転資金とは、毎月発生する固定費と変動費を賄うための資金です。内訳には、家賃、仕入費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信費、広告宣伝費などが含まれます。
月々の目安は50万円から80万円程度です。ただし、開業してすぐに売上が安定するとは限りません。そのため、少なくとも半年分、300万円から500万円程度を確保しておくと安心です。
資金の余裕があることで、開業後の不安を減らし、サービスの質向上に集中できます。
ダイニングバーの開業に必要な資格

ダイニングバーを合法的に運営するためには、いくつかの資格や許可、そして届出が欠かせません。これらは安全や衛生を守るために定められたルールであり、違反すれば営業ができないだけでなく、罰則の対象になることもあります。
また、どの手続きも申請から交付までに時間がかかるのが一般的です。開業予定日から逆算し、早めに準備を進めることがポイントとなります。
食品衛生法に基づく営業許可
飲食店を開業するには、まず「食品衛生法に基づく営業許可」が必須です。申請の要件は、食品衛生責任者の設置と、法令で定められた設備基準の遵守です。
食品衛生責任者は、調理師や栄養士、製菓衛生師といった資格保持者であれば兼任できます。資格を持っていない場合でも、食品衛生責任者講習会を受講すれば取得可能です。講習は約6時間で、修了試験に合格すれば資格が与えられます。
【申請手続き】
- 提出先:管轄の保健所
- 提出期限:店舗工事の完了予定日の10日前まで
- 許可証交付:通常2〜3週間程度
- 有効期限:5年間(更新が必要)
営業許可は飲食店経営の出発点となる手続きです。申請の遅れや不備は開業スケジュール全体に影響するため、早めに準備を進めることが重要です。
深夜酒類提供飲食店営業の届出
深夜0時から日の出前までに酒類を提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要です。これを提出しなければ深夜営業はできません。
【届出のポイント】
- 対象時間:深夜0時~日の出前に酒類を提供する店舗
- 提出期限:営業開始の10日前まで
- 提出先:営業予定地を管轄する警察署・生活安全課
- 営業制限:用途地域によっては営業不可の区域あり(物件選び段階で要確認)
必要書類には、深夜酒類提供飲食店営業開始届出書、営業方法を記した書類、店舗の平面図、住民票(本籍記載)、身分証明書などが含まれます。
さらに、深夜営業では近隣住民への騒音やトラブル防止に配慮することが不可欠です。防犯体制や騒音対策を整えておくことが、許可取得後の安定した営業につながります。
出典:警視庁「性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業の届出」
防火管理者選任届
収容人数が30人以上の店舗では、防火管理者を選任し、消防署へ届け出ることが義務付けられています。資格区分は店舗規模によって異なり、延床面積300㎡以上は「甲種」、300㎡未満は「乙種」の防火管理者が必要です。
【資格区分と講習】
- 甲種:延床面積300㎡以上の店舗に必要。講習は2日間(10時間)、受講料約8,000円
- 乙種:延床面積300㎡未満の店舗に必要。講習は1日間(5時間)、受講料約7,000円
【届出手続き】
- 提出先:管轄消防署
- 提出期限:営業開始日の7日前まで
- 追加書類:店舗規模や設備によっては「防火対象物使用開始届出書」の提出が必要
火災を未然に防ぐための体制を整えることは、法令上の義務であると同時に、安心して営業を続けるための基本でもあります。
ダイニングバーを開業する際の流れ

ダイニングバーを開業するには、いくつもの準備を同時並行で進める必要があります。どの作業をいつ行うかを整理し、開業予定日から逆算してスケジュールを組むことが大切です。
1.コンセプトを決める
ダイニングバー開業の出発点は「コンセプト」を定めることです。お店の方向性を決める最初のステップであり、後の準備すべての軸となります。コンセプト次第で、提供するメニューや店舗の雰囲気、ターゲット客層、そして価格帯までが決まります。
効果的なコンセプトを設計するには、まず「自分はどんな価値を提供したいのか」を明確にすることが欠かせません。
そのうえで競合店の分析を行いましょう。開業予定地周辺の類似店舗を実際に訪れ、客層やサービス内容を観察すると、自店の差別化ポイントが見えてきます。
2.事業計画書を作成する
コンセプトを形にし、開業の実現性を確かめるためには事業計画書が欠かせません。この書類は、金融機関からの融資や助成金の申請時に必ず提出が求められる重要なものです。そのため、専門家だけでなく第三者が読んでも理解しやすい内容に仕上げる必要があります。
事業計画書には、営業計画、仕入計画、売上計画、資金計画といった基本項目を盛り込みます。あわせて、近隣の競合店の状況や自店の強みを分析することで、より説得力のある計画に仕上げます。
3.店舗物件を探す
ダイニングバーを成功させるには、コンセプトとターゲット客層に合った立地を選ぶことが欠かせません。立地選びでは、交通アクセスのよさ、人通りの多さ、周辺の競合状況、そして賃料と売上予測のバランスを意識することが重要です。
また、物件の種類によっても初期費用や開業スピードは大きく変わります。代表的なのが「居抜き物件」と「スケルトン物件」です。
とくに未経験からの開業では、リスクを抑えられる居抜き物件の活用がおすすめです。初期投資の削減と工期の短縮という2つのメリットは、安定したスタートを切るうえで大きな支えになります。
4.開業資金を調達する
開業に必要なおおよその資金を把握したら、自己資金だけで足りない分をどう補うかを考えましょう。主な方法として、日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」、各種補助金や助成金、そしてクラウドファンディングがあります。
- 日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」
創業間もない事業者でも利用しやすく、比較的低金利で融資を受けられる制度。 - 補助金・助成金
返済不要という大きなメリットがある一方、募集時期や対象条件が限定され、採択可否は審査に左右される。 - クラウドファンディング
資金調達と同時に宣伝効果も期待できるが、魅力的な企画設計や発信力が不可欠。
いずれの方法を選択するにしても、事業計画書の作成は不可欠です。金融機関や審査機関は計画書を通じて事業の実現可能性を判断します。資金調達の成否は、計画書の完成度に大きく依存すると認識しておきましょう。
5.資格・免許を取得する
資格や許可の取得は、開店直前にまとめて済ませられるものではありません。書類の取り寄せや審査に時間がかかるため、開店予定日から逆算して早めに準備を進めることが大切です。
具体的には、食品衛生責任者の資格取得、防火管理者の選任、食品衛生法に基づく営業許可、そして深夜酒類提供飲食店営業の届出などがあります。これらを計画的に進めておくことで、開店直前に慌てることなくスムーズに営業を始められます。
6.設備や什器を決める
店舗の設備や什器は、コンセプトを具現化する重要な要素であると同時に、日々の営業効率や安全性に直結するため、慎重かつ計画的に選定する必要があります。
とくに厨房設備については、食品衛生法で定められた基準を満たすことが求められます。開業前には保健所による立ち入り検査も実施されるため、早い段階から基準を踏まえた準備を進めておくことが不可欠です。
また、グラスや食器類は使用頻度が高く、破損や洗浄待ちを考慮する必要があります。一般的には客席数の2倍から3倍程度を目安に用意することで、繁忙時にも安定したサービス提供が可能になります。
十分な備品を確保しておくことは、顧客満足度の向上と安定的な店舗運営に直結します。
7.仕入れ先を決める
お酒や食材の仕入れ先は、サービスの品質や価格、そして安定した供給を左右する大切な要素です。選定の際には、商品の品質、料金、納品の速さや正確さ、取引条件といった点をしっかり確認することが重要です。
仕入れ先には、地元の業務用酒販店、ディスカウントショップ、通販・オンラインサービスなど多様な選択肢があります。
- 酒販店:専門性が高く、安定供給に強みがある。
- ディスカウントショップ:コストを抑えやすく、仕入れ単価を下げやすい。
- 通販・オンライン:利便性が高く、希少性のある商品を導入しやすい。
複数の仕入れルートを確保し、需要変動や供給リスクに応じて柔軟に使い分けることが、安定した店舗運営と収益性の確保につながります。
8.集客活動を始める
開業準備と並行して、できるだけ早い段階から集客活動を始めましょう。とくに未経験での新規開業では知名度がゼロからのスタートになるため、オープン前からのアピールが欠かせません。
代表的な方法には、Googleビジネスプロフィールの登録、SNSでの情報発信、Webサイト制作、ポスティングチラシの配布などがあります。
- Googleビジネスプロフィール:検索結果に表示されやすく、地元のお客様に見つけてもらいやすい
- SNS:開業準備の様子を発信することで、共感や期待感を育てられる
- Webサイト:信頼性を高められる
- チラシ:インターネットに疎い高齢者などにもアプローチできる
複数の手段を組み合わせ、早い段階からお店の存在を知ってもらうことが、開業初日からの集客につながります。
ダイニングバー開業では、接客を担う人材の質も重要です。
経験豊富なスタッフ採用には、業界特化の転職サービス【バリプラNext】を活用しましょう。
ダイニングバーの開業を成功させるためのポイント
飲食業界は競争が激しく、単に開業するだけでは継続的な経営は困難です。店舗を軌道に乗せ、常連客に支持されるダイニングバーへと成長させるためには、計画性と持続的な改善が不可欠となります。
その鍵となるのが、戦略的な取り組みと日々のオペレーション改善です。以下では、開業後に特に留意すべきポイントを具体的に解説します。
独自性のあるコンセプトにする
競合のなかで選ばれるには、独自性のあるコンセプトが必要です。コンセプトは単なる雰囲気づくりではなく、他店との差別化を生み出す最大の武器となります。
たとえば、地元の食材を活用したオリジナルメニューや、特定のテーマ性を持たせた空間づくり、ライブイベントの開催、独自の内装デザインなどがあります。こうした要素が、お客様の記憶に残る体験を生み出します。
コンセプトに合った立地を選ぶ
店舗のコンセプトと立地が合致していなければ、想定した顧客を十分に獲得することは困難です。ターゲットとする客層の生活動線やライフスタイルを踏まえた立地選定は、売上確保に直結する最重要要素といえます。
立地判断に迷う場合は、「居抜きの神様」を活用するのも有効な手段です。豊富な実績と専門知識を持つプロの視点から、コンセプトに適した物件を提案してもらうことで、立地選定の精度を高め、開業リスクを軽減できます。
初めての人でも入れる雰囲気づくりをする
バー業態は一般的に「敷居が高い」という印象を持たれやすく、新規顧客の来店を妨げる要因となり得ます。そのため、初めて来店する顧客が抵抗感なく入店できる雰囲気を意図的に設計することが重要です。
具体的な工夫としては、コンセプトに沿ったBGMの選定、明るく視認性の高い外観、看板での「おひとり様歓迎」といった明確なメッセージ表示が有効です。また、店内の視認性を高めることで、入店前の心理的ハードルを下げ、気軽に立ち寄れる空間を演出できます。
リピーターを増やす
安定した売上をつくるには、リピーターの存在が欠かせません。常連客は口コミで新規顧客を呼び込む効果もあります。
基本は、質の高いお酒や料理、丁寧な接客です。そのうえで、定期イベントやメンバーシップ制度、割引券、SNS発信などを取り入れると効果的です。特別感を与える工夫が、顧客を再び呼び込む力になるでしょう。
他店との差別化を図る
競合が多いなかで選ばれるには、多角的な差別化が必要です。コンセプトだけでなく、オリジナルメニューやカクテルの開発、内装デザイン、ライブイベントや貸切対応といったサービス面での工夫も効果的です。
さらに、ターゲット顧客を絞り込み、自店ならではの体験を提供することが成功につながります。
コスト管理を徹底する
収益性を高めるには、徹底したコスト管理が欠かせません。仕入コストや賃料、人件費、水道光熱費といったランニングコストを常に把握することが大切です。
あわせて、売上分析や予算管理、在庫管理を定期的に行い、原価率を抑える工夫を続けましょう。無駄を減らす習慣が、安定した経営を支えます。
こちらの記事では、バーの開業について解説しています。
必要な届出や資金も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
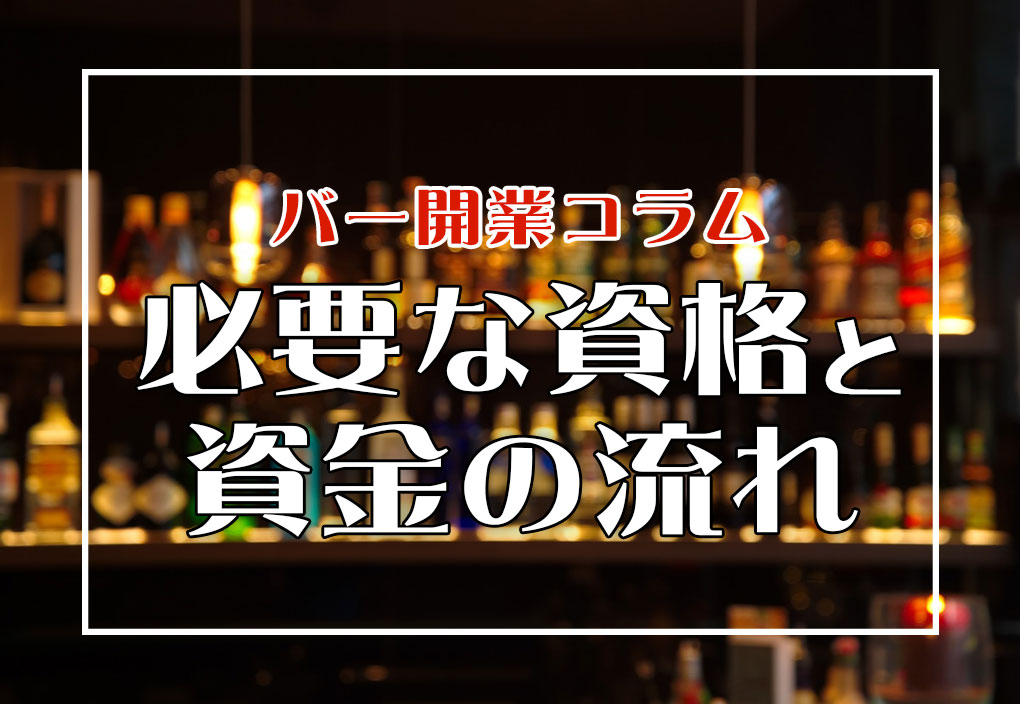
まとめ
ダイニングバーの開業は、正しい知識と計画的な準備を行えば、未経験者であっても実現可能です。必要となる資金は概ね1,000万~4,000万円程度ですが、居抜き物件を活用すれば初期投資を大幅に削減でき、開業リスクを抑えることが可能です。
成功の要点は、独自性のあるコンセプト設計、立地の適切な選定、各種許可・資格の確実な取得、そして開業後の継続的な改善にあります。特に、リピーター獲得とコスト管理は、安定した経営基盤を築く上で不可欠な要素です。
開業を検討される方には、居抜き物件の活用を推奨します。初期投資の削減や工期短縮により、未経験者でも挑戦しやすい環境を整えられます。
「居抜きの神様」では、バー経営に適した居抜き物件を豊富に取り揃えており、一般には公開されていない非公開物件も多数取り扱っています。「投資リスクを抑えて挑戦したい」「開業までの時間を短縮したい」とお考えの方は、ぜひ一度「居抜きの神様」をご覧ください。













コメント