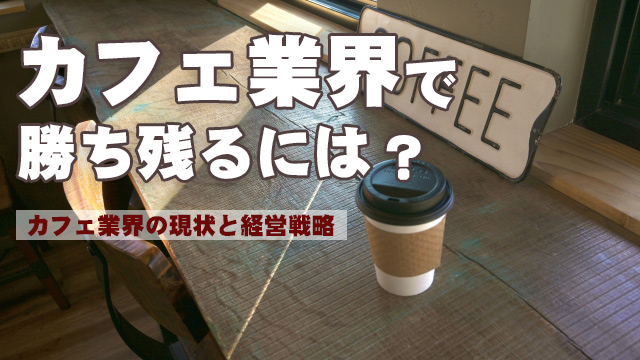-

カフェの開業準備リスト!開業までのスケジュールを紹介
カフェの開業を目指しているものの、何から始めればいいのか分からず、不安を感じている方は多いのではないでしょうか。カフェの開業準備は、コンセプトの設計をはじめ、事業計画立案、資金調達、物件探し、内装工事、備品購入、各種届出申請、スタッフ募... -

成功のカギはココにあり!カフェ業界で勝ち残るための戦略を解説
近年、カフェ業界は新型コロナウイルスの影響から徐々に回復し、再び活気を取り戻しつつあります。しかし、カフェ市場の競争はかつてないほど激化しており、今後も生き残るためには明確なコンセプトや戦略、そして課題への対応力が求められます。 本記事で... -

失敗しない!カフェ開業前に知っておくべきコンセプト設計の基礎知識
コンビニなどで安くておいしいコーヒーが手軽に買えるようになった昨今、前にも増して競争が激化しているカフェ業界。そんななかでカフェを成功させるためには、商品力だけでなく、明確なコンセプト戦略が欠かせません。 コンセプトが定まっていないと、他... -

カフェのキッチンの内装レイアウトを決める際のポイントを解説
カフェはお客様がくつろぎ、快適に過ごせるレイアウトが求められます。客席にあわせて、キッチンの内装レイアウトも重要です。動線が整備されていない、客席が広すぎてキッチンが狭く、動きにくいなどの場合にはお客様に快適なサービスを提供できません。 ... -

カフェ開業前に確認!方法や取得しておきたい資格|一問一答Q&A付き
カフェの開業を考えているものの、何から手をつけたらよいか悩んでいる方は多いでしょう。スムーズにカフェ経営を進めるには、開業前の段階で疑問を解決する必要があります。 本記事では、開業方法の種類や必要な資格・手続き、内装・資金の考え方まで、押... -

井荻駅│都市の便利さと下町らしい温かみが共存する、住み心地の良い街
杉並区の居抜き物件紹介 西武新宿線の居抜き物件紹介 井荻駅の居抜き物件紹介 井荻駅は東京都杉並区に位置する西武新宿線の駅です。駅周辺には住宅街が広がり、公園が点在するなど落ち着いた環境が整い、住み心地は抜群。ファミリー層から高齢者まで、幅広... -

【これなら間違いない!】ワイン好き500人が選ぶ「絶対欲しい最強おつまみTOP10」
産地や種類によって豊かな個性を持つワインは、その魅力をより一層引き立ててくれる「おつまみ」との相性が重要です。ワインに合う一品をメニューに取り入れるだけで、訪れたお客様の特別なひとときを印象深いものに演出できるはずです。 今回はNEXERと共... -

ひばりが丘の多国籍料理店の居抜き物件|都心へのアクセス抜群なベッドタウンの周辺情報
西東京市 西武池袋線 ひばりヶ丘駅 東久留米駅 中華・エスニック・多国籍料理 【西東京市 ひばりが丘駅|1階路面店・角地にある多国籍料理居抜き物件】 所在地東京都西東京市ひばりケ丘北3丁目最寄り駅西武池袋線 ひばりヶ丘駅 徒歩3分西武池袋線 東久留米... -

金町駅│再開発により利便性が高まる、自然豊かな下町
葛飾区の居抜き物件紹介 JR常盤線各駅停車の居抜き物件紹介 金町駅の居抜き物件紹介 葛飾区に位置する金町駅は、都心へのアクセスの良さと下町の風情を兼ね備えたエリアです。昔ながらの商店街のレトロな雰囲気が楽しめる一方で、再開発によりタワーマン... -

京成金町駅の中華料理店居抜き物件|生活利便性の高い住宅街の周辺情報
葛飾区 京成金町線 JR常盤線各駅停車 京成金町駅 金町駅 中華・エスニック・多国籍料理 【葛飾区 京成金町駅|角地1階路面店 中華料理店居抜き物件】 所在地東京都葛飾区金町5丁目最寄り駅京成金町線 京成金町駅 徒歩3分JR常磐線各駅停車 金町駅 徒歩3分階...