飲食店経営が厳しい6つの理由と成功の秘訣!気になる年収事情も解説

飲食業界は競争が激しく、経営が厳しいといわれています。飲食店を始めたものの、赤字続きで閉店を考える経営者も少なくありません。この記事では、飲食店経営が厳しい6つの理由と成功するための秘訣を解説します。さらに気になる経営者の年収事情や必要な資格も紹介しますので、飲食店の経営を考える際の参考にしてください。
飲食店の経営は厳しい?
飲食業界は開業のハードルが低く、毎年何万もの新規開業者が参入している反面、廃業率も高い業種です。中小企業庁の「小規模企業白書」によると、「宿泊業・飲食サービス業」は開業率6.9%、廃業率5.0%と、すべての業種の中で最も高くなっています。
一般に、飲食店は開業から1年以内に約30%、5年では約80%、10年で90%以上が廃業するといわれています。飲食業界は競争が激しく、その厳しさは他の業種と比べても際立っています。

飲食店経営が「厳しい」6つの理由
飲食店の廃業率の高さがわかったところで、飲食店の経営が厳しいといわれる理由をみていきましょう。主な理由には、以下の6つが考えられます。
- 初期費用や運用コストがかかる
- 競合が多い
- 利益が安定しない
- 労働時間が長くなりやすい
- 人材が不足している
初期費用や運用コストがかかる
飲食店を開業するには多くの初期費用が必要です。店舗物件にかかる費用のみならず、必要に応じて内装工事や設備、厨房機器の購入など。さらに開業しても、家賃、人件費、光熱費、食材費といった運用コストが毎月発生します。特に人件費と食材費は売上の変動に影響を受けやすいため、常に変動費として意識し適切な管理が欠かせません。
開店直後は、初期費用を回収と毎月の運営コストの支払いが重なり、経営が軌道に乗るまでには時間がかかるのが一般的です。開店当初から順調に利益が得られれば良いですが、思うように売り上げが伸びない可能性もあります。初期費用を抑える工夫や、綿密な資金計画を立てることが安定した経営につながります。
競合が多い
飲食店経営が厳しい理由のひとつに競合の多さが挙げられます。
「食品衛生責任者」の資格さえあれば誰でも開業できるため、参入のハードルが低く、新規店舗が次々と誕生しています。また大手チェーン店やフランチャイズとの競争も激しく、個人経営の店舗はブランド力や資本力で劣り、集客に苦戦しやすいのが現実です。
競争が激しい市場で生き残るためには、独自の強みやリピーターを増やす工夫が欠かせません。独自の料理やコンセプトで他店にはない魅力を打ち出せなければ、長期的な経営は難しいでしょう。
売上が安定しない
売上が安定しないことも、飲食店経営が厳しい理由です。飲食店では人件費や原材料費の割合が大きく、利益率は約10%程度と他業種に比べて低い傾向があります。さらに、環境の変化が売上に直結しやすいのも課題です。
例えば、悪天候が続くと客足が減り、1日の売上に大きな影響を与えます。また感染症の流行時には、多くの飲食店が営業自粛を余儀なくされ、大きな打撃を受けました。このように売上の予測が難しく、安定性に欠けることが飲食店経営を困難にします。
労働時間が長くなりやすい
飲食店では、一般に昼営業、夜営業、仕込みと労働時間が長くなりがちです。経営者は店舗の運営だけではなく、さらに経営戦略の策定、人材教育や管理、経理など多岐にわたる業務をこなす必要があります。
常に集客や利益率を意識し、どうすれば良いのかを考え続ければなりません。そのため、経営者には十分な休息時間を確保しにくいのが現状です。長時間労働が続くと、判断力の低下や体調不良を招き、経営に悪影響を及ぼす可能性も。
できるだけ早い段階で、休息を確保できる環境を整えることが、飲食店経営を長く続けるための重要なポイントです。
人材が不足している
飲食業界は、休日が少なく長時間労働になりやすい上に、給与水準が低いというイメージが根強く、人材確保が厳しい業界とされています。さらに、研修期間が短く、従業員の離職率が高いことから、慢性的な人手不足に悩む店舗も少なくありません。
飲食店では人件費を大幅に上げるのが難しいといわれますが、給与が高くても労働環境が悪ければ、離職率は下がりません。人材育成に力を入れ、働きやすい環境を整えることが従業員の定着につながる重要なポイントです。

飲食店経営者の年収
飲食店経営者の年収は、個人経営か法人か、また店舗の規模によっても異なりますが、一般的には400万円から600万円程度といわれています。個人差が大きく、年収が得られないままで廃業する経営者もいれば、年収1,000万円以上の経営者もいます。小規模な個人経営でも、所得300万円程度はないと継続するのは厳しいでしょう。
国税庁調査によると、飲食店に勤務している人の平均年収は264万円。他業種と比べて最も低くなっています。全体の平均年収460万円を考慮しても、飲食店に勤務しているよりも経営者になった方が年収の上がるチャンスがあります。
出典:国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査 -調査結果報告-」
飲食店の経営に必要な資格
飲食店の経営では食品衛生法や消防法といった法令を守ることが求められ、食品衛生責任者や防火管理者の設置が必要です。それぞれのポイントを説明します。
食品衛生責任者
食品衛生責任者とは、その施設の衛生管理の全般について責任を持つ者です。食品衛生法に基づいて定められた国家資格であり、飲食店の経営では各事業所に1名以上の食品衛生責任者の設置が義務付けられています。開業時に、担当の保健所へ食品衛生責任者の名前を書いた書類の提出が必要です。
食品衛生責任者の資格がない場合は、各自治体で開催される食品衛生責任者養成講習会を受けてください。講習項目は「衛生法規」「公衆衛生学」「食品衛生学」を中心に約6時間、1日で取得可能です。インターネットで受講可能な「eラーニング方式」を採用している自治体なら、自宅で講習を受けることもできます。
なお、調理師や栄養士、製菓衛生師の資格をお持ちの方は、食品衛生責任者の資格要件を満たしているので講習会の受講は不要です。
防火管理者
防火管理者とは建物の防火管理を担う責任者のことです。飲食店などの多くの人が利用する建物では、火災による被害を防ぐための消防計画を作成し、防火管理に必要な業務(防火管理業務)を計画的に実施する役割を担います。
消防法により、飲食店では収容人数30人以上の場合に防火管理者の設置が義務付けられており、資格の習得には「防火管理講習」の受講が必要です。防火管理者には2種類あり、店舗の延床面積が300㎡以上の場合は「甲種防火管理者」、300㎡未満の場合は「乙種防火管理者」を取得が求められます。
以下に、飲食店における防火管理者の基準などをまとめました。ただし、自治体により取得にかかる費用や基準が異なる場合があります。事前に地域の担当部署へ確認してください。
| 取得に必要な日数(時間) | 費用の目安 | 基準 | |
|---|---|---|---|
| 取得しなくて良い | 不要 | 不要 | 店舗の収容人数が30人未満(スタッフも含む) |
| 甲種防火管理者 | 2日(約10時間) | 8,000円 | 店舗の延床面積300㎡以上 |
| 乙種防火管理者 | 1日(約5時間) | 7,000円 | 収容人数が30人以上でお店の延床面積300㎡未満 |
飲食店の経営を成功させる秘訣
閉店する飲食店がある一方で、長く勝ち残っている店舗もあります。飲食店の経営を成功させるポイントは、コンセプトの明確にし、集客に力を入れること、お金の動きの理解や従業員のモチベーションを向上させることです。さらに改善しつづけることも欠かせません。
コンセプトを明確にする
飲食店の経営を長く続けるためには、コンセプトの設定が不可欠です。コンセプトとは、お店の方向性やテーマを示すもので、お店の個性であり、事業の根幹になります。コンセプトを明確にすることは、ターゲットの絞り込みや集客にもつながります。
コンセプトがあいまいだと、顧客に「どのようなシチュエーションで利用できる店なのか」が伝わりません。選ばれにくくなり、集客が難しくなります。一方、コンセプトがはっきりしていれば、店の外装・内装・メニューや接客方法に一貫性が生まれ、店の魅力が伝わりやすくなります。顧客満足度を高め、リピーターの獲得につながるでしょう。
競合店との差別化を図るためには、ざっくりとした方向性を決めるだけではなく、この店ならではの大きな強みを出すことが重要です。コンセプトを明確にすることは、長期的に繁盛する飲食店になるための第一歩です。
集客に力を入れる
飲食店の経営を成功させるには、集客に力を入れることが不可欠です。競争の激しい飲食業界。料理がおいしいだけでは生き残れません。新規顧客の獲得とリピーターの確保を両立し、安定した集客を目指すことが重要です。
- オンライン集客:ホームページ、SNS、グルメサイトを活用し、店舗の情報を発信して認知度を高め、新規顧客を獲得する
- オフライン集客:チラシ配布、店頭のディスプレイや地域イベントへの参加など、地域の人々にアプローチする
- リピーターの確保:ポイントカードや会員制システムを導入、再来店のきっかけをつくる
- 口コミ戦略:顧客満足度を高め、自然な口コミで店の評判を広げてもらう
飲食店の集客は自店に合った方法を見つけ、継続的に実施することが成功の秘訣です。
お金の流れを理解する
どの業種でも経営において、お金の流れを理解することが重要です。どんなに良いサービスやメニューを提供しても、収支バランスが悪ければ利益を上げられません。以下にお金の流れを把握するためのポイントをまとめます。
- 開業前の資金計画:自己資金や借入額、初期投資の回収期間を明確にし、安定したスタートを切る準備をする
- 日々の売上とコストの管理:売上・原材料費・人件費・光熱費などを常に把握し、経営状態をリアルタイムで知る
- FLコストの理解:食材費(Food cost)と人件費(Labor cost)を合わせたFLコストを把握し、適切なバランスを維持する
- 損益分岐点の把握:損益分岐点を理解することで売上目標を設定しやすくなり、より具体的な経営戦略を立てられる
お金の流れを理解することで、目標の売上高を設定し、コストの適切な管理が可能になります。
従業員のモチベーションを向上させる
飲食店の経営において、従業員のモチベーションは非常に重要です。動線を最適化するなど働きやすい環境を整え、マニュアルの整備やトレーニングを適切に実施し、適切な報酬を提供することで従業員のモチベーションを向上できます。
従業員に「長く働きたい」と思ってもらえる環境を作ることでサービスの質を維持しやすくなります。その結果、お客様満足度の向上、リピーターの獲得につながります。
継続的に改善する
勝ち残る飲食店は現状に満足せず、常に改善を重ねています。例えば、アンケートや口コミサイトを活用して顧客の要望を把握し、サービスやメニューに反映させる、季節ごとにメニューを更新するなど。顧客の声を大切にし、柔軟に対応する姿勢が大切です。
継続的な改善により、お客様の満足度を高め、競争の激しい飲食業界で生き残り続けられるでしょう。
飲食店の経営に関するよくある質問
最後に飲食店経営に関してよくある質問をまとめました。
飲食店の経営に向いている人の特徴は?
飲食店経営には料理の知識や人を喜ばせるサービス精神だけではなく、さまざまなスキルを兼ね備えたバランス感覚が求められます。飲食店は、料理のおいしさだけでは成功しません。市場調査や競合分析、資金計画、集客戦略といった計画性と経営能力が求められます。さらに、迅速な判断力と行動力で変化に対応する柔軟性も重要です。
また、お客様やスタッフ、取引先など多くの人と関わる仕事なので、円滑にコミュニケーションを取れることが重要です。お客様との会話を楽しみ、リピーターを増やせる人は成功しやすいでしょう。同時に、スタッフの教育やモチベーション管理も経営には欠かせません。従業員のスキル向上や定着率の向上が、サービスの質や売上アップにつながります。
飲食店の経営を続けるか閉店するかの判断基準は?
飲食店の閉店・撤退を判断するポイントは、売上・資金繰り・市場環境・経営者のモチベーションの4つです。
- 赤字が続く:3ヵ月以上赤字が続き、固定費の支払いが困難になった場合は要注意。回復が見込めなければ撤退を検討すべきです。また、前年同月比20%以上の売上減少が続くのも要注意です。
- 資金繰りの悪化:家賃や仕入れ費の支払いが遅れる、給与の遅配が発生するなど、キャッシュフローが回らなくなったら危険信号です。
- 市場環境の変化:人通りの減少や競合店の影響でターゲット顧客が減り、立地変更も厳しい場合は撤退も検討しましょう。
- 経営者やスタッフの疲弊:長時間労働や人手不足でモチベーションが低下し、サービスの質が落ちると経営継続は困難です。
飲食店の移転や閉店は「買取の神様」にお任せください
飲食店の経営は、決して簡単なものではありません。ですが、正しい知識と適切な戦略を持って取り組めば、成功の可能性は十分にあります。この記事で解説した、飲食店の経営が「厳しい」といわれる理由や成功の秘訣を参考に、ぜひあなたの飲食店経営を成功に導いてください。
「買取の神様」では飲食店の移転や閉店に関する相談を承っています。居抜き売却でしたら、造作や備品をそのまま売却できるため、閉店に伴う原状回復工事の削減ができ、造作譲渡金を得られるケースもあります。相談・査定は無料ですので、いつでもお気軽にお問い合わせください。


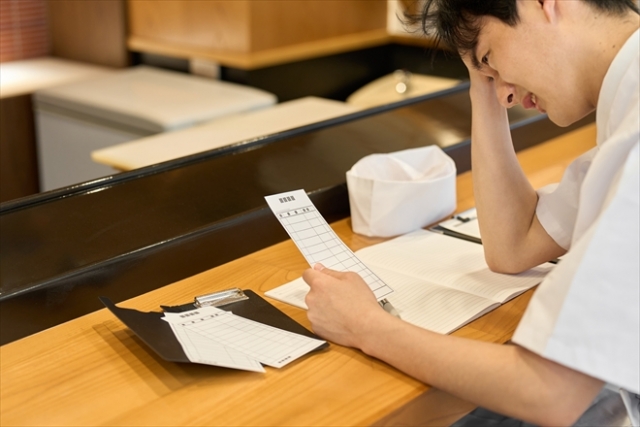





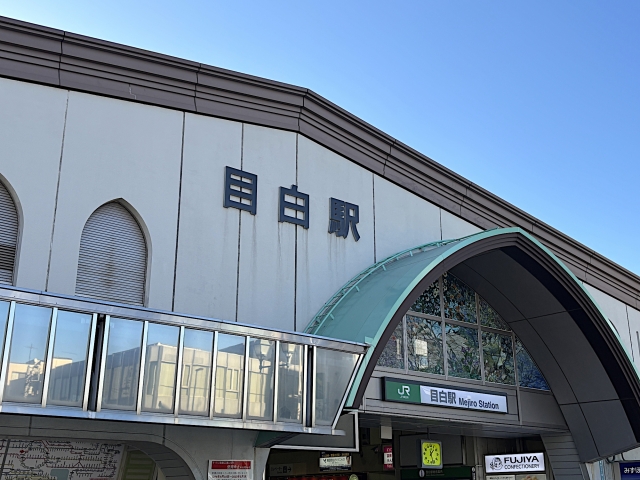




コメント