飲食店のオーナーチェンジ完全ガイド|流れ・手続き・注意点を徹底解説

飲食店の経営がうまくいかず、閉店を考えているなら、オーナーチェンジという選択肢があります。オーナーチェンジを行えば、高額な閉店コストを抑えつつ、店舗を他の人に引き継ぐことが可能です。この記事では、飲食店のオーナーチェンジの流れをステップごとに解説し、必要な手続きや書類、さらには見落としがちな注意点まで紹介します。オーナーチェンジを検討する際の参考にしてください。
飲食店のオーナーチェンジとは
飲食店のオーナーチェンジとは、飲食店を閉店せずに、現在経営しているオーナーが経営権や店舗を他の人(新オーナー)に引き継ぐことです。多くの場合、設備や内装をそのまま利用できる居抜き形式で行われ、閉店時に必要な原状回復費用(スケルトン工事など)を使わずに譲渡できるのが特徴です。
飲食店のオーナーチェンジのメリット
飲食店のオーナーチェンジには、閉店の際のコストを抑えられる、事業の後継者が見つかり、従業員の雇用を守れるといったメリットがあります。それぞれのポイントを説明します。
閉店コストを大幅に削減できる
オーナーチェンジなら、原状回復工事や設備処分の必要がないため、閉店時のコストを抑えられます。さらに造作譲渡料として収入を得られる可能性もあります。
後継者不足を解消できる
後継者不足に悩んでいる飲食店の場合、オーナーチェンジよって廃業を防げます。新たなオーナーに引き継ぐことで、店の歴史や地域でのブランドを残せる。
従業員の雇用を守れる
事業譲渡の際に従業員を新オーナーに引き継ぐことで、スタッフの雇用を継続できます。突然の閉店で職を失うリスクを防ぎ、従業員の生活を守る選択でもあります。
飲食店オーナーチェンジの流れ
飲食店のオーナーチェンジを行う場合、居抜き物件として造作譲渡を選択するのが一般的です。続いては、造作譲渡でオーナーチェンジする場合の流れを説明します。
1. 契約書を確認する
店舗が賃貸物件の場合、店舗の譲渡や売却が可能なのかを賃貸借契約書で確認します。特に、契約書に記載されている解約予告期間や原状回復義務に関する項目が重要です。契約によっては、居抜き物件として譲渡できないケースもありますが、物件所有者(貸主)との交渉で可能になることも。
物件の賃貸契約書だけでなく、リース品やレンタル品に関する契約書も必ず確認しましょう。契約期間が残っている場合は、契約内容によって残りの支払いや違約金が発生するケースがあります。事前にしっかりチェックして、思わぬ出費を防ぐことが大切です。
2. 業者や専門家へ査定を依頼する
不動産会社や買取業者など専門家へ査定を依頼し、店舗の適切な価値を評価してもらいましょう。貸主への交渉が必要な際や手続きが煩雑で負担が大きい場合などは、専門家に相談すると安心です。
3. 売却価格を設定する
専門家の査定結果をもとに売却価格を決定します。買取希望者が納得できる現実的な価格設定がポイント。見積りと合わせて設備リストや修繕履歴などを提示すると交渉がスムーズです。
4. 物件所有者(貸主)の承諾を得る
賃貸物件では、貸主から造作譲渡の承諾を得ることが必要です。居抜き売却では賃貸借契約の引き継ぎが伴います。借主の承諾を得ずに取引を進めると、後々トラブルになる危険性があります。必ず事前に貸主に相談しましょう。貸主との交渉に自信がないのであれば、専門業者にアドバイスを仰ぐことも1つの方法です。
5. 不動産会社と媒介契約を結び、買取希望者を募集する
不動産会社と契約を結んで買取希望者を募集します。買主を募集する際、賃貸借契約書の写しや店舗平面図といった資料の提出を求められることがありますので、事前に準備しておきましょう。
6. 造作譲渡契約を締結する
買取希望者の中から譲渡先が決定したら、造作譲渡契約(売買契約)を結びます。造作譲渡契約書の作成には専門的な知識が必要なので、専門性の高い業者にサポートしてもらうと安心です。
7. 物件所有者(貸主)との賃貸契約を解除する
造作譲渡契約を締結したら、売主(現オーナー)が貸主との間に結んでいる賃貸借契約を解約し、貸主と新オーナーとの契約締結を調整します。解約予告期間をうまく調整できれば、家賃の支払いが無駄にならないことも。
8. 店舗引き渡しと代金受領
賃貸借契約が締結できたら、契約内容に従って店舗を引き渡します。仲介業者を介する場合、業者が一時的に代金を預かることが一般的です。引き渡しが問題なく完了したことを確認後、代金が仲介業者から振り込まれます。代金の振り込みを確認してオーナーチェンジが完了です。
飲食店のオーナーチェンジに必要な手続きと書類
飲食店のオーナーチェンジの流れがわかったところで、手続きや必要な書類をみていきましょう。手続きを把握しておくことで、スムーズな引き継ぎを実現できます。
譲渡契約書
店舗の引き継ぎ条件(価格、設備、引き渡し日など)を記載した契約書を作成します。売主(現オーナー)と買主(新オーナー)が署名し、合意を証明しましょう。
造作譲渡契約書に記載する一般的な項目は以下のとおりです。
- 物件所有者および貸主の承諾獲得
- 譲渡する造作物リスト
- 造作譲渡料
- 支払い期日
- 引き渡し期日
- 支払い方法
- 支払い遅延の場合の処置
- 造作物に関する契約不適合責任
- 原状回復義務の所在
- 契約解除の条件
ほかにも必要な項目があれば、適宜、契約書に記載してください。
賃貸借契約書
店舗の賃貸契約内容を確認するための書類です。貸主の承諾や契約引き継ぎの条件をチェックする際に必要です。
営業許可書と保健所への届出
所轄の保健所へ「廃業届」を提出し、「飲食店営業許可書」を返納しましょう。提出期限は地域ごとに異なりますが、一般的には廃業日から10日以内とされています。書類の様式も保健所によって違いがあるため、所轄の保健所で確認してください。必要書類は保健所や自治体の公式サイトからダウンロード可能です。地域によっては電子申請にも対応しています。書類作成の際には「食品営業許可証」に記載された営業許可番号が必要ですので、手元に準備しておきましょう。
売主が返却した後、買主は新たに「飲食店営業許可書」を取得します。「食品営業許可証」の有無や店舗の設備変更があった際は、再度の保健所による検査が求められる場合もあります。
税務署への届出
オーナーチェンジにて、売主が事業を廃業した場合、税務署に以下の届け出が必要です。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 給与支払い事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書
- (消費税の)事業廃止届出書
「個人事業の開業・廃業等届出書」は所轄の税務署へ廃業日から1ヵ月以内を目安に提出しましょう。廃業の届け出は都道府県税事務所にも必要です。書類の名称や提出期限は異なる場合がありますので、所轄の税事務所に問い合わせてください。
「給与支払い事務所等の開設・移転・廃止届出書」は、従業員を雇用していたり、青色専従者の家族がいたりした場合に提出します。営業廃止日から1ヵ月以内が目安です。
青色申告で所得税の確定申告をしていた場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出します。提出期限は青色申告をとりやめた翌年の3月15日までです。消費税の課税事業者の場合は、廃業してすぐに「事業廃止届出書」の提出します。
防火管理者選任(解任)届出書
消防署に「防火管理者選任届出書」を提出します。飲食店店舗が30人以上収容可能な場合、開業時に防火管理者の選任届を提出しているので、オーナーチェンジにあわせて解任届を提出します。防火管理者の解任日は、廃業日(または譲渡日)を記入してください。届け出の書類は所轄の消防署でもらうか、行政のサイトからもダウンロード可能です。提出に期限はありませんが、可能な限り早めに提出しましょう。
解任届提出後、買主は新たに「防火管理者選任届出書」を申請します。
飲食店のオーナーチェンジでの注意点
オーナーチェンジを行う際にトラブルを防ぐためには、曖昧な約束を避け、契約書で条件を明確にするのが大切です。注意したい5つのポイントを解説します。
店舗の状態を正確に伝える
オーナーチェンジする場合は、必ず店舗の正確な情報を伝えます。特に空調や水まわりはトラブルが発生しやすいので、事前に状態を確認しておきましょう。また厨房機器や家具・内装は、譲渡の範囲や状態をトラブル防止のため文書で確認しておくことが重要です。引き継ぎ後に「壊れていた」「修理費用がかかった」と揉めるケースもあるため、写真やリストで記録を残すと安心です。
賃貸契約の引き継ぎ条件を必ず確認する
オーナーチェンジは物件の引き継ぎだけではなく、貸主からの賃貸契約の承諾が必要です。オーナーが変わる場合、貸主の同意なしでは名義変更できない場合が多いです。事前に不動産会社や貸主と条件をしっかり確認しておきましょう。
オーナーチェンジを検討したら早めに相談する
「店舗を譲渡して、オーナーチェンジしたい」と思ったら、早めに専門家へ相談して動き始めましょう。オーナーチェンジには時間もコストもかかりますが、早い段階から準備を始めることで、スムーズに進められ、コストを削減につながる場合もあります。
期限が迫って余裕がなくなると選択肢が限られ、譲渡条件を妥協せざるを得ない状況になることも。専門業者に相談し、店舗譲渡を計画的に取り掛かることが成功のポイントです。

無償での譲渡の場合も契約書を交わす
無償で事業譲渡を行う場合も、事業譲渡契約書を取り交わします。契約書を作成しておくことで、後々のトラブルを防止できるでしょう。
売掛金や仕入れ契約の精算を確認する
取引先との間に未払いの請求書や在庫の扱いがある場合、誰が支払うのかを明確にすることが大切です。特に仕入先やリース契約については、オーナー交代のタイミングで契約変更や解約が必要になるケースも。 契約内容を確認し、引き継ぐか解約するかを決めておきましょう。
飲食店のオーナーチェンジに関するよくある質問
飲食店のオーナーチェンジを検討する際、「どのような方法があるのか」「費用はどのくらいかかる?」「告知のタイミングは?」など疑問を感じることもあるでしょう。最後にオーナーチェンジに関してよくある質問を紹介します。
飲食店のオーナーチェンジの方法は?
飲食店の店舗譲渡し、オーナーチェンジするには主に以下の3つの方法があります。
造作譲渡
店舗の内装や設備など物理的な資産を譲渡する方法です。飲食店のオーナーチェンジで一般的に利用されています。閉店時に必要となる原状回復工事のコストを節約可能。また譲受人が開業までの時間とコストを削減できるため、双方にとって利点があります。
事業譲渡
店舗の物理的な資産だけではなく、従業員やブランド、営業ノウハウなどの無形資産を含めて譲渡する方法です。飲食店の顧客基盤やブランド価値もあわせて事業をスムーズに引き継ぎできます。
株式譲渡
法人所有の飲食店の際に利用される方法です。会社の株式を譲渡すると、店舗を含めた事業全体を移転します。株式譲渡では経営権も移転するので、経営構造を大きく変更しなくても新しい経営者に事業を委ねられるのが特徴です。
飲食店のオーナーチェンジにかかる費用は?
オーナーチェンジの際、仲介手数料や契約書作成費などで数十万円程度が一般的です。ですが、原状回復工事(スケルトン工事)が不要になる場合が多く、閉店よりコストが抑えられるでしょう。また厨房機器や内装をそのまま引き継ぐため、撤去や処分費用も発生しません。さらに造作譲渡金を得られるケースもあります。
オーナーチェンジ後、営業許可書はそのまま使えますか?
飲食店の営業許可書は、オーナーごとに発行されるため名義変更が必要です。基本的には、新しいオーナーが保健所へ再申請し、審査を経て許可を取得します。許可証の更新ができるかどうかは地域ごとにルールが異なるため、事前に所轄の保健所に確認することをおすすめします。
従業員や取引先へオーナーチェンジを告知するタイミングは?
オーナーチェンジがほぼ確定した契約締結後、できるだけ早めに告知するのが理想的です。通常、引き渡しの1~2ヵ月前が目安です。従業員や取引先は、今後の営業体制や取引条件に大きく関わります。事前に誠意を持って伝えることで信頼関係を守れるでしょう。
従業員には、オーナーチェンジ後も雇用契約が継続するか終了するかを明確に伝え、不安を和らげることが大切です。退職勧奨や雇用条件の変更があれば、労働基準法に基づいて誠実に説明します。
仕入先やリース契約を結んでいる企業には、契約変更や支払い方法の確認が必要になる場合があります。スムーズな引き継ぎのため、オーナーチェンジの成立が決まり次第、早めに担当者へ連絡してください。
飲食店のオーナーチェンジなら「買取の神様」にお任せください
飲食店のオーナーチェンジを成功させるには、流れ知り、法的手続きなどをしっかり行うことが大切です。税務署や保健所、消防署といった公的機関への許可や届出などは漏れがないように確認しましょう。
「買取の神様」では飲食店の移転や閉店に関する相談を承っています。居抜き売却でしたら、造作や備品をそのまま売却できるため、閉店に伴う原状回復工事の削減ができ、造作譲渡金を得られるケースもあります。相談・査定は無料ですので、いつでもお気軽にお問い合わせください。



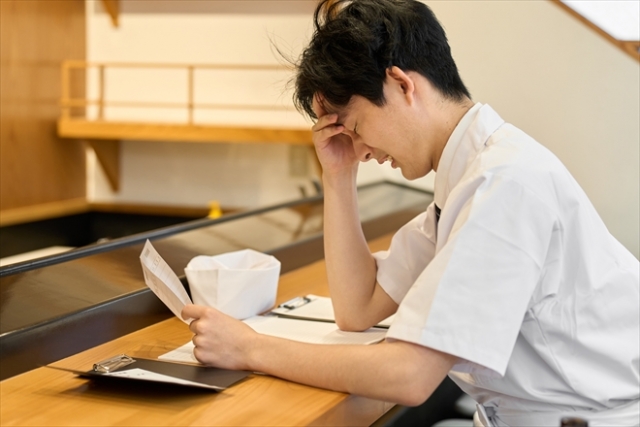
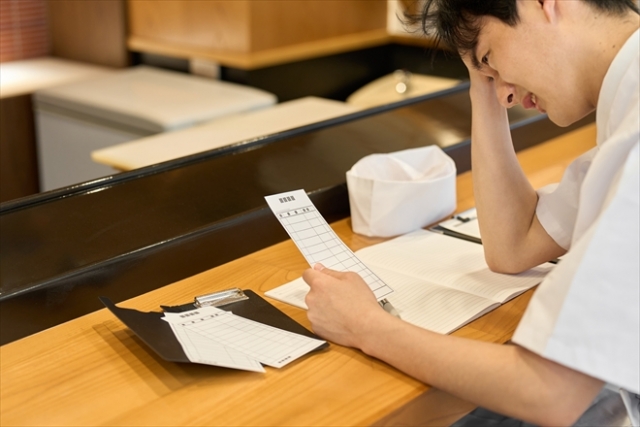



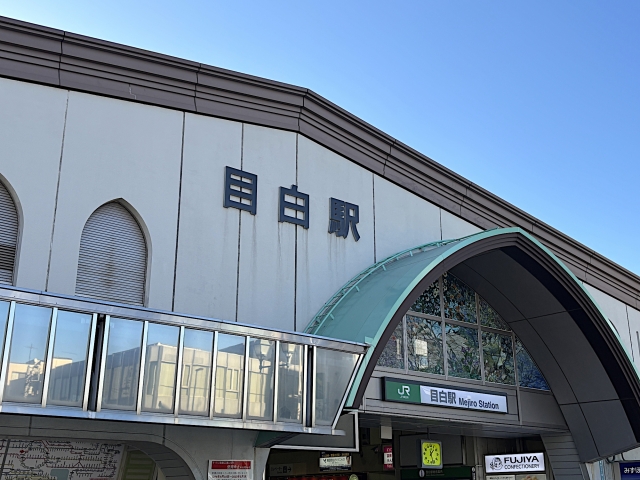




コメント