居酒屋の開業は、飲食業界での経験を活かしながら独立を目指す方にとって、大きな可能性を秘めた選択肢です。しかし、開業にあたってはさまざまな準備や手続きが必要です。
店舗物件の選定から内装工事、必要な許認可の取得、従業員の採用まで、検討すべき事項は多岐にわたります。とくに開業時の資金計画は慎重に立てる必要があり、初期費用の見積もりや運転資金の確保が重要です。
この記事では、居酒屋開業に必要な具体的な手順や注意点を解説していきます。
居酒屋を開業する方法

居酒屋の開業方法は、大きく分けて「個人で開業する方法」と「フランチャイズで開業する方法」の2つがあります。それぞれに特徴やメリット・デメリットがあるため、自身の経験や資金力、目指す経営スタイルに合わせて選択しましょう。
個人で開業する

個人での開業はフランチャイズに加盟せず、自らの経験やアイデアを活かして独自の居酒屋を立ち上げる方法です。店名やコンセプト、メニューの構成まで、すべてを自分の裁量で決定できるため、理想のお店を運営できます。
この方法の最大のメリットは、経営の自由度が高いことです。
メニューや価格設定、サービス内容などすべてを自分の判断で決められるため、市場の変化や顧客ニーズに柔軟に対応できます。独自のサービスで他店と差別化を図ることで、固定客の獲得も期待できます。
また、加盟金やロイヤリティーなどのフランチャイズ特有の費用が不要なため、初期投資を抑えられる点も大きなメリットです。さらに、店舗が軌道に乗れば、利益はすべて自分のものになります。
一方で、開業当初は知名度が低いことがデメリットです。また、経営ノウハウを一から構築する必要があります。しかし、すでに飲食店での経験をお持ちの方であれば、さほど問題ではないでしょう。
フランチャイズで開業する

大手居酒屋チェーンなどのフランチャイズ本部と契約を結んで店舗を運営する方法です。
加盟店は本部のブランドや経営ノウハウを活用できる代わりに、加盟金やロイヤリティー(利用料)を支払わなければいけません。また、フランチャイズ本部と加盟店はそれぞれ独立した事業体として運営されるため、経営責任はオーナー自身のものとなります。
この方法のメリットは、知名度の高いチェーン店の看板を掲げられることです。開業当初から集客が期待でき、本部からの経営サポートも受けられます。
また、仕入先が確立されているため、食材の調達も円滑に進められます。従業員の教育プログラムも整備されているため、人材育成の面でも心強いでしょう。
一方で、デメリットとしては経営の自由度が低い点が挙げられます。メニューや価格設定、店舗の内装など、多くの面で本部のルールに従わなければいけません。
また、加盟金やロイヤリティーの支払いが必要となるため、収益面での負担も大きくなります。さらに、本部やほかの加盟店で不祥事や食中毒などの問題が発生した場合、自店舗のイメージにも影響が及ぶ可能性があり、その対応は困難をともなうことがあります。
こちらの記事では、居酒屋の売上平均について解説しています。繁盛しているお店の特徴や売上アップの方法も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

また、こちらの記事では居酒屋の開業の成功率につて詳しく解説しています。居酒屋が閉店する原因や開業を成功させるコツをご紹介しているので、ぜひ合わせてご覧ください。

居酒屋を開業する手順

居酒屋の開業には、コンセプトの決定から店舗のオープンまで、さまざまなステップが必要です。ここでは、開業までの具体的な手順を10のステップに分けて解説します。計画的に準備を進めることで、スムーズな開業が実現できるでしょう。
1.コンセプトを決める

コンセプトの決定は、オープンの1年前から半年前に着手すべき重要な要素です。
居酒屋業態には数多くのスタイルが存在しており、ターゲット層や提供する価値によって、お店の方向性は大きく変わってきます。
たとえば、50代の男性をメインターゲットにする場合でも「味と素材にこだわった本格的な料理」を提供するのか「仕事帰りに気軽に立ち寄れる雰囲気」を重視するのかで、店舗の在り方は大きく変わります。前者であれば「創作居酒屋」や「ご当地居酒屋」に、後者であれば「立ち飲み屋」や「大衆酒場」にするべきです。
コンセプトを具体化する際は、以下の「7W2H」の観点から検討することが効果的です。

- Why(なぜその店を開くのか)
- When(いつ利用してもらうのか)
- Where(どこに出店するのか)
- Who(誰が運営するのか)
- Whom(誰をターゲットにするのか)
- What(何を提供するのか)
- Which(どのような特徴を持たせるのか)
- How(どのように運営するのか)
- How much(価格帯をどうするのか)
以上を明確にすることで、ブレのないコンセプトを打ち出せます。
2.事業計画書を作成する

事業計画書は、開業までの道筋と開業後の経営方針を具体的な数値として示すものです。コンセプトの決定と並行して、オープン1年前から半年前には取り組み始めましょう。
事業計画書には、開業の動機やコンセプト、会社名、店名といった基本情報に加え、資金計画の詳細を記載します。具体的には、現在保有している資金額や開業前の投資計画、借入計画、そして開業後の売上目標や資金繰りの見通しなどを、具体的な数値として明記する必要があります。
とくに重要なのは、希望的観測にもとづいた数値ではなく、市場調査や競合分析にもとづいた現実的な計画を記入することです。なぜなら、この事業計画書は金融機関からの融資を受ける際の重要な審査材料となるためです。
また、計画書は第三者が見ても理解できる構成と表現で作成することが重要です。箇条書きやグラフ、表などを効果的に活用し、読み手にとって分かりやすい内容となるよう心がけましょう。
実現する可能性の高い綿密な計画を立てることが、開業後の安定した経営にもつながります。
3.資金を調達する

資金調達は、オープンの半年前から本格的に取り組む必要があります。必要な資金は大きく分けて、開業資金と運転資金の2種類です。
開業資金には、店舗物件の取得費用や内装工事費、設備・備品の導入費用、各種許認可の取得費用、そして開業前の広告宣伝費などが含まれます。とくに店舗物件の取得と内装・設備にかかる費用は、全体のなかでも大きな割合を占めることになります。
一方、運転資金は開業後の事業運営に必要な資金です。具体的には、店舗の賃料や水道光熱費、食材などの仕入れ費用、従業員の人件費、継続的な販促費用などが含まれます。
一般的に居酒屋が軌道に乗り始めるまでには半年以上かかるとされています。そのため、最低でも6ヵ月分の運転資金を確保しておくことが望ましいです。
重要なポイントは、開業資金をできるだけ抑えて運転資金を多く残すことです。なぜなら、運転資金に余裕があれば、開業後に予期せぬ事態が発生しても状況を立て直すための施策を打てるためです。
とくに居抜き物件の活用は、内装設備費用を大幅に抑えられる有効な選択肢となります。
4.店舗物件を探す
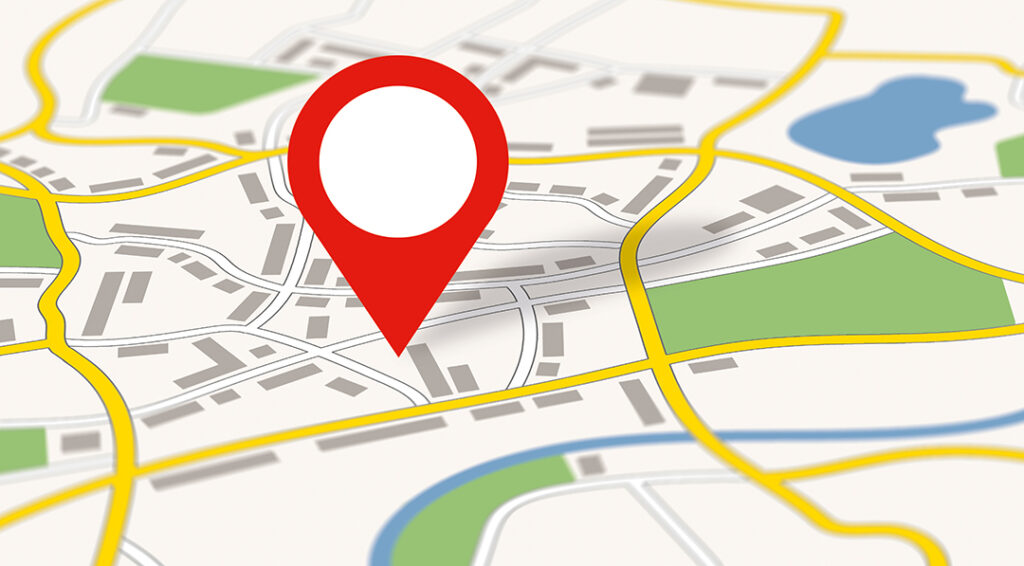
店舗物件の選定は、オープンの半年前から着手する必要があります。
物件探しの前提として、出店予定エリアの競合調査を丁寧に行うことが重要です。コンセプトや事業計画と実際の物件との間にズレが生じないよう、周辺の家賃相場や競合店の状況を把握しておきましょう。
物件選びでは、厨房の広さやレイアウト、給排水設備の状態、店舗周辺の人通りや競合店の有無など、具体的なチェックポイントをリスト化すると効率的です。とくに、設定した目標月商の1/10以内の家賃設定であることは、重要な選定基準となります。
よい物件をいち早く見つけるためには、不動産業者との関係づくりも大切です。事業計画書の作成段階から複数の不動産業者に足を運んで信頼関係を築くことで、条件のよい物件情報をいち早く得られる可能性が高まります。
とくにおすすめなのが、居抜き物件の活用です。居抜き物件であれば、厨房設備や内装がすでに整っているため、初期投資を大幅に抑えられます。内外装工事費用を削減して運転資金をより多く確保することで、開業後の経営安定にもつながるでしょう。
5.内外装の工事を行う

内外装工事は、オープンの3ヵ月前から開始するのが理想的です。工事の内容や範囲は、店舗のコンセプトに大きく関わってくるため「どのような空間を作りたいか」というビジョンを明確にしたうえで、業者選定を行いましょう。
工事を依頼する業者は、飲食店の施工実績が豊富な専門業者を選ぶことをおすすめします。飲食店特有の設備や法規制に精通している業者であれば、スムーズな工事進行が期待できるためです。また、見積もりを取る際は複数の業者に依頼し、工事内容や価格を比較検討しましょう。
一般的な内装工事期間は、着工から2週間〜2ヵ月程度です。ただし、物件の規模や状態によっては、さらに長期間を要する場合もあります。
また、商業ビルなどでは工事可能な時間帯に制限があり、夜間工事が必要になるケースもあるため、工期の設定には余裕を持たせましょう。
6.厨房機器や備品を揃える

厨房機器や備品の調達は、オープンの3ヵ月前から計画的に進めていく必要があります。初期投資を抑えるためには、リサイクル品の活用もおすすめです。
毎年、多くの飲食店が開業と廃業を繰り返しているため、状態のよい中古機器や備品が流通しています。ただし、購入の際は動作確認や衛生面のチェックを徹底することが重要です。
とくに注意が必要なのが、厨房のレイアウトです。一度設置した機器の配置を変更することは難しいため、作業動線や効率性を十分に考慮する必要があります。調理場からホールへの動線、食材の搬入経路なども含めて、綿密なシミュレーションを行いましょう。
工事が完了した際には、水回り設備や空調設備、厨房機器の動作確認を必ず実施します。また、設備の取扱説明書の確認や保証書類の受け取りも忘れずに行いましょう。
7.資格・許認可を取得する

居酒屋の開業には、食品衛生責任者資格・防火管理者資格・飲食店営業許可が必要です。
食品衛生責任者は、すべての飲食店に1店舗につき1名の常駐が義務付けられています。都道府県が実施する講習を受講することで資格を取得でき、一度取得すれば全国で有効です。
防火管理者は、建物全体の収容人数が30人以上となる場合に必要です。この人数には従業員も含まれ、建物内に収容可能な総人数で判断されます。資格には「甲種」と「乙種」があり、甲種は2日間、乙種は1日間の講習受講が必要です。
飲食店営業許可は、保健所への申請が必須です。申請にあたっては、まず保健所で事前に相談し、店舗の工事完了予定日の約10日前に必要書類を提出します。その後、保健所による施設検査を受け、基準を満たしていれば営業許可証が交付されます。
開業に間に合うよう、各資格や許可を取得しましょう。
お酒の資格を取るならJSFCAへ

8.メニューを考案する

居酒屋のメニューは顧客を集める要素のひとつです。ターゲット層に向けて、居酒屋の魅力が伝わる料理や飲みもののメニューを考案しましょう。コンセプトをメニューに反映させると、より魅力が伝わりやすくなります。
メニューを考えるときは、定番のメニューだけではなく、流行りや地域ならではの食材を使ったメニューもおすすめです。他店にはないメニューを考案すると、競合店との差別化も図れます。
また、独自性を高めるだけではなく、経営面で利益率の向上も考慮する必要があります。サイドメニューやオプションメニューを充実させると、より幅広いターゲット層が狙えて、売り上げ向上にもつながりやすいです。
ただし、取り扱う食材の種類が増えれば、その分経費も高くなります。メインメニューで使う食材で別のメニューを考えたり、適切な価格を設定したりして、売り上げと経費のバランスを考慮しましょう。
メニューを考案したら実際に料理をつくり、スタッフや知り合いから感想をもらうのがポイントです。はじめから完璧なものがつくれるわけではないため、改善点を反映させながらよりよいメニューを完成させましょう。
9.集客施策を実施する

集客施策の実施は、オープンの2ヵ月前から着手すべき重要な項目です。開業時は最も注目を集めやすい時期であり、この機会を最大限に活用することが、その後の集客にも大きく影響します。
具体的な施策としては、まずお店のホームページの制作があります。店舗の基本情報やコンセプト、メニューなどを分かりやすく掲載し予約受付機能なども検討しましょう。
また、Googleビジネスプロフィール(GBP)への登録も必須です。登録するとGoogleマップの検索結果に表示され、顧客に店舗の基本情報や営業時間、アクセス方法などを簡単に確認してもらえます。
SNSの活用も効果的です。InstagramやFacebookなどで内装工事の様子や料理の写真、スタッフの紹介など開業に向けた準備の過程を発信することで、オープン前から期待感をもたせられます。
たとえ好立地であっても、効果的な集客施策を行わなければ、十分な集客は望めません。オープン前から計画的に情報を発信することで、開業と同時にスタートダッシュをかけられます。
居酒屋であれば、食べログ、ぐるなび、ホットペッパーへの掲載も検討しましょう。掲載方法や掲載内容次第では、掲載金額の7倍以上の売上も期待できるためです。
居抜きの神様であれば、こうしたグルメポータルサイトへの掲載に関してもノウハウを持っています。業態やエリア毎に適切なアドバイスをさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
<参考>
・飲食店のホームページ制作法!無料ツール、相場、見本を紹介|大阪のホームページ制作会社セブンデザイン
10.従業員を募集・教育する
スタッフの採用と教育は、オープンの1ヵ月前から開始するのが適切です。採用時期が早すぎると開業までの空白期間が長くなり、内定辞退のリスクが高まります。一方で、オープン直前の採用では、十分な研修期間が確保できない可能性があります。
必要な従業員数は店舗の規模によって異なりますが、ホールスタッフは「収容人数÷テーブル数÷4」を目安に考えます。たとえば、収容人数30人でテーブルが5台の居酒屋であれば、曜日や時間帯に応じて1〜2名のホールスタッフが必要です。
キッチンスタッフは、メニュー構成によって人数が変わってきますが、同規模の店舗で複数の調理セクションがある場合、繁忙時には2〜3名の人員を確保しておくことが望ましいでしょう。
採用活動では、求人サイトやSNSの活用、知人からの紹介など、複数の募集形態を活用するのがおすすめです。応募が少ない場合や採用が決まらない場合は、オープン20日前、10日前と段階的に追加募集をかけ、必要な人員を確実に確保しましょう。
11.店をオープンする

オープン後が、居酒屋経営の本当のスタートとなります。しかし、この時点はあくまでもスタート地点に立ったに過ぎません。実際の経営では、さまざまな課題に直面することになります。
飲食店経営が難しいとされる理由は、主に3つあります。
- 競争の激しさ:居酒屋の数は多く、顧客獲得の競争は激化しています。
- 初期投資の高さ:設備投資や運転資金の負担が大きくなります。
- 継続的な品質管理の必要性:料理の味や接客サービスの質を常に一定以上に保つ必要があります。
居酒屋が軌道に乗るまでには時間がかかるため、焦って無理な営業を行うと、体調不良やモチベーション低下につながるおそれがあります。長期的な視点を持って、着実に運営していきましょう。
居酒屋を開業するために必要な資格・許可
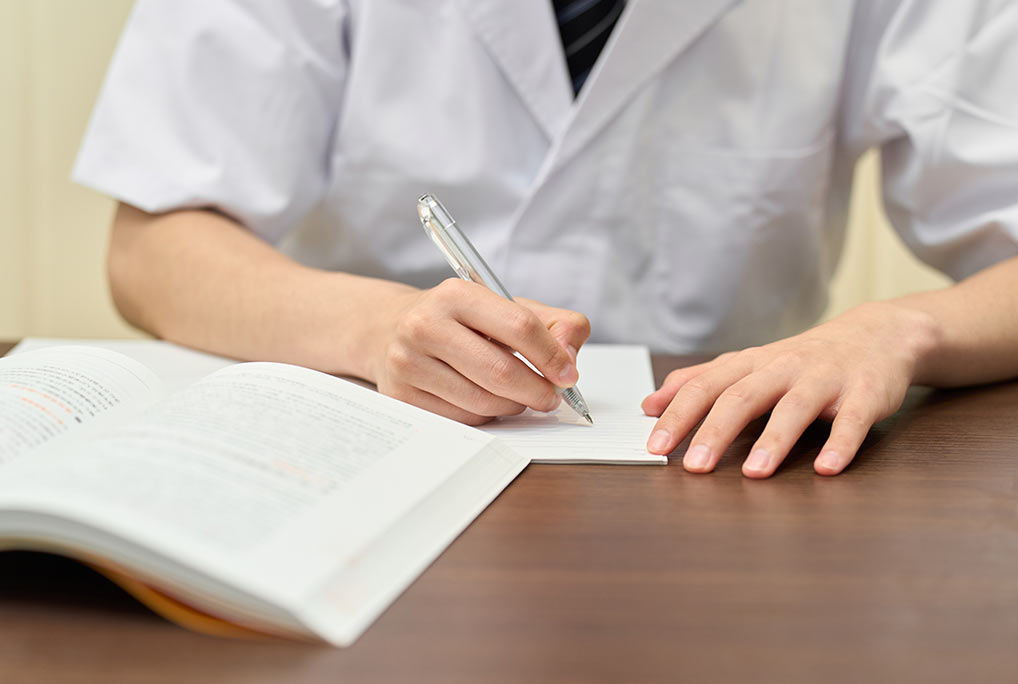
居酒屋を開業するには、食品衛生責任者・防火管理者・飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業の4つの資格と許可が必要です。それぞれの役割や手続き先を確認して、開業の準備に向けて資格と許可を取得しましょう。
食品衛生責任者
食品衛生責任者は、飲食店の衛生管理を統括する責任者であり、居酒屋を開業する際には各店舗に必ず1人配置しなければなりません。保健所で「飲食店営業許可」を取得する際にも必須となる資格です。
取得方法は以下のとおりです。
- 都道府県知事などが実施する講習会、または適正と認められた講習会を受講
- 講習は1日で実施され、修了後に資格が交付される
【有資格者として認められる職種・学歴】
- 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
- 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者
- 大学で医学・歯学・薬学等の課程を修めた者
食品衛生責任者は、衛生管理計画を策定したり、従業員に衛生教育を行ったりするのが業務内容です。食品管理や調理での衛生管理に関するルールを守る役割も担っています。
防火管理者
防火管理者は、火災を未然に防ぎ、安全に店舗を運営するための責任者です。居酒屋を開業する際には、消防法に基づき防火管理者を選任し、防火体制を整えることが義務付けられています。
【取得方法と区分】
- 甲種防火管理講習:延床面積300㎡以上の店舗が対象。2日間
- 乙種防火管理講習:延床面積300㎡未満の店舗が対象。1日間
防火管理者になるには、延床面積が300平米以上の店舗なら甲種防火管理講習、延床面積が300平米未満の店舗なら乙種防火管理講習を受講する必要があります。甲種防火管理講習は2日間にわたって講習内容を学び、乙種防火管理講習は1日間基礎的な知識を身につけます。
防火管理者は、安全に経営するために消化器の設置場所や、火災発生時の避難経路などの防火管理計画を作成するのが主な役割です。スタッフへの周知や定期的な訓練の実施も、防火管理者の業務のひとつです。
防火管理者は開業準備だけでなく、開業後も継続的に防火体制を維持する責任を担います。適切な計画と定期点検を徹底することが、安全で信頼される店舗経営につながります。
飲食店営業許可
飲食店営業許可は、食品を取り扱う営業を始める際に必ず必要となる許可です。取得には保健所での手続きが求められ、近年は窓口申請に加えてオンライン申請も可能となっています。
申請時に必要な書類は以下のとおりです。
- 事業計画書
- 店舗の見取り図
- 設備に関する資料
- 食品衛生責任者の資格証明書
申請書類をもとに審査を行い、店内の衛生状態や食品の取り扱い方法などに問題がないと判断されれば許可がおります。審査後に交付された飲食店営業許可証は、店舗内に掲示して大切に保管しましょう。
深夜酒類提供飲食店営業
深夜酒類提供飲食店営業は、午前0時以降も居酒屋を営業したいときに必要な許可です。上記の3つの資格や許可を取得したうえで、深夜営業を行うには別で深夜酒類提供飲食店営業の許可を得る必要があります。
- 提出先:店舗所在地を管轄する警察署
- 入手方法:警察署で入手、または警視庁ホームページからダウンロード可能
記入が必要な届出書は、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書と営業の方法に関する届出書の2種類です。提出後は公安委員会により、建物の構造や防音設備、照明設備、営業時間、酒類の提供方法、18歳未満の従業員の有無などが確認されます。
申請内容に不備がなければ、受理されて10日ほどで深夜営業の開始が可能です。許可を取らずに深夜営業をすると、最大6か月の営業停止を命じられるおそれがあります。営業停止は売り上げに大きく影響してしまうため、居酒屋を開業するときは申請忘れに注意しましょう。
出典:警視庁公式サイト
居酒屋の開業にかかる費用

居酒屋の開業には、物件取得費や内外装工事費、厨房機器や備品の購入費用などさまざまな初期投資が必要です。ここでは、開業に必要な費用の内訳を詳しく解説し、適切な予算計画の立て方について説明します。
物件取得費

居酒屋の物件取得費用は、立地や広さによって大きく異なりますが、一般的に約200万円程度が必要です。
ただし、これはあくまで目安であり、立地条件のよい都心部や繁華街ではさらに高額になることもあります。物件取得費用には、不動産会社への仲介手数料、保証金、敷金・礼金などが含まれます。
一般的な目安として、物件取得費用は全体予算の20%程度に抑えましょう。この配分を守ることで、その後の内装工事や設備投資、さらには運転資金の確保にも支障をきたさずに済みます。
こちらの記事では、小さな居酒屋を経営するメリットについて解説しています。小さい居酒屋の目安や開業する際の注意点も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

内外装工事費
居酒屋の開業において、内外装工事は最も大きな初期投資のひとつです。店舗のコンセプトや雰囲気を具現化する重要な工事で、規模やデザインによって数十万円から数百万円の費用が必要となります。
一般的に、内外装工事費は開業資金全体の約50%を占めます。
具体的には、床・壁・天井などの内装工事や、看板・外観などの外装工事、給排水設備の整備、電気工事、空調設備の設置などが含まれます。予算の半分を占める大きな支出となるため、適切にコントロールしなければいけません。
工事費用を抑えるためには、必ず複数の業者から見積もりを取りましょう。見積もりを比較検討することで適切な価格を把握できます。
もし内外装工事費の費用を抑えたいのであれば、居抜き物件がおすすめです。元々、居酒屋だった居抜き物件であれば既存の内装や設備を活用できるため、コストを削減しながらスピーディーに開業できます。
厨房機器・什器・備品費
居酒屋の開業には、調理場のコンロや冷蔵庫、シンクなどの厨房機器が必要です。さらに、テーブルや椅子、照明器具などの什器、食器類や調理器具などの備品も揃えなければいけません。
これらの設備にかかる費用は、一般的に100万〜200万円程度です。全体の開業費用のなかでは約30%を占める重要な投資項目となります。
費用を抑えるためには、中古品の活用が効果的です。また、ほかの飲食店経営者とのネットワークを活用し、不要になった設備を譲り受けることでコストを削減できます。
こちらの記事では、ジョッキの容量について解説しています。ビールジョッキの平均容量や美味しく注ぐ方法も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

こちらの記事では、生中の量について解説しています。一般的な量や安く提供する方法も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

運転資金
運転資金は、店舗の日々の運営に必要不可欠な資金です。具体的には店舗の家賃や水道光熱費、従業員の人件費、食材などの仕入れ費用、広告宣伝費などが含まれます。
一般的な居酒屋の場合、月々の運転資金は店舗の規模や従業員数によって大きく変動します。とくに開業直後は、知名度が低く来店客数が安定しないため、十分な売上を確保できない可能性があります。経営が軌道に乗るまでの運転資金は、事前に確保しておきましょう。
運転資金の目安として、最低でも6ヵ月分を用意することをおすすめします。この期間があれば、開業後の予期せぬ支出や売上の変動にも余裕を持って対応できるためです。開業前の資金計画では、この運転資金の確保を重要な検討項目として位置付けておきましょう。
緊急資金
緊急資金は、予期しないトラブルが起こったときに備えておくための資金です。設備や機器を中古で購入した場合、急な故障で修理費用がかかったり買い替えるための費用がかかったりする可能性があります。
予想以上に人手が足りないと感じたときは、臨時でアルバイトを雇うための人件費も発生します。万が一、緊急資金がなければ予期しないトラブルに対応できず、経営を維持できなくなるリスクも高いです。
居酒屋を開業するときは予期しない事態が起こるのを想定して、緊急資金を準備してから開業しましょう。
居酒屋を開業した後の失敗ケース
居酒屋の開業後は、さまざまな要因で経営が行き詰まるケースがあります。ここでは、実際によく見られる失敗事例を紹介します。
立地が適切ではなかった
立地選びの失敗として最も多いのは、ターゲット層と出店エリアが合っていないケースです。たとえば、サラリーマン向けの居酒屋を住宅街に出店する、高単価の創作居酒屋を学生街に出店するといった場合、想定する客層との需要が合わず、集客しにくくなります。
競合店の調査不足も大きな失敗要因です。同じような業態の店舗が密集しているエリアでは、明確な差別化ができなければ埋もれてしまう可能性が高くなります。
一方で、周辺に競合店がまったくないエリアは、そもそも居酒屋への需要自体が低い可能性もあるため、慎重な判断が必要です。
また、駅からの距離や店舗の視認性なども重要な要素です。駅から徒歩15分以上かかるアクセスの悪い場所や、通りから店舗が見えにくい場所は、集客の大きな障壁となります。
とくに飲酒をともなう居酒屋の場合は車で来店できないため、駅からのアクセスのしやすさが重要となります。
利益率が低すぎた

売上が順調に見えても、利益率が低ければ経営は徐々に行き詰まっていきます。飲食店の場合、適正な営業利益率は10〜15%とされていますが、この数字を下回る店舗は早急に経営方法を改善しなければいけません。
利益率が低い主な原因のひとつは、仕入れコストが高すぎることです。仕入れ先の選定が適切でない場合や発注量の管理が不十分な場合、食材コストが必要以上にかさんでしまいます。
また、競合店を意識しすぎるあまり、価格設定を必要以上に抑えてしまうケースも少なくありません。
人件費の管理も重要な課題です。来客数に対して過剰な人員を配置したりシフト管理が不適切だったりすると、人件費率が高くなり利益を圧迫します。とくに開業直後は、必要以上にスタッフを雇用してしまいがちです。
また、水道光熱費の無駄も見逃せません。厨房機器の使用方法が非効率だったり空調の設定が適切でなかったりすると、想定以上の光熱費がかかってしまいます。
さまざまな経費を適切にコントロールして健全な利益率を確保することが、安定した経営への近道となります。
こちらの記事では、飲食店の持ち込み料金について解説しています。持ち込み料の相場や持ち込みのメリット・デメリットも取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

コンセプトやメニューに誤算が生じた

コンセプトやメニューの設定ミスは、居酒屋経営において深刻な問題を引き起こします。とくに、ターゲット層が不明確な場合、店舗の方向性全体が曖昧になってしまいます。
たとえば「学生向けなのか、社会人向けなのか」という基本的な位置づけが定まっていないと、価格帯や内装などが中途半端になり、結果として誰からも選ばれない店舗になりがちです。
競合店との差別化も重要な課題です。同じエリアの他店と似たようなメニューや雰囲気では、顧客に選ばれる理由が乏しくなります。とくに、すでに地域に根付いた強力な競合店が存在する場合、独自性がないことは致命的な問題となります。
開業後の軌道修正には多くの時間とコストがかかるため、当初からしっかりとしたコンセプト設計を行う必要があります。
こちらの記事では、成功するメニュー開発のコツは?気を付けたいポイントも解説しています。コンセプトの明確化から原価管理まで、成功につながるポイントを押さえましょう。

居酒屋の開業を成功させるポイント

居酒屋の開業を成功に導くためには、事前の準備から開業後の運営まで、さまざまな要素に注意を払う必要があります。ここでは、多くの成功店に共通する重要なポイントを紹介します。
コンセプトを具体的に決める
「どんなお店にしたいのか」という明確なビジョンがあってこそ、その後の具体的な準備作業がスムーズに進められます。
まず重要なのは、市場調査にもとづいたコンセプト設定です。「リーズナブルな大衆居酒屋」「こだわりの地酒が楽しめる和食居酒屋」など、具体的なイメージを描きます。
その際、立地周辺の競合店の状況や想定される客層のニーズを十分に調査することが、不可欠です。とくに重要なのが、競合店との差別化です。
同じようなコンセプトの店舗が周辺に多い場合、価格競争に巻き込まれる可能性が高くなります。そのため、メニュー構成や価格帯、サービス内容など、独自の特徴を持たせることが重要です。
明確なコンセプトが決まれば、内装業者への指示もスムーズになり、店舗デザインや設備の選定もぶれることなく進められます。また、スタッフの採用や教育の方針も定まりやすくなります。
立地を慎重に選ぶ
立地選びは、居酒屋経営の成否を大きく左右する重要な要素です。出店を検討する際は、まず徹底的な競合調査を行う必要があります。周辺の居酒屋の業態やメニュー、価格帯を把握せずに出店すると、予期せぬ競争に巻き込まれる可能性があります。
エリアの特性を理解することも重要です。たとえば、高齢者が多い地域では落ち着いた雰囲気で質の高い料理を提供する居酒屋が好まれます。
一方、学生が多いエリアでは、リーズナブルな価格設定が求められます。ターゲット層に合わせた店づくりを心がけましょう。
さらに、居酒屋の場合は駅からの距離が集客に大きく影響します。お酒を提供する店舗であるため、お客様は車での来店ができません。そのため、駅から徒歩圏内の場所に出店することが望ましいでしょう。
利益率の高いメニューを考案する
利益を確保できるメニュー構成は、居酒屋経営の安定性を左右する重要な要素です。とくに利益率が高いのは、アルコール類です。ビールやサワー、カクテルなどの原価率は比較的低く、安定した利益を見込めます。
また、揚げ物類も原材料費を抑えやすく、提供価格に対して高い利益率を確保できます。さらに、デザート類も原価を抑えやすいメニューのひとつです。
利益率が高いメニューを店舗の看板商品として打ち出すことで、安定した経営基盤を築けます。ただし、利益率だけを追求するのではなく、お客様に満足していただける品質とのバランスを取ることも重要です。
定期的にメニューの原価率を見直し、適切な価格設定を心がけましょう。
綿密に資金計画を立てる

開業準備における最も重要な要素のひとつが、綿密な資金計画です。お店のコンセプトにもとづいて、必要な資金を具体的に算出し、現実的な事業計画を立てることが重要です。
とくに注意すべき点は、開業資金の調達方法と運転資金の確保です。内装工事費や厨房機器、什器備品などの初期投資に加え、ある程度の運転資金を見込んでおく必要があります。また、予期せぬ支出に備えて、ある程度の予備費も確保しておくことが賢明です。
融資を利用する場合は、より詳細な事業計画書が求められます。売上予測や収支計画、資金繰り表など、具体的な数字にもとづいて計画しましょう。
金融機関は、これらの計画の実現可能性を厳しく審査します。そのため、甘い見通しや不十分な計画では、そもそも資金調達の段階で行き詰まってしまう可能性があります。
こちらの記事では、小さな居酒屋経営者の年収について解説しています。年収の相場や年収を上げる方法も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

客層に合った方法で集客する
集客は居酒屋経営を成功させるうえで、最も重要な要素のひとつです。とくに個人経営の居酒屋は、開業時の知名度が低いため、計画的な集客戦略が必要となります。まずは、ターゲットとする客層を明確にし、その層に効果的にアプローチする方法を選びましょう。
近隣のお客様を主なターゲットとする場合は、チラシやポスターなどの紙媒体が効果的です。地域の住民や会社員に直接アピールできる手段として、ポスティングや駅前でのチラシ配布なども検討しましょう。
一方、観光客や若年層をターゲットとする場合は、ホームページやSNS、グルメサイトなどのWeb媒体の活用が重要です。
想定する客層の年齢や性別によって、情報収集の方法は大きく異なります。たとえば、20〜30代はSNSでの情報収集が主流ですが、40〜50代は口コミサイトや紙媒体を重視する傾向があります。
ターゲット層の特性を理解し、適切な媒体選択を行うことで、効率的に集客できるでしょう。
<参考>
・ホームページ制作 大阪 | Web制作会社LIVALEST
居抜き物件を検討する
初期投資を抑えるなら、居抜き物件の活用がおすすめです。居抜き物件とは、前の店舗の内装や設備をそのまま引き継いで使用できる物件のことです。
とくに居酒屋として使用されていた物件であれば、厨房設備や内装、空調設備などをそのまま活用できるため、開業コストを大幅に削減できます。
ただし、物件選びの際は設備の状態や耐用年数、必要な修繕の有無などを専門家に確認してもらうことが重要です。また、前店舗のイメージを払拭するためのリニューアル費用も考慮に入れましょう。
まとめ

居酒屋を開業するには、コンセプトを考えたり資金を調達したりして、資格や許可を取得する必要があります。講習会への参加や物件の取得などに時間がかかるため、事前に開業する流れを把握するのがポイントです。
開業するのにかかる費用も確保する必要があり、運転資金や緊急資金まで準備してから開業すると安心です。少しでも費用を抑えて居酒屋を開業したい方は、前の店舗の内装や設備がそのまま使える居抜き物件を検討しましょう。
居抜きの神様では、東京都の居抜き物件情報をご紹介しています。内装や設備はもちろん、物件周辺の情報もお届けするため立地選びの参考にしていただけます。東京都内で居酒屋を開業したい方は、居抜きの神様の物件情報をご覧ください。
<併せて読みたい>
・SNSを活用した集客はこちらの記事をご覧ください。
・オフィスデザイン会社を徹底比較!依頼するメリットや注意点を紹介:SFA JOURNAL
・店舗を紹介するための方法8選
<参考>
・全国で選ばれる「クリーンライフ」の安心サービス
(クリーンライフは、幅広い水道トラブルに対応するサービスを展開しています。特に、トイレの詰まりに関しては、専用機材を使用し迅速かつ確実に解決へ導きます。)













コメント