カフェの開業を考えていて、開業にかかる資金の目安がつかめずに悩んでいる方もいるでしょう。カフェの開業には多くの資金が必要になるため、開業を成功させるためには、必要な資金について、内訳も含めて正確にとらえておくことが重要です。
本記事では、カフェの開業に必要な資金の詳細について詳しく解説します。金額の大まかな目安のほか、業態ごとの必要な金額の違いや資金の調達方法も解説するため、ぜひ参考にしてください。
喫茶店やカフェの開業資金の目安と内訳
喫茶店やカフェを開業するためには、必要な資金を正確に把握することが大切です。喫茶店やカフェを開業する場合、必要な資金の総額は500〜1,000万円が目安とされています。ただし、本当に必要な金額は、業態や店舗の立地、規模などによって変わります。
30席近い大きなカフェの場合は、おおよそ面積は20坪で坪単価40~70万円で800~1,400万円くらい資金が必要ともいわれています。自分の開業の実態に合った、しっかりとした資金計画を立てて、成功のための第一歩を踏み出しましょう。
以下では、喫茶店やカフェの開業に必要な資金の内訳と、それぞれの目安となる金額について詳しく解説します。
物件取得費
物件取得費とは、礼金・仲介手数料・前家賃・保険料など、物件の契約にかかる費用のことです。立地や店舗などの諸条件にもよりますが、飲食店を開業する際の物件取得費の目安は、家賃の12ヵ月分といわれています。
具体的には、保証金または敷金が賃料の3〜12ヵ月分、礼金が0〜2ヵ月分、仲介手数料が1ヵ月分、前家賃が日割計算されることに加え、保険料、造作譲渡料がかかります。
たとえば、家賃が10万円の物件の場合、保証金が6ヵ月、礼金が2ヵ月であれば、前家賃と仲介手数料がそれぞれ1ヵ月分かかるため、賃料の10ヵ月分である100万円がかかります。
また、これに保険料や造作譲渡料が加わると、およそ12ヵ月分がかかることも珍しくありません。かかる費用を、120〜150万円程度と見ておけば、まず安心でしょう。
また、賃料は開業後の固定費として毎月の支払いに直結します。立地が良いほど賃料は高くなるため、毎月の収支の計画とすり合わせたうえで、物件を選ぶ必要があります。
内外装費
内外装費とは、店舗の内外装にかかる費用の総称です。具体的な内訳としては、設計・デザイン費と工事費に分類できます。
設計・デザイン費は、総工事費用から一定の割合で換算する算出方法のほか、坪単価や人件費をベースにする方法があります。また、このほかにも、店舗の規模などによっても費用は変わります。
内装工事費は、店舗内の床や壁、天井の表面などの内装工事全般にかかる費用です。素材や設備のグレードによって費用は変わるため、店舗のブランドイメージとの兼ね合いを見ながら調整する必要がありますが、10坪の店舗であれば、坪単価50万〜200万円程度で見積もっておけばよいでしょう。
一方で、外壁工事は費用が高額になりやすく、10坪の店舗の場合で250万円〜500万円が相場です。内装とのバランスも重要になるため、こちらも資金と相談しながら施工内容を判断しましょう。
設備費
設備費とは厨房などの設備のほか、電気・ガス・水道等の設備工事にかかる費用です。10坪の店舗の場合は、200〜250万円程度が相場です。
ただし、厨房設備にかかる費用は、店舗の規模や業態、設備のメーカーによって大きく変わります。とくに、厨房設備は新品で揃えるか、中古やリース品を使うかなどで、かかる費用が異なるため、早い段階で方針を決めておくことが重要です。
開業資金に余裕がない場合、すべての厨房設備を新品で揃えるのは現実的ではありません。居抜き物件の備え付けや中古品の利用を積極的に考えましょう。また、居抜き物件の場合は、修理やメンテナンスにかかる費用は借主負担になるため、必要な費用として見込んでおく必要があります。
また、設備にかかる費用は、建物の状態によって変わる場合があります。内装のリニューアルを考えている場合は、早い段階でデザイン設計事務所に相談することが大切です。
備品費
備品にかかる費用は、店舗の広さのほか、業態やオーナーのこだわりによっても変化します。また、店のブランディングにも関わってくるため、開業資金と相談しながら折り合いをつける必要があります。
厨房設備などと同様、備品をすべて新品で揃えると、費用は一気にふくらむため、資金に余裕がない場合は、中古品などの使用を積極的に考えましょう。ただし、POSレジのような電化製品は耐用年数があります。
製造から年月が経つにつれて故障しやすくなるため、保証期間がどの程度残っているか、また、保証の範囲には何が含まれているかなどもしっかり確認しましょう。
広告・宣伝費
広告・宣伝費は、お店の知名度を得るためにかかる費用全般のことです。開店して間もない時期は、多くの人にお店を知ってもらうことが非常に重要です。
飲食店の場合は厨房設備などにかかる費用が大きいため、つい広告・宣伝費を削ってしまいやすいですが、集客に直結する費用のため、十分にお金をかけることが大切です。
広告・宣伝費としてかかる具体的な内訳としては、看板やチラシ、ポスティング費用のほか、Webサイトの作成費用やグルメサイトへの掲載料などがあります。相場は20〜50万円程度を見込んでおきましょう。
運転資金
開業時に必要な運転資金としては、最低でも約半年分の費用を想定する必要があります。運転資金に含まれる具体的な内訳としては、賃料や光熱水費、人件費、仕入れ費用などが含まれます。
とくに、開店してしばらくはしっかりとした売上が立たないため、そこから運転資金を出すことがほとんどできません。安定するまでの費用は最初にしっかりと確保しておくことが重要です。
業態別|カフェの開業資金の違い
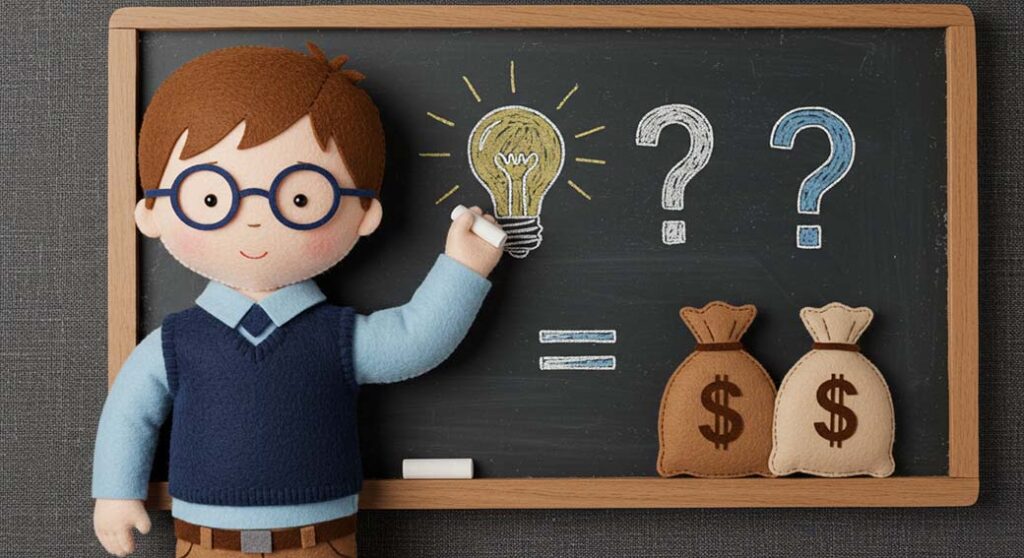
カフェの開業に必要な資金は、業態によって大きく異なります。とくに、個性的なブランディングを取り入れたい場合や、移動型の店舗で開業したい場合は、費用のかかるポイントが一般的なカフェと異なる場合があります。
内訳も含めて、開業資金の把握が必要です。ここでは、業態ごとの開業資金の目安について解説します。
喫茶店
一般的な喫茶店の場合、開業資金として必要な金額は700〜1,500万円程度です。店舗の規模や立地などでも費用は変わりますが、場合によっては高額な資金が必要になるため、綿密な資金計画を立てておきましょう。
とくに、喫茶店のオーナーのなかにはコーヒーにこだわりたい方も多くいます。この場合、良質なコーヒー豆や特殊な焙煎機などが必要になるケースも多いため、導入費用や設置スペースの確保なども含めて、開業を計画する必要があります。
また、喫茶店ならではの、落ち着いてくつろげる雰囲気を提供したい場合、席間のスペースを十分に確保する必要があります。賃料に対して席数が少なくなる場合もあるため、それらを考慮したうえで、運転計画を立てましょう。
店舗型カフェ
店舗型カフェとは、店舗を構えて営業するカフェのことです。店舗型カフェの場合、提供する食事の内容によってかかる開業資金が大きく変わります。
| 種類 | 調理工程 | 具体例 |
| 軽飲食 | 本格的な調理工程がなく、調理の際に煙やにおいが発生しない、または少ないもの | 飲料、サンドイッチ、お菓子などスイーツ類 |
| 重飲食 | 調理工程に火や油を使用し、調理の際に煙やにおいが発生するもの | フライドポテトなどの揚げ物、パスタ、ハンバーグ |
調理をほとんど行わず、飲料を中心に提供する「軽飲食」で開業する場合は、店舗の設備が軽食のみに対応していればよく、スタッフの人数も比較的少人数ですむため、開業資金が比較的低く収まる傾向があります。ただし、客単価が低くなりやすいことを見込んだうえで、計画を立てる必要があります。
一方で、厨房で本格的な調理を行う「重飲食」で開業する場合、物件の設備もより本格的なものが必要です。重飲食では調理に火を使うため、ガスや電気、給排気により多くの費用を投じる必要があります。
また、排気に臭いや煙が混ざることから、大家が入居に難色を示すことも少なくありません。店舗探しにも時間がかかりやすく、費用も高くなる傾向があります。ただし、軽飲食と比較すると重飲食の方が利用者1人あたりの単価が上がりやすくなるため、売上は高くなる傾向にあります。
このように、軽飲食と重飲食の違いによって開業資金や売上に大きな差が出るため、どちらのスタイルで開業するのか、あらかじめしっかりとした検討が必要です。
軽飲食の居抜き事例
都内のJR大塚駅から徒歩5分、建物1階の16.52坪の、物件軽飲食向けの居抜き物件では、前のテナントもカフェ・カフェバーだったため、造作を大きく変えることなく、比較的コンパクトな改装で開業できます。
毎月の賃料は528,000円、敷金・保証金は6ヵ月、権利金・礼金も2ヵ月と、物件取得費も平均的です。
重飲食居抜き事例
都営大江戸線の都内の都庁前駅から徒歩7分、建物1階24.34坪の重飲食向けの居抜き物件では、ハンバーガー店として営業していたことから、充実した厨房設備が整っています。
賃料は月額880,000円、敷金・保証金は6ヵ月、権利金・礼金も1ヵ月と、物件取得費も平均的ですが、軽飲食よりも賃料はやや高めです。賃料には、店舗の広さや立地も影響するものの、一般的に軽飲食よりも高くなる傾向にあります。
自宅型カフェ
自宅の一部を改装して経営する「自宅型カフェ」では、家賃がかからないのがメリットです。開業資金を計画するうえでも、一般的なカフェの運転資金から、物件取得費用や家賃を差し引いて考えられます。
ただし、自宅が住宅街にあるような場合だと、集客の面で不安があります。その分、広告費にお金をかける必要があるため、それほど費用に大きな差が出ない場合もあります。とくに、飲食業の場合は立地が非常に重要となり、集客方法も含めて開業を計画する必要があります。
また、一般住宅はもともと飲食業向けに作られてはおらず、改装費用が予想外にかさむ可能性がある点にも留意しておきましょう。
移動型カフェ
移動型カフェとは固定した店舗ではなく、車両などを使って営業するカフェのことです。移動型カフェは店舗がないため物件取得費はかかりませんが、車両の購入費や改造費用がかかります。
一般的に、開業にかかる費用は250〜300万円程度が目安です。また、このほかにも、車両の駐車場代やガソリン代を見込んでおく必要があります。
また、移動型カフェは公道で営業できず、公園やスーパーの敷地などを借りる必要があります。使用料を請求されることも想定されるため、これらの費用も考慮しておきましょう。
間借り型カフェ
間借り型カフェとは、すでに存在する店舗の営業時間外に、その店舗を借りて営業するスタイルのカフェのことです。利用時間ごとの料金を支払うだけで営業を始められるため、開業にかかる初期費用がほとんどかかりません。
また、貸す側としても、営業時間外の店舗を有効活用できるため、双方にとってメリットのある業態です。間借り型カフェに必要な費用の相場は、都心部で1日あたり5,000〜15,000円程度、郊外で1日あたり2,000〜8,000円程度が目安です。
喫茶店やカフェの開業資金の調達方法
喫茶店やカフェの開業には高額の開業資金が必要ですが、すべてを自己資金でまかなえない場合があります。その場合は、金融機関などから開業資金を調達する必要があります。以下では、喫茶店やカフェの開業資金の調達方法について解説します。
自己資金
開業する場合、自身の貯蓄を自己資金として持ち出すのが基本です。自己資金は借り入れた資金ではないため、利息が生じず返済の必要もないのが利点です。開業してしばらくは売上が満足に上がらず、安定するまで時間を要する可能性があるため、資金繰りの負担をいかに減らせるかは非常に重要です。
喫茶店やカフェの開業には多額の開業資金が必要です。すべてを自己資金でまかなうのは難しいですが、借り入れる金額を少しでも減らせるよう、自己資金をしっかりと積み立てておきましょう。
また、自己資金が少ないと、金融機関からの借入に悪い影響を与えることがあります。事業計画に信憑性が低いと見なされ、審査に通らないこともあるため注意が必要です。
公的金融機関からの融資
公的金融機関とは、政府が全額または一部の資金を出資している金融機関で、政府系金融機関とも呼ばれています。具体的には、日本政策金融公庫などがこれに該当します。
公的金融機関は、中小企業や個人に対する出資を目的として設立されているため、個人事業主によるカフェの開業資金の融資にも応じてくれます。無保証人、無担保で開業資金を借り受けられるのも大きなメリットです。
日本政策金融公庫の場合、新規開業・スタートアップ支援資金として、7,200万円までの資金を借り入れることが可能です。返済期間は設備資金の場合は最長20年で、利率は2〜4%程度です。
公的金融機関からの融資は、民間金融機関などからの融資と比べて、負担が少ないのが特徴です。開業資金が不足している場合は、優先的に検討してみましょう。
出典:日本政策金融文庫「新規開業・スタートアップ支援資金」(https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html)
民間金融機関からの融資
公的金融機関以外に、民間の金融機関から融資してもらう方法もあります。民間金融機関は、メガバンクや地方銀行、信用金庫の3種類に分類できますが、喫茶店やカフェの開業程度の規模であれば、地方銀行と信用金庫が借入先の対象です。
民間金融機関は公的金融機関よりも借入の条件は劣りますが、小規模の事業者にも融資してくれやすい傾向があります。また、地方銀行や信用金庫は地域密着型のところも多いため、これまでの融資の実績にもとづいた相談や提案を受けることもできるでしょう。
ただし、民間金融機関は審査が厳しく、承認されるまで日数もかかります。開業資金の確保のためにも、早めに動き出しましょう。
親族・知人からの借入
身内に頼ることに抵抗感がない場合は、親族や知人から開業資金を借り入れるのもひとつの方法です。
親族や知人から資金を借りるメリットとしては、金利や返済期限の融通がきくことが挙げられます。借り入れる金額にもよりますが、金融機関からの借入ほど返済がシビアではないため、精神的なプレッシャーが少ないのもよい点です。
一方で、身内であるからこそ、返済が滞った場合に人間関係を損なってしまいやすいです。親族や知人であるからこそ、返済がルーズにならないようにしましょう。
また、身内から資金を提供してもらう場合に気をつけたいのが、贈与税です。当事者同士の話し合いで、開業資金の貸し借りを行ったとしていても、返済期限が設けられていない場合は、実質的な贈与と見なされる場合があります。
仮に、1年間の贈与額が110万以上の場合、110万円を超えた額に贈与税がかかります。贈与と見なされてしまった場合、借りた金額によっては想定外の多額の出費が生じる可能性があるため、第三者から見て贈与と思われないような外形を整えることが必要です。
具体的には、返済期限を書面で記しておき、その期日どおりに返済することなどがあります。
出典:国税庁「贈与税がかかる場合」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm)
共同経営での共同出資
複数人が共同で開業する場合は、それぞれが自己資金で出資する方法もあります。単純に用意できる資金が2人分になるため、単独で開業するよりも資金に余裕が生まれやすいのがメリットです。
一方で、共同出資は利益を分配することになってしまう点や、その割合についてトラブルになりやすい点がデメリットです。また、閉店する際のお互いの負担の割合なども、トラブルにつながりやすい傾向があります。
共同経営者は事業における最大のパートナーであり、関係を損なわないためにも、資金はあらかじめしっかりと話し合い、懸念点をお互いに取り除いておくことが大切です。
投資家からの出資
カフェの開業資金を投資家から集める方法もあります。投資家からの出資ときくと、スタートアップ企業などに投資するエンジェル投資家をイメージしやすいですが、個人経営の喫茶店やカフェの規模の場合は、あまり現実的ではありません。
一方で、現在では、個人が集められる資金調達の方法として、クラウドファンディングが広く知られるようになりました。小規模な開業であっても、多くの人の共感を集められれば、多額の資金を集められる場合があります。
また、実際にクラウドファンディングで資金を調達し、開業に至ったケースも複数存在します。話題性に自信があれば広告活動も兼ねて、クラウドファンディングを利用するのもよいでしょう。
補助金・助成金
小規模事業者の開業に対して、国や自治体が助成金を交付している場合があります。助成金は借入とは異なるため、基本的に返済は不要です。助成金は、開業資金の総額に対してそこまで金額は大きくありませんが、資金を集めることに苦労する開業時には大きな助けになるはずです。
しかし、助成金には条件があるため、必ずしも誰もが受けられるわけではありません。制度自体に上限額もあります。交付金によって交付までの条件が異なるため、事前に制度をしっかり読み込むようにしましょう。
喫茶店やカフェの開業資金を抑えるには

喫茶店やカフェの開業資金を抑えるには、いくつかのコツがあります。以下では、それぞれの方法について具体的に解説します。
居抜き物件を活用する
カフェの開業資金を抑える方法として効果が高いのが、居抜き物件の活用です。カフェに必要なものがひと通り揃っているため、店舗に関わる費用を大きく抑えられます。
具体的には、内装や什器が揃っていることに加えて、電気・ガス・水道の設備が整っているため、追加の工事がほとんど必要ない場合が多く、施工費を大きく下げられます。また、前の利用者が利用していた焙煎機などの特殊設備が残っていれば、さらに費用を抑えられます。
ただし、居抜き物件で気にしておきたいのが、前の店舗が事業を撤退している事実です。飲食業において立地は非常に重要ですが、その立地に問題がある可能性があります。
そのほかにも、店舗運営に悪影響をもたらす要因が周囲に存在する可能性があるため、契約する際は念入りに調査をしたうえで決定するようにしましょう。
フリーレント物件を活用する
フリーレント物件とは、賃貸借契約で定めた条件を満たすことで、一定期間の賃料が無料になる契約のことです。賃料が無料になる期間は契約内容によって異なりますが、固定費として発生する賃料がしばらくの間は無料になるため、開業当初の負担を軽減できます。
ただし、フリーレント物件は無料の期間が終了しても、契約時に定めた期間内は契約を解除できません。契約を解除する場合は、契約予定だった期間分の家賃に加えて違約金を支払う必要があるなど、条件が厳しく定められている場合もあります。賃料の安さにむやみに飛びつくのではなく、契約前に契約条件をしっかりと確認するようにしましょう。
また、家賃交渉はフリーレント物件以外でも可能です。管理会社や大家と交渉して、契約月の日割り分の賃料を無料にできないか相談する方法もあります。この場合は、繁忙期ではなく閑散期の方が交渉をうまく進めやすいことが一般的です。
中古品やリース品を活用する
喫茶店やカフェの開業資金を抑えるためには、中古品やリース品の利用も積極的に検討してみましょう。
厨房機器は新品で購入しようとすると非常に高額になることが多いため、資金に不安が残る開業時期は、機器を新品で揃えることは避けた方が賢明です。中古品で厨房機器を揃えた場合、新品の半額程度で購入できることも多いため、開業資金を大きく抑えられます。
質の良い中古品を揃えるためには細かなチェックが必要ですが、資金の節約効果は高いため、ぜひ検討してみましょう。厨房機器を新品で揃えることにこだわりがある場合は、経営が軌道に乗ってから検討することをおすすめします。
また、開業資金に余裕がなく中古品の購入も難しい場合は、リース品の利用も検討してみましょう。毎月のランニングコストは上がりますが、月々数万円の費用で、総額で数百万円する新品の厨房機器を使用できるのは大きなメリットです。
ただし、リース契約には契約期間が存在します。途中解約の条件なども事前にしっかりチェックしておきましょう。
内装や家具をDIYする
内装や家具をDIYすることでも、開業資金を大きく抑えられます。内装や家具に関する費用は、開業資金のなかでも大きな割合を占めます。とくに、業者に施工を依頼すると数十万円から数百万円の費用がかかることも多く、店舗が広いほど金額は高額になりやすいです。
また、内装や家具はデザインや材質にこだわればこだわるほど、費用はどんどん高くなってしまうため、DIYが得意であれば自分で工事を行うのもよい方法です。
ただし、電気やガス、水道は工事に特殊な技術や資格が必要な場合があります。無理をせず、専門業者に依頼しましょう。
また、慣れていないにもかかわらず無理にDIYを進めると、工事が思ったように進まず、スケジュールが遅延してしまうこともあります。中途半端にDIYをした結果、自分たちではどうにもできず、結果的に業者を頼ることになる可能性もあります。
費用を抑えるために進めたことが、逆に費用をかけることにもなりかねないため、事前にしっかりと計画を立てることが重要です。
SNSで宣伝や告知を行う
広告費や宣伝費を抑えるために、SNSを積極的に使いましょう。最近では、XやInstagram、TikTokなどからお店を調べる人も増えており、とくに、情報の感度が高い若年層ほど、その傾向が高くなっています。SNSから口コミにつなげることもできるため、SNSを効果的に使うことで、集客を増やせる可能性があります。
SNSはアカウントの作成に費用がかからないため、無料で利用を始められます。SNSは拡散力が強く、アピール次第では、自身のお店について広く周知することが可能です。
また、開店前から開店に至るまでの様子を継続的に発信することで、開店時点での店の認知度を事前に高められます。
開業資金以外に押さえておくべきポイント

喫茶店やカフェを開業すると際は、開業資金以外にも押さえておくべきポイントがあります。以下で、詳細を解説します。
店舗の立地
飲食店を開業する場合、立地は非常に重要です。人通りの多さも集客につながる大切な要素ですが、それ以上に重要なのが、お店のコンセプトやターゲット層に対して立地が合っているかどうかです。
喫茶店やカフェの場合、美味しいコーヒーにこだわりたいのか、それとも安さを重視したいのかで、カフェの性格は変わります。また、食事もしっかり提供したいのか、軽食程度にとどめておくのかで、おのずと来店者も変わりますが、立地としっかり合っていないとなかなか集客にはつながりません。
また、立地はターゲット層にも大きく関わります。サラリーマンやOLをターゲットにしたいのか、それともファミリーで通える店にしたいのかで、出店すべき店舗のエリアはまったく違うものになります。ファミリー層をターゲットにする場合は、駐車場も確保しなければならないため、店舗選びの条件がより難しくなるでしょう。
さらに、立地は店舗の賃料にも大きく影響してきます。人通りが多く人気のエリアは賃料が高いため、集客がうまくいっても維持費の高さで経営が苦しい場合もあります。客単価や回転率の見込みが甘いと経営計画自体を見直さなければならなくなるため、事前の想定をしっかり立てておく必要があります。
店舗のコンセプト
喫茶店やカフェでは、お店全体のコンセプトをしっかりと決めましょう。コンセプトとは、お店の基本方針や方向性のことです。
「美味しいこだわりのコーヒーを出す店」「リーズナブルな価格のファミリーで楽しめる店」などのお店の方針に関わることのほか、オープンカフェが併設されている、ペットと一緒に来店できるなど、お店の性格を決定づける特徴的なものまでを含みます。
とくに、現代では大手チェーン店が全国の至るところに出店しており、提供するサービス内容も非常に充実しています。また、個人経営の喫茶店やカフェもすでに数多く存在しているため、新規店舗としての存在感を示すためにも、コンセプトは重要です。
コンセプトを明確化することは、来店するお客さんに対するアピール以外にも、事業計画の立てやすさにつながります。コンセプトのはっきりしているお店は、融資する側としても出資の判断をしやすいため、事前にしっかりと考えておきましょう。
メニューの種類と内容
メニューの種類と内容は、お店のコンセプトに沿ったものにしましょう。また、メニューが多過ぎると、廃棄の食材が増える可能性があります。開業してしばらくはメニューの数を絞って営業するとよいでしょう。
また、メニューが決まったら、食材の仕入れも先の検討も進めます。内装や設備などの準備と並行して進めておくことで、余裕を持って開店の日を迎えられます。
必要な免許と資格
喫茶店やカフェを開業するために必要な資格も、事前に取得しておきましょう。飲食店の場合、まず、食品衛生責任者を設置する必要があり、そのうえで飲食店営業許可をとる必要があります。
食品衛生責任者の資格は、講習会かeラーニングを受講することで取得できます。栄養士や調理師などの資格がある場合は、講習会の受講は免除されます。
出典:厚生労働省「食品衛生管理者」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049348.html)
必要な届出
食品衛生管理者の資格を取得したら、飲食店営業許可を管轄の保健所に申請する必要があります。店舗の検査を受ける必要があるため、開業の準備ができたタイミングで検査を受けられるようにしましょう。
具体的には、内装や設備の工事がすべて終了し、調理台などの搬入もすんでいる必要があります。検査の結果、店舗が施設基準を満たしていれば、営業許可証が発行されます。検査の当日に発行されることはないため、何日かかるかは事前に確認しておきましょう。
さらに、自家焙煎やコーヒー豆を挽いて販売する場合は「営業届出」を出す必要があります。管轄の保健所に忘れず届け出ましょう。
また、店舗の建物の区分によっては、防火管理者を設置する必要があります。店舗の広さによって、受けるべき講習の種類が変わるため、店舗の内装設計が固まった後で受講を申し込みましょう。
このほかにも、個人事業主としてカフェを営業する場合は、所轄の税務署に開業届を出す必要があります。青色申告をする見込みのある人は、青色申告承認申請書もあわせて提出しておきましょう。
出典:東京都保険医療局・保健所「食品関係営業許可申請の手引」(https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyokatodokede/files/kyoka_tebiki202303.pdf)
出典:厚生労働省「密封包装食品製造業の対象食品」(https://www.mhlw.go.jp/content/000868566.pdf)
出典:東京消防庁「防火管理者が必要な防火対象物と資格」(https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/jissen/p04.html)
こちらの記事では、カフェの開業方法について解説しています。必要な資格や許可も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

まとめ

喫茶店やカフェの開業にかかる費用は店舗の設備や立地などによって異なりますが、開業のためにはまとまった資金が必要です。個人資金だけでまかなえる人は限られているため、開業資金をどのように調達するかは、カフェの開業を成功させるための重要なポイントです。
また、開業にあたっては、どのように費用を抑えるかも重要です。開業資金のなかで大きな割合を占めるのは内装・設備工事費であることからも、居抜き物件での開業は、資金面で圧倒的に有利です。
居抜き物件で開業する場合、物件探しが成功の鍵を握ります。理想の物件を自力で探し出すことは非常に難しいため、信頼できる企業やサービスのサポートを受けるようにしましょう。
居抜きの神様では、居抜き物件を多数掲載しており、さまざまな条件から物件を探せます。喫茶店に適した小型物件を中心に集めており、独自の情報ルートで入手した独占未公開物件も限定公開しています。
提供する飲食内容によっても必要な設備が異なることを踏まえ、さまざまな種類の居抜き物件を取り揃えているため、希望に添った店舗を見つけられます。喫茶店開業を目指す方はぜ、ぜひお気軽にご利用ください。













コメント