カフェの開業を考えているものの、何から手をつけたらよいか悩んでいる方は多いでしょう。スムーズにカフェ経営を進めるには、開業前の段階で疑問を解決する必要があります。
本記事では、開業方法の種類や必要な資格・手続き、内装・資金の考え方まで、押さえておきたい基本情報を解説するとともに、つまづきやすい疑問にも一問一答形式でわかりやすくお答えします。これからカフェ開業を始めたい方は、ぜひ参考にしてください。
カフェの開業方法

カフェを開業する場合、自力開業やフランチャイズなど多様な方法があります。それぞれに特徴があり、自分の経験や資金、目指す店舗のイメージに応じて選ぶことが大切です。ここでは、主な開業方法を3つ解説します。
自力で開業する
理想のカフェを形にしたいなら、自力での開業が最も自由度の高い方法です。店舗のコンセプトから内装、メニューまで、自分の想いやセンスを表現できます。
一方で、物件探しから内装工事、保健所の許可申請、集客に至るまで、あらゆる準備を自分で進めなければなりません。時間や労力がかかるうえ、開業資金や運転資金の確保といった資金面の管理も重要です。
手間はかかりますが、自力開業は、自分だけのこだわりを詰め込んだカフェを実現したい方にとって、挑戦する価値のある選択肢といえるでしょう。
カフェで働きながら準備する
開業に不安がある場合は、カフェで働きながら準備する方法もよいでしょう。現場を体験すると、接客の流れや店舗運営の実態を学べるため、開業後のミスマッチを防ぎやすくなります。
実店舗での日常業務は、メニュー開発や仕入れ管理、シフト調整などさまざまです。開業前に経験を積んでおくと、経営視点を持った準備がしやすくなります。また、スタッフとの関係づくりや顧客対応のコツも身につき、独立後にも大いに役立ちます。
できるだけリスクを抑えながら現実的にカフェ開業を目指したい方は、先んじて実務経験を積むことをおすすめします。
フランチャイズに加盟する
カフェを開業するにあたって、未経験でも安定した運営を目指したい場合は、フランチャイズへの加盟が有効です。既存ブランドの知名度や運営ノウハウの活用により、開業直後から一定の集客が期待できます。
フランチャイズ本部からは、店舗運営マニュアルや研修制度、開業前後のサポートが提供されるのが一般的です。立地選定や内装デザインの支援が受けられるケースもあり、自力での開業に比べて負担を抑えやすいでしょう。
一方で、加盟金やロイヤリティが必要となるため、契約内容を十分に比較・検討することが大切です。
カフェの開業に必要な資格と許可

カフェの開業には、必ず取得しなければならない資格と、必須ではないものの取得しておくと役立つ資格があります。ここでは、主な資格を解説します。
必須の資格・許可
カフェを開業する場合、食品衛生協会と保健所に関連する資格や許可を得る必要があります。それぞれの概要を確認しておきましょう。
【食品衛生協会】食品衛生責任者
カフェ営業に欠かせない資格のひとつが、食品衛生協会が主宰する「食品衛生責任者」です。衛生管理の基本知識を身につけ、食中毒や衛生上の事故を未然に防ぐための資格であり、カフェに限らず、飲食を提供するすべての事業者に義務付けられています。
資格を取得するには、各都道府県の食品衛生協会が実施する6時間程度の講習を受ける必要があります。特別な試験はなく、比較的取得しやすい資格ですが、取得しなければカフェを開業できません。ただし、調理師や栄養士の免許を保持している場合は免除されます。
出典:一般社団法人東京都食品衛生協会(https://www.toshoku.or.jp/training/index.html)
【保健所】飲食店営業許可申請
カフェを開業する際は、店舗の所在地を管轄する保健所で「飲食店営業許可」を取得しましょう。法令により、飲食を扱う施設では必ず取得しなければならない許可です。
許可を得るには、事前に施設の図面や申請書類を提出し、保健所による現地確認と設備基準の適合が求められます。厨房のレイアウトや手洗い場の設置など、衛生面での条件が細かく定められており、それを満たすことが許可の条件です。
申請には手数料がかかり、設備の完成後に検査を受けて合格すると営業許可証が交付されます。スムーズに申請するためにも、開業計画の初期段階から要件を把握しておくことが重要です。
そのほかの資格・許可
カフェで提供するメニューや店舗の仕様によっては、ほかにも必須となる資格・許可があります。また、取得しておくと営業に役立つ資格も少なくありません。ここでは、主な資格・許可を4つ解説します。
【消防署】防火管理者
一定規模以上のカフェを開業する際には「防火管理者」の選任が求められる場合があります。火災発生時の対応や日常の防火体制を整えるうえで、法律に基づく重要な役割です。
具体的には、店舗の収容人員が30人以上、または延べ床面積が300㎡を超える場合、防火管理者の選任が義務づけられます。防火管理者には、大規模施設にも対応できる「甲種」と小規模施設向けの「乙種」があり、店舗の規模に合わせて選ぶことが大切です。
将来的に複数店舗の展開や規模拡大を見込むなら甲種を、現時点で小規模運営にとどめる場合は乙種でも問題ありません。
たとえ選任義務がなくても、安全な運営のために防火対策への理解と準備は欠かせません。条件を早めに確認し、必要に応じて講習の受講を検討しましょう。
出典:東京消防庁「防火管理者が必要な防火対象物と資格」(https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/jissen/p04.html)
【保健所】菓子製造業許可
カフェで焼き菓子やケーキを製造し、販売用に包装して提供する場合は「菓子製造業許可」が必要です。これは食品衛生法にもとづき、製造工程を衛生的に管理するために設けられた許可制度です。
たとえば、併設の製造スペースで菓子を作って店頭や通販で販売する場合や、ほかの販売ルートに提供するケースでは、この許可が求められます。飲食店営業許可とは別で、調理スペースや設備にも独自の基準があり、専用の作業場や手洗い設備などの設置が必須です。
申請や検査も保健所で行われ、地域によって細かな要件が異なるため事前確認が欠かせません。
将来的に焼き菓子の販売を拡大したいと考えている場合は、早い段階から許可取得を見据えた厨房設計・運営計画を立てておくとスムーズです。
出典:厚生労働省「営業許可業種の解説」(https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000706467.pdf)
【日本バリスタ協会】JBAバリスタライセンス
高品質なコーヒーを提供したいと考えるなら「JBAバリスタライセンス」を取得するのもよいでしょう。日本バリスタ協会(JBA)が認定する民間資格で、エスプレッソを中心とした本格的な技術と接客スキルを体系的に学べます。
ライセンスには「JBAバリスタライセンス1st」と「2nd」の2段階があり、カフェで実務経験のある方やこれから開業を目指す方が多く受講しています。講習では抽出技術に加えて、マシンの扱い方、衛生管理、ラテアートなども習得できるため、専門性の高いカフェを開業したい方にとって強みとなる資格です。
必須資格ではないものの、コーヒーにこだわりのある店舗を目指すなら、JBAの資格取得は信頼性やスキルの裏付けとして活用できます。
出典:日本バリスタ協会(https://jba-barista.org/license)
【日本スペシャルティコーヒー協会】コーヒーマイスター
コーヒーに強いこだわりを持ってカフェを開業したいなら、コーヒーマイスターの資格取得を検討するのも一案です。日本スペシャルティコーヒー協会(SCAJ)が認定する民間資格で、専門的な知識と技術を段階的に習得できます。
資格を取得するなかで、コーヒー豆の生産・流通・焙煎・抽出といった工程を包括的に学べるため、品質の高いコーヒーを提供することが可能です。取得には講座を受講し、筆記試験に合格する必要があります。
専門性をアピールしたい場合や、ブランディングを強化したい場合に有効な資格といえるでしょう。
出典:一般社団法人日本スペシャルティコーヒー協会(https://scaj.org/meister/about-meister)
カフェの開業に関するQ&A
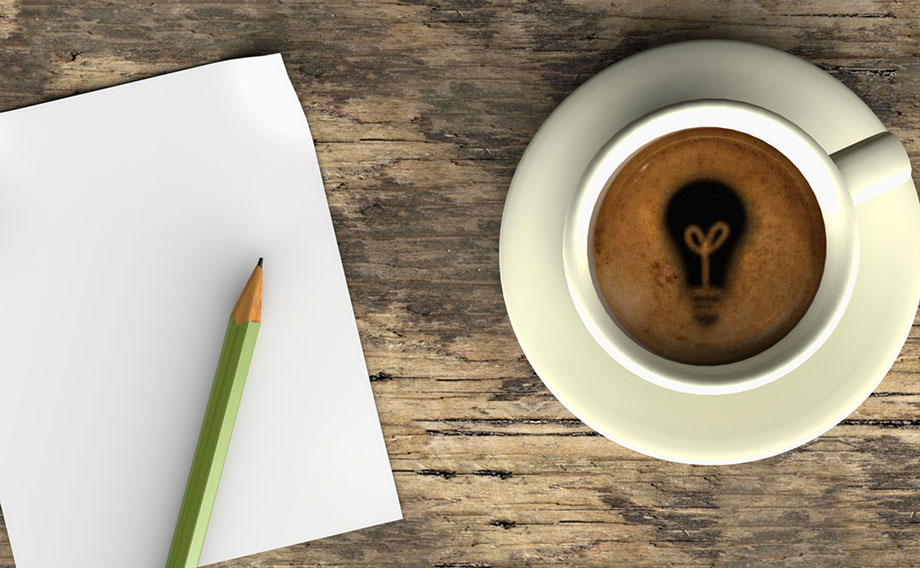
カフェを開業するにあたって、疑問や悩みを抱えている方は多いでしょう。ここでは、よくある質問を9つ解説します。
カフェの内装を決めるポイントは?
内装はカフェの雰囲気や世界観を表現する重要な要素です。ターゲット層やコンセプトに合った空間づくりは、来店のきっかけや滞在時間に影響を与えます。
設計を考える際は、ターゲット層を明確にして、年齢層や過ごし方に合った空間を意識することが大切です。
たとえば、落ち着いた雰囲気を好む大人向けなら木目調や間接照明を取り入れ、SNS映えを重視する若年層向けなら色使いや装飾を工夫するなど、ターゲットによって内装の方向性は変わってきます。
また、席数や動線、照明の配置など、快適性や回転率も考慮しながら、総合的にバランスの取れた内装を検討しましょう。
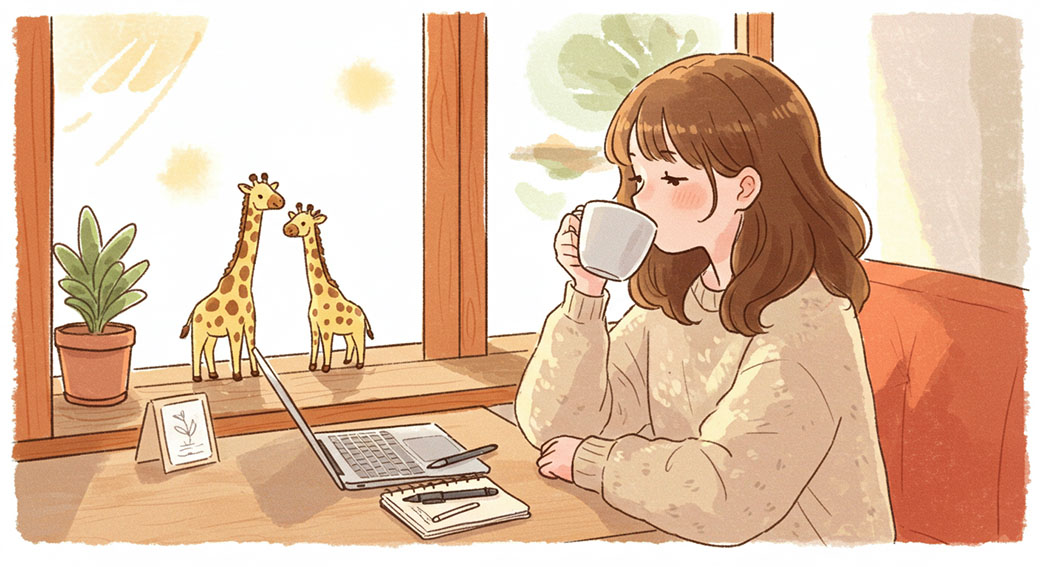
喫茶店とカフェの違いは?
喫茶店とカフェに大きな違いはありません。以前は「喫茶店営業許可」がありましたが、2021年6月の食品衛生法改正に伴い「飲食店営業許可」に統合されました。
そのため、法的な違いはなく、店名や店舗のコンセプトなどで区別されています。調理をともなうメニューも提供できるほか、条件を満たせばアルコールの販売も許可されています。

カフェ開業が甘いといわれる理由は?
カフェ開業は夢を持って始める人が多い一方で、準備段階の認識に甘さがあるといわれることがあります。設備やメニューに注力するあまり、経営の現実に目が向きにくい傾向があるためです。
物件選びや内装、SNSで映える空間づくりなどに意識が集中し、収支計画や市場分析といった経営面の準備が後回しになることもあります。その結果、思ったように集客できず、早期に閉店してしまうケースも少なくありません。
開業前には、店舗運営に必要なスキルや現実的な経営計画についても、十分に準備を進めることが重要です。

カフェ経営は難しい?
開業後のカフェ経営は、継続的に利益を出し続けるという視点でみると、難易度が高いといえます。リピーターの定着、季節変動への対応、競合との競争など、安定経営を維持するための課題はさまざまです。
とくに、固定費の管理や食材ロスの抑制、人件費とのバランス調整など、日々の運営には経営的な視点と柔軟な対応力が求められます。さらに、近年ではSNS運用やデリバリー対応など、求められるスキルが多様化している点も課題です。
カフェ経営を長く続けていくには、美味しいコーヒーを淹れるスキルだけでは不十分であり、総合的な経営能力が問われます。

喫茶店の開業資金はいくら?
喫茶店の開業資金は、内装や規模などによって変動しますが、平均すると500万円〜1,000万円程度の資金が必要です。とくに、物件取得や内装工事、設備購入など、初期投資に多くの費用がかかります。
たとえば、家賃の保証金や礼金、備品購入費に加えて、内装デザイン費や広告費などを含めると、数百万円単位の出費は避けられないでしょう。
コストを抑えたい場合は、居抜き物件を活用する方法がおすすめです。ただし、開業直後は売上が安定しない可能性があるため、運転資金として数か月分の人件費や家賃などを確保しておきましょう。

カフェのキッチンの内装はどう決める?
カフェのキッチンは、作業効率や衛生面に直結するため、計画的に設計することが重要です。見た目よりも「動きやすさ」と「安全性」を優先して考える必要があります。
調理やドリンク作りの動線がスムーズであれば、作業の無駄が減り、スタッフの負担軽減にもつながります。
たとえば、シンク・冷蔵庫・作業台・コンロを無理なく行き来できるレイアウトや、調理器具や食材の収納場所を確保しておくことがポイントです。また、保健所の基準を満たすために、手洗い場や換気設備などの設置も欠かせません。
キッチン設計は、店舗全体の運営効率に大きな影響を与える要素です。開業前に必要な設備や動線をしっかり検討し、実用性の高い設計を目指しましょう。

カフェのコンセプトの考え方は?
カフェを成功させるには、コンセプトを明確にすることが欠かせません。提供する商品やサービスだけでなく、内装や接客、BGMなど、店舗全体の世界観に一貫性をもたせるためです。
コンセプトは「誰に・何を・どのように届けるか」を軸に考えると整理しやすくなります。たとえば、働く女性に癒しの空間を提供するカフェなら、照明や香り、椅子の座り心地まで工夫するとよいでしょう。
このようにターゲット像を具体的に描き、その人が心地よく過ごせる空間設計や魅力的に感じるサービスに反映させる必要があります。

カフェ業界の将来性は?
カフェ業界は今後も一定の需要が見込まれ、将来性のある分野です。スペシャルティコーヒーやテイクアウト需要の高まり、ワークスペースとしての活用など、新たなニーズに対応できる店舗は成長の余地があります。
とくに、コンセプトやサービスに独自性があるカフェは競合との差別化が図れ、支持を集めやすい傾向にあります。市場は成熟しつつあるものの、柔軟な工夫次第で十分にチャンスを見いだせるでしょう。
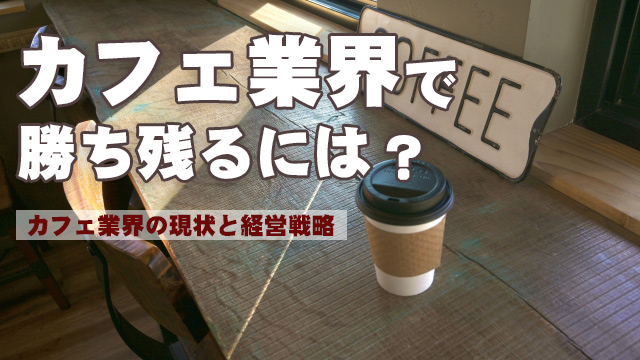
カフェ開業に必要な準備は?
カフェを開業するには、事前に多くの準備が必要です。開業後のトラブルを避けるためにも、段取りよく計画を立てましょう。
はじめに、コンセプトとターゲットを明確にし、事業計画や資金計画を作成します。そのうえで物件選び、内装設計、メニュー開発、仕入先の確保、必要な資格・許可の取得といった手順を進める流れです。
準備段階での情報収集や試算が不十分だと、運営に支障をきたす可能性があります。確実なスタートを切るためには、一つひとつの工程を丁寧に進めることが重要です。

まとめ

カフェを開業するには、資金計画や資格取得、物件選びなど多くの準備が必要です。とくに物件は初期費用や開業スピードに大きく影響するため、慎重に選定しましょう。
開業時のコストや工期を抑えたい場合は、内装や設備なども含めて借りられる「居抜き物件」の活用が効果的です。内装工事の負担を軽減できるほか、すぐに営業を始めやすいというメリットがあります。
居抜きの神様では、東京都を中心にカフェ開業を目指す方向けの小型居抜き物件を豊富に取り扱っています。内装や設備がすでに整っているため、開店コストと時間の大幅な削減が可能です。
独自の情報ルートで集めた独占未公開物件も限定公開しており、ご希望に沿った店舗を見つけられます。カフェの開業を検討中の方は、お気軽にご利用ください。













コメント