飲食店を開業する際には、営業許可をはじめとした複数の届出が必要です。店舗の規模や業態によって必要な許可が異なるほか、従業員を雇う場合には保険加入手続きも発生します。これらの届出は、提出先が異なるため、事前準備が欠かせません。
本記事では、飲食店開業に必要な主要な届出と、その手続きの流れについて詳しく解説します。開業を目指す方はぜひ参考にしてください。
飲食店開業時の届出一覧

まずは、飲食店を開業する際に必要な届出を以下にまとめました。届出には「必須」と「条件による」があり、それぞれの概要や期限を確認しておきましょう。
1.必須の届け出
以下の届け出はすべての飲食店に必要です。
| 届出名 | 提出先 | 提出期限 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 開業届(個人事業の開業届) | 税務署 | 開業から1ヵ月以内 | 個人事業を始めたことを税務署に届け出るための書類。税務上の青色申告などを選択可能にします。 |
| 飲食店営業許可 | 保健所 | 開業の1ヵ月前 | 飲食店営業に必須の許可。保健所の検査を受ける必要があります。 |
| 防火対象物使用開始届 | 消防署 | 開業の7日前まで | 店舗の消防設備や防火対策を消防署に報告する届出。 |
2.条件によって必要な届け出
店舗の規模や従業員の有無により追加で必要な場合があります。
| 届出名 | 提出先 | 概要 |
|---|---|---|
| 防火管理者選任届 | 消防署 | 一定規模以上の店舗や火気を扱う場合に必要。防火管理者の選任を届け出ます。 |
| 労災保険・雇用保険加入手続き | 労働基準監督署・公共職業安定所 | 従業員を雇う場合に必要。労災や雇用保険の適用手続きを行います。 |
| 防火対象物工事計画届出書 | 消防署 | 店舗内装などの工事を行う場合に提出。工事内容を消防署に届け出ます。 |
提出が必須のもの
はじめに開業する際に必ず提出する届出から紹介します。1つ目は一般に開業届などと呼ばれる個人事業の開業・廃業等届出書が挙げられます。この通称、開業届は個人が事業をはじめるとき税務署に提出することが義務付けられており、開業してから1ヵ月以内に提出しなければなりません。
2つ目は飲食店営業許可が挙げられます。これは保健所に対して申請するもので、保健所が実施する検査をクリアすることで許可を得られるものです。この許可がなければ飲食店として開業することはできないので、ある意味最重要項目ともいえるでしょう。申請期限は開業の1ヵ月前となっています。
3つ目は、防火対象物使用開始届です。これは消防署が管轄するエリアの飲食店の消防設備について把握することが目的となっています。お店で使用する消防設備には消防法で一定の基準が設けられているため、それに準じた設備を準備しなければなりません。なお、提出期限は開業の7日前までとなっています。
形態によって提出が必要になるもの
形態により提出する書類には、規模や設備によるもの、従業員を雇う際に必要となるものがあります。規模や設備で必要となるのは主に消防署への提出書類で、防火対象物工事等計画届出書、火を使用する設備等の設置届、防火管理者選任届などがあります。
なお、従業員を雇う際に必要となるのは、労働基準監督署に提出する労災保険加入手続き、公共職業安定所に提出する雇用保険の加入手続きが挙げられます。
個人事業の開業・廃業等届出書
個人事業の開業・廃業等届出書は、国税庁のホームページからダウンロードするか、最寄りの税務署で配布しています。ここでは提出にあたり注意点や手続きの流れを紹介していきます。
提出すべきメリット

開業届を提出することで、事業主としてさまざまな優遇制度や支援を受けられます。ここでは、開業届を提出する3つのメリットについて詳しく解説していきます。
青色申告を選べる
個人事業主の確定申告には白色申告と青色申告の2種類があり、開業届を提出することで青色申告を選択できるようになります。青色申告は、日々の取引を複式簿記で記帳する必要があるものの、最大65万円の特別控除を受けられるなど税制上の大きなメリットがあります。
とくに、飲食店経営では家族従業員への給与を経費として計上できることや、開業初期の赤字を3年間繰り越して相殺できる制度が、経営の安定化に役立つでしょう。
また、厨房機器といった減価償却資産も30万円未満であれば損金算入できることも、開業時の支出が多い飲食店では大きなメリットとなります。
ただし、それぞれの措置には一定の要件が設けられているため確認が必要です。青色申告には帳簿が必要となりますが、近年では専用のクラウドサービスや会計ソフトが充実しており、経理の知識が少なくても効率的に記帳・申告が行えるようになっています。
職業証明になる
開業届は個人事業主としての公的な証明書となります。飲食店の物件を契約する際の賃貸審査や、事業資金の融資申し込み時に求められる提出書類として活用できます。
また、事業主の子どもを保育所に預ける際の就労証明など、さまざまな場面で職業証明として利用できることがメリットです。
自身の事業を円滑に進めるうえで、開業届は欠かせない証明書類といえるでしょう。
小規模企業共済に加入できる
小規模企業共済は、個人事業主のための公的な退職金制度です。加入する際は確定申告の控えを提出しなければいけません。事業を始めたばかりは確定申告の控えがないため、開業届の控えが必要となります。
会社員と異なり、個人事業主には一般的な退職金制度がないため、小規模企業共済への加入は将来の生活保障として重要な役割を果たします。また、毎月の掛け金は所得控除の対象となるため、節税効果も期待できます。
掛け金は、月額1,000円〜最高70,000円の範囲内(500円単位)で自由に選択できるため、事業の収益状況に合わせて柔軟に設定できる点もメリットです。
手続きの流れ
個人事業の開業・廃業等届出書を入手したら、開業か廃業を選択する欄で「開業」に丸印をつけます。次に、所轄の税務署を記入し、書類の提出日・自宅または事務所の住所・代表者のマイナンバー・屋号・開業日を記入します。このとき、所轄の税務署は現住所のほかにも店舗の住所からも選択できるので、自身で選択するようにしましょう。
なお、青色申告承認申請書も一緒に提出する場合は、有りに丸印をつけて消費税に関する項目は一般的には無しに丸印をつけます。ここまで記入できたら具体的な事業内容を記入し、専従者がいる場合は、それも記入しておきましょう。この時点で会計士や税理士がいる方はその方の署名も必要です。すべての記入が終わったら所轄の税務署に提出すればOKです。
申請後のデメリット

開業届の提出にはさまざまなメリットがある一方で、いくつかのデメリットもあります。とくに、社会保障制度や税務面での変更が生じる可能性があるため、事前に確認が必要です。ここからは、主な3つのデメリットについて詳しく解説します。
失業手当が受けられない
失業手当の受給資格がある状態で個人事業を開始する場合は、とくに注意が必要です。開業届を提出すると、その時点で失業手当の受給資格が失われてしまいます。
失業手当は、求職活動をしている方への支援であるため、開業届を提出することで求職者とみなされなくなります。
個人事業を開始した場合は申告せねばならず、万が一、無申告で事業を開始して失業手当を受給し続けた場合は不正受給となります。不正受給をした場合は、最高で2倍の納付命令を受けるといった厳しい処分を受ける可能性があるため、注意しましょう。
扶養から外れる
開業届の提出により、配偶者の健康保険や厚生年金保険の被扶養者から外れる可能性があります。扶養から外れた場合は、国民健康保険や国民年金に加入して自身で保険料を負担する必要が生じるため、月々の固定支出として大きな負担となります。
ただし、事業収入が一定の基準を下回る場合は、引き続き被扶養者として認定される可能性があります。この基準は加入している健康保険組合によって異なるため、事前に勤務先の担当部署や健康保険組合に確認しておきましょう。
また、扶養からの削除時期や手続きについても確認が必要です。とくに開業初期は収入が安定しないことも多いため、慎重な判断と計画が求められます。
職業区分や所得によって税率が異なる

開業届に記載する職業は3種類の法廷業種に区分され、個人事業税の税率に直接影響します。個人事業税は、事務所や事業所のある都道府県に納付する地方税です。たとえば、東京都の場合は物品販売業や運送取扱業の場合は5%、畜産業や水産業は4% といったように税率が異なります。
また、年間で事業を行うと290万円の事業主控除が受けられるため、年間の所得が290万円以下の場合は課税されません。ただし、事業を行った期間が1年に満たない場合は、期間に応じて控除される額が異なるため、確認が必要です。
内容が細かく複雑なため、開業届を出す前に税理士への相談や、管轄の都道府県の税事務所への確認が大切です。とくに、複数の事業を営む場合は、主たる事業の判断基準などの確認も必要です。
また、申請時には記載した内容に誤りがないか、記入漏れがないかを十分確認して提出することが大切です。上述の通り、個人事業の開業・廃業等届出書の提出は開業から1ヵ月以内が期限となっています。この期限を過ぎてしまってもとくに罰則はありませんが、できるだけ期限内に手続きするようにしましょう。
飲食店営業許可
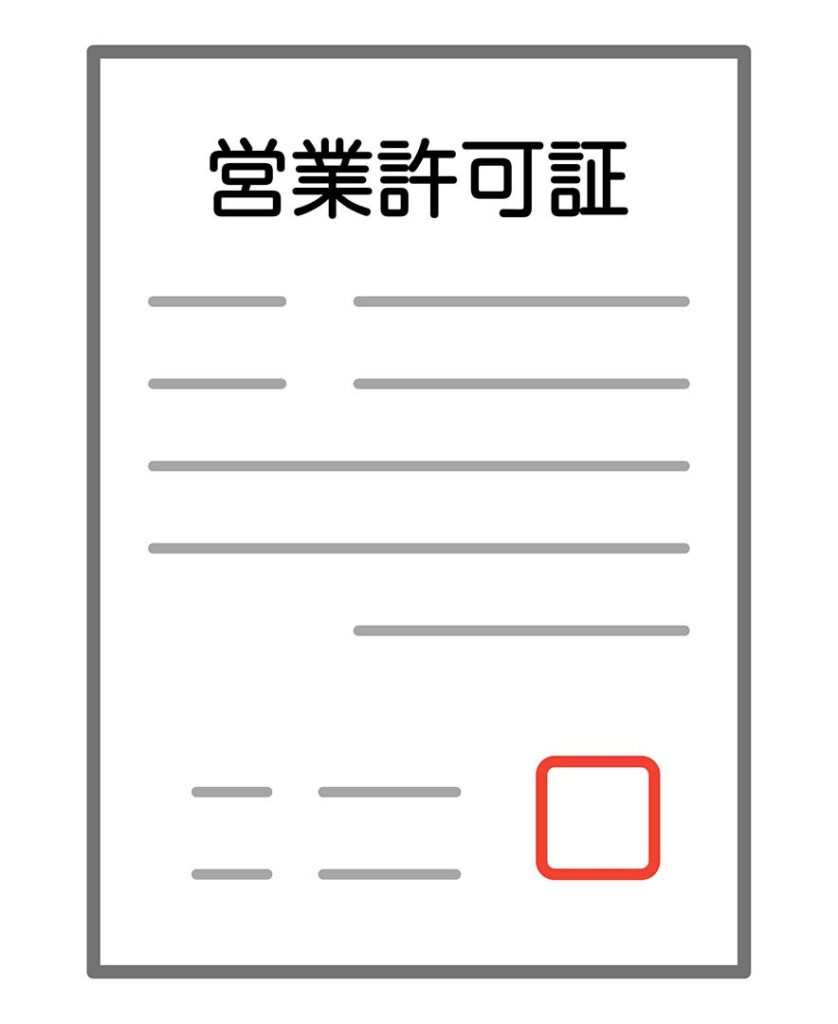
飲食店営業許可は、飲食店を営むうえで必要な許可であり申請先は保健所になります。店舗が複数ある場合は、一つひとつの店舗ごとに申請しなければなりません。
また、この許可は場所や設備に対する許可であり、経営途中で経営者が代わったとしても届出を出せば許可そのものを引き続くことができます。
ただ、この許可だけでは実質飲食店を営業することは難しく、食べ物を扱う上では食品衛生責任者の資格も必要です。次は、食品衛生責任者について解説していきます。
申請には食品衛生責任者の資格が必須
飲食店ではお店側での衛生管理が必要であり、常に食品や飲料、そのほかの衛生管理が行き届いていることが求められます。なお、店舗には食品衛生責任者を置くことが義務付けられているため、個人であったとしても飲食店を開業するなら必ず必要な資格となります。
食品衛生責任者の資格を保有するには、栄養士・調理師・製菓衛生師・食品衛生管理者などの資格を保有しているか、養成講習会を受講するか、そのほか行政が認める講習会を受講することが必須です。栄養士などの資格がない場合でも、そのほかの方法を実践することで資格を取得できます。
なお、店舗がある都道府県以外での受講でもOKなので、そのときの都合に合わせた受講が可能です。
手続きの流れ

飲食店営業許可の申請を行う際は、はじめに所轄の保健所に相談して申請を行います。その後、保健所による店舗の立入検査が行われ、基準をクリアすると飲食店営業許可証の発行を受けます。
防火対象物使用開始届
飲食店を営むうえでは、調理に関する飲食店営業許可のほかに火気に関する防火対象物使用開始届が必要です。飲食店営業許可と防火対象物使用開始届の両方を申請することで、火を使った料理を提供できるようになる、と考えていてよいでしょう。ここでは、防火対象物使用開始届がどのようなものなのか解説していきます。
防火対象物とは
防火対象物使用開始届は、消防署が管轄の設備について把握するためのもので、火気を扱う場合は営業をはじめる7日前までに消防署への提出が必要なものです。
また、お店を出すにあたり内装の修繕をする際にもこれらの工事に着手する7日前までに「防火対象物の工事等計画の届出」が必要になります。
大きく分けると、現状の店舗のまま飲食店を営む場合は、防火対象物使用開始届、工事をともなう場合は、防火対象物使用開始届と防火対象物の工事等計画の届出が必要になるということです。火気を扱う場合は、必須の届出となるだけに、事前かつ計画的に届け出るようにしましょう。
対象物の分類
| 防火対象物の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 特定防火対象物 | 不特定多数の人が利用する施設や、避難に時間がかかる施設を指します。 |
| ・劇場や映画館などの興行場 | 映画館、劇場、コンサートホールなど。 |
| ・飲食店等 | レストラン、カフェ、居酒屋、バーなど。 |
| ・百貨店やスーパー | 商業施設、ショッピングモール。 |
| ・宿泊施設 | ホテル、旅館など。 |
| ・病院や福祉施設 | 病院、介護施設、老人ホームなど。 |
| 非特定防火対象物 | 主に特定の人が利用する施設や、利用者が限定される施設を指します。 |
| ・事務所 | 一般的なオフィスビル。 |
| ・工場や倉庫 | 製造工場、物流倉庫など。 |
| ・学校や教育施設 | 学校、塾、幼稚園など。 |
防火対象物の目的
防火対象物を定める目的は、火災が発生した場合の被害を最小限に抑えることです。これには以下のような意義があります。
1.火災の早期発見と通報
消防用設備(火災報知器、スプリンクラーなど)の設置基準を守ることで、火災の早期対応が可能になります。
2.安全な避難の確保
避難経路の確保や防火管理者の選任を通じて、利用者や従業員の安全を確保します。
3.建物の耐火性向上
防火材を使用することで、火災による建物の損傷を減らします。
手続きの流れ

防火対象物使用開始届を提出する際は、所轄の消防署の公式ホームページで用意しているものを使用します。届出日や届出先の消防署名、届出者の個人情報、店舗については建物欄・事業所については事業所欄に所定の内容を記載します。店舗の工事が必要な場合は、工事等の各項目に必要事項を記載しましょう。
このほかに添付資料が必要となる場合は、それらも準備してください。代表的なものでは防火対象物概要表・案内図・平面図・詳細図・立面図・断面図・展開図・室内仕上表および建具表などが挙げられます。
また、必要に応じて防火管理者選任届出書・消防用設備設置届出書・消防計画の届出などの提出を求められることがあるので、こちらも準備しておくことをおすすめします。
飲食店の開業には届出だけでなく、全体の開業スケジュールの把握も必要です。こちらの記事では、飲食店の開業スケジュールについて、オープンまでにやることリストを解説しますので合わせてご覧ください。
こちらの記事では、飲食店を開業する際に必要な資格や手続きについて解説しています。資金の調達方法や目安も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。


まとめ

今回は飲食店を開業するにあたって必要となる届出について紹介しました。単純に個人事業主として開業届けを出すだけでなく飲食店営業許可や食品衛生責任者、防火対象物使用開始届など複数の届出が必要となるため、事前の準備はなかなか忙しいものとなるでしょう。
しかし、飲食店を営むという夢や目標を実現するためにはマストなものです。少々複雑な届出であったとしてもしっかり準備して取り組むことをおすすめします。また、店舗がまだ決まっていない場合や、これから物件を探す方は独自の非公開物件を扱う居抜きの神様にご相談ください。
「居抜きの神様」では、他のサイトでは公開されていない店舗を数多く保有しているほか、開業に関する手続きなどもお手伝いいたします。東京都を中心に関東一円、大阪の一部のエリア に展開しているので、飲食店の店舗選びのことならお任せください。













コメント